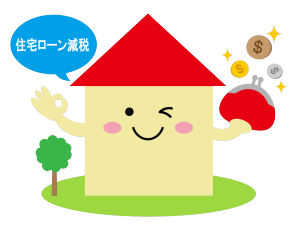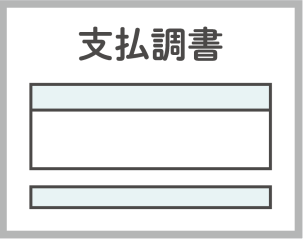概要
公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算しますが、外国の法令に基づき支給される年金がある方は、それも含めて計算します。
国外年金を外貨による支払で受けた場合は、支払を受けた時の電信売買相場の仲値(TTM)で日本円に換算して1年間の金額を合計した金額が、国外年金による公的年金等の(年間の)収入金額となります。
国外年金を邦貨(円)による支払で受けた場合(普通預金口座への日本円による振込みの方法による受領等)は、その日本円の1年間の金額を合計した金額が、国外年金による公的年金等の(年間の)収入金額となります。
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
ただし、平成27年分以後は、源泉徴収の対象となっていない年金(例えば、外国の制度に基づき国外において支払われる年金)がある場合には、公的年金等に係る申告不要制度は適用できません(所法121③)。
よって、通常、外国の法令に基づき支給される年金は源泉徴収の対象となっていないので、原則として、確定申告をすることになります。
ただし、所得税額等を計算した結果、確定申告を要しない場合もあります。例えば、公的年金等の雑所得の金額(公的年金等の収入金額-公的年金等控除額)より、基礎控除等の所得控除の合計額の方が大きければ、納税額0円であり申告の必要はないということになります。
国外年金の支給を受けた場合の誤りやすい事例
(誤った取扱い)
国民年金120万円と公的年金等に該当する米国年金200万円の収入がある者に対し、公的年金等に係る収入金額が400万円以下であるため、公的年金等に係る申告不要制度を適用し、確定申告書の提出は不要であると指導した。
(正しい取扱い)
源泉徴収の対象となっていない公的年金等がある場合には、公的年金等に係る申告不要制度は適用できない(所法121③)。
事例の場合、日本国内の源泉徴収義務者を通さずに支払われる米国年金は源泉徴収の対象となっていないため、公的年金等に係る申告不要制度は適用できない。ただし、所得税額等を計算した結果、確定申告を要しない場合もある。
令和6年版 誤りやすい事例(所得税法) 大阪国税局より
平成30年7月9日裁決(東裁(所)平30第18号)(棄却)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 審査請求人Xは、平成26年分、平成27年分及び平成28年分(以下、これらを併せて「本件各年分」という。)の所得税等について、いずれも法定申告期限内に申告(以下「本件各確定申告」という。)した。
本件各確定申告において、Xは、本件各年分に支払を受けたアメリカ合衆国からの年金(以下「本件各米国年金」という。)に係る所得を申告していなかった。
② Xは、税務調査において、調査担当職員から、本件各米国年金は公的年金等に係る雑所得に該当するとの指摘を受け、平成30年1月16日、本件各年分の所得税等の各修正申告書を所轄税務署長に提出した。
③ 所轄税務署長は、これに対し、平成30年2月27日付で、本件各年分の所得税等について、過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)をした。
④ Xは、平成30年3月3日、過少申告となったのは当該所得を申告に含める必要があることについて税務署等から何ら説明がなく、知り得なかったのであるから、国税通則法65条(過少申告加算税)4項(以下「本件条項」という。)に規定する「正当な理由」があるとして、本件各賦課決定処分の全部の取消しを求めた。
(2)本件の主な争点
本件各確定申告が過少申告となったことについて、本件条項に規定する「正当な理由」があると認められるか否かである。
(3)裁決要旨(棄却)
① Xは、本件各確定申告が過少申告となったのは、Xが米国年金を申告不要のものと認識し、申告に含める必要があることについて、年金事務所や税務署から説明がなく知ることができなかったからであり、年金事務所や税務署は説明義務を怠っていたのであるから、このような場合は、本件条項に規定する「正当な理由」があると認められる旨主張する。
② しかしながら、税務署等が個々の納税者に対して、ある所得を所得税等の申告に含める必要があることについて、事前に説明しなければならないとする法令上の規定はなく、税務署等はXが主張する説明義務を負うものではない。そして、申告納税制度の下においては、納税者自身が自己の判断と責任において、法令の規定に従って、適正な申告をしなければならないものであり、結局のところ、本件各確定申告が過少申告となったのは、Xが、米国年金に係る所得の申告の必要性を知らなかったという税法の不知又は当該所得の申告義務につき誤った解釈をした結果によるものといわざるを得ない。
③ したがって、本件各確定申告が過少申告となったことについて、真にXの責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお、Xに過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、Xの主張する事情は本件条項に規定する「正当な理由」があると認められる場合には該当しない。
平成30年8月28日裁決(関裁(所)平30第1号)(棄却)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 審査請求人Xは、平成15年4月27日以降、日本国内に住所を有する、所得税法2条《定義》1項3号に規定する居住者である。
② Xは、昭和63年から平成15年まで米国に滞在し、会社代表者を務めるなどして米国の社会保障制度に加入していたことから、米国の社会保障制度に基づく年金を受給しており、平成26年分及び平成27年分(以下「本件各年分」という。)において、X名義の普通預金口座への日本円による振込みの方法により受領した(以下、Xが受領した当該年金を「本件米国年金」という。)。
③ 米国の社会保障庁が発行した本件米国年金に係る支払報告書(以下「本件支払報告書」という。)には、いずれも「税率」欄に「00%」と記載され、「源泉徴収税額」欄には記載がなかった。
④ Xは、厚生労働省から受給した老齢基礎年金及び老齢厚生年金(以下、これらを併せて「本件老齢年金」という。)並びに本件米国年金はそれぞれ所得税法35条《雑所得》3項1号及び同項3号に規定する公的年金等に当たることから、いずれも同条1項に規定する雑所得に該当するものの、本件米国年金については、日米租税条約に基づき日本において課税の対象とされないこととなるとの考えから、本件米国年金を雑所得の収入金額に算入せずに本件各年分の所得税等の各確定申告書を、いずれも法定申告期限までに提出した。
⑤ 原処分庁は、平成30年2月23日付で、本件米国年金は日本において雑所得として課税の対象になるとして、所得税等の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)をした。
⑥ Xは、本件各更正処分に不服があるとして、平成30年3月12日に審査請求をした。
(2)本件の主な争点
日本における本件米国年金に対する課税は、日米租税条約に反するか否かである。
(3)裁決要旨(棄却)
① 両締約国間における課税権の配分を目的とする規定の一つとして、日米租税条約17条1及び同条約18条2は、政府職員の一定の退職年金等を除き、一方の締約国の居住者が受益者である退職年金等に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる旨規定している。なお、この趣旨は、過去の勤務の対価としての性格をも有する退職年金等につき通常の人的役務提供の場合と同様に役務提供地で課税することとした場合、一般に少額所得者が多いと思われる退職年金等の受益者がその居住地国において外国税額を控除しきれないことが少なくないと考えられることなどから、居住地国においてのみ課税することを認めることとしているものと解される。
② したがって、日米租税条約17条1及び同条約18条2の各規定により、本件米国年金に対してはXの居住地国である日本においてのみ課税することができ、ほかに同条約において本件米国年金に対する課税を制限するような規定もないことから、日本における本件米国年金に対する課税は、日米租税条約に反しない。
③ Xは、日米租税条約17条1の規定に基づき米国年金を日本においても課税することは同条約の前文に記載された同条約の理念に反する旨主張するが、退職年金等については、同条1の規定により二重課税の回避を目的として居住地国においてのみ課税することができ、米国年金については米国では課税されていない。