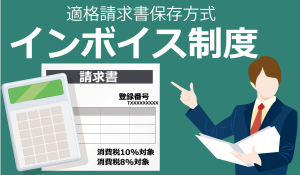概要
住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合に限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)については、消費税は課されません(消法6①、別表第二13)。
貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合
貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが「明らかにされている場合」とは、当該契約において当該貸付けに係る用途が「明らかにされていない場合」に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含み、例えば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当します(消基通6-13-11、令和6年3月15日裁決・関裁(諸)令5第30号)。
(1) 住宅の賃借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
(2) 住宅の賃借人が当該住宅を第三者に転貸している場合であって、当該賃借人と入居者である転借人との間の契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合
(3) 住宅の賃借人が当該住宅を第三者に転貸している場合であって、当該賃借人と入居者である転借人との間の契約において貸付けに係る用途が明らかにされていないが、当該転借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
当該契約において当該貸付けに係る用途が「明らかにされていない場合」には、例えば、住宅の貸付けに係る契約において、住宅を居住用又は事業用どちらでも使用することができることとされている場合が含まれます(消基通6-13-10)。
令和2年度税制改正
令和2年度税制改正により改正されましたが、令和2年度税制改正の解説749頁では、以下のように解説しています。
社会政策的な配慮から、住宅の貸付けについては非課税とされています。この住宅の貸付けについては、一義的には賃貸借契約により合意した用途に基づいて課税関係を判定できるようにするため、制度上、住宅の貸付けは「貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る」こととされていました。
建物の貸付けにあたっては、実務上住宅の貸付け(人の居住用)か否かを明らかにして契約されており、課税関係の判断に迷うことはないと考えられますが、住宅の貸付けに係る契約においてその用途が特定されていないなどの場合も考えられるため、今般の居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除制度の適正化にあわせて、契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の判断基準を明確化することとされました。
具体的には、住宅の貸付けに係る契約において、当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなときは、当該住宅の貸付けについて消費税を非課税とすることとされました(消法別表第1十三)。この結果、契約において貸付けの用途が不明の場合については、その貸付けの状況、例えば、賃借人が個人であるか否かや、建物の転貸の状況、建物の構造や設備などから、人の居住の用に供されていることが明らかかどうかを、判断することとなります。
一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合
一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合は、住宅の貸付けから除かれ、非課税とはなりません(消令16の2)。
イ 貸付期間が1月未満の場合
ロ 旅館業法2条1項に規定する旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業)に係る施設の貸付けに該当する場合
例えば、ホテル、旅館、リゾートマンション、貸別荘等は、その利用期間が1月以上となる場合であっても、非課税とはなりません(消基通6-13-4)。
「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます(旅館法2②)。
「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいいます(旅館法2③)。
「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいいます(旅館法2④)。なお、学生又は独身者等が利用するいわゆる下宿は、旅館業法上の「下宿営業」には該当しません(消基通6-13-4)。
昭和61年3月31日付厚生省指導課長通知によれば、旅館業法にいう「人を宿泊させる営業」とは、以下の2点を条件として有するものであるとされています。
| 1 施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあるものと社会通念上認められること 2 施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業しているものであること |
そのため、「旅館業法運用上の疑義について(昭和63年1月29日衛指第23号)」では、以下の理由により、ウィークリーマンションは旅館業法の適用対象施設として取り扱われるとされています。
| 1 契約上、利用期間中の室内の清掃等の維持管理は利用者が行うこととされているが、1~2週間程度という1月に満たない短期間のうちに、会社の出張、研修、受験等の特定の目的で不特定多数の利用者が反復して利用するものであること等、施設の管理・経営形態を総体的にみると、利用者交替時の室内の清掃・寝具類の管理等、施設の衛生管理の基本的な部分はなお営業者の責任において確保されていると見るべきものであることから、本施設の衛生上の維持管理責任は、社会通念上、営業者にあるとみられる。 2 また、生活の本拠の有無についても、利用の期間、目的等からみて、本施設には利用者の生活の本拠はないとみられる。 |
住宅の範囲
住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほかマンション、アパート、社宅、寮等が含まれます。
庭、塀等住宅の附属設備及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備等通常住宅に付随する施設は、住宅に含まれます(消基通6-13-1)。
なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはなりません。
駐車場付き住宅の貸付け
駐車場付き住宅における駐車場の貸付けは、次のいずれにも該当する場合、非課税となります(消基通6-13-3)。
イ 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合
ロ 家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
名古屋地裁平成17年3月3日判決(税資255号-68(順号9949))要旨
本件通達(消基通6-13-3)は、駐車場の貸付けが住宅の附属施設として一体として行われる場合であって、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものに限り、全体を住宅の貸付けとして扱い、駐車場部分についても非課税とする取扱いを定めているところ、このような基準は、駐車場の貸付けが原則として課税売上げに当たり、住宅の貸付けに含まれて両者の区別が不可能ないし著しく困難である場合に例外的に非課税とする消費税法の上記趣旨に合致すること、実際にも、住宅の使用料とは別個に駐車場使用料等が定められ、収受されている場合には、住宅の貸付けと駐車場の貸付けとの区別が容易であると考えられることなどを考慮すると、その合理性を十分に肯認することができる。
店舗等併設住宅の貸付け
店舗等併設住宅の居住用部分は住宅に該当しますから、その居住用部分の貸付けは非課税となります(基通6-13-5)。
この場合において、建物の貸付けに係る対価の額を住宅に係る対価の額と事業用の施設に係る対価の額とに面積比等により合理的に区分することになります。
平成22年6月25日裁決(裁事79集591頁)要旨
請求人は、関係法人に有料老人ホーム施設として賃貸した建物のうち、介護職員が使用する事務室、スタッフステーション、宿直室、厨房等は、いずれも当該施設の入居者が使用するものではなく、住宅の貸付けに該当しないから非課税とならない旨主張する。しかしながら、消費税法上、非課税となる住宅の貸付けの範囲の判定に当たっては、住宅に係る賃借人が日常生活を送るために必要な場所と認められる部分はすべて住宅に含まれると解するのが相当であるところ、介護付有料老人ホームは、単なる寝食の場ではなく、入居した老人が介護等のサービスを受けながら日常生活を営む場であるから、介護付有料老人ホーム用の当該建物の内部に設置された事務室、スタッフステーション、宿直室、厨房等の介護サービスを提供するための施設は、入居者が日常生活を送る上で必要な部分と認められることから、これらの部分の貸付けは非課税となる住宅の貸付けに該当する。
住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の場合
有料老人ホーム、ケア付住宅、食事付の貸間、食事付の寄宿舎等のように、1つの契約で非課税となる住宅の貸付けと課税となる役務の提供を約している場合には、この契約に係る対価の額を住宅の貸付けに係る対価の額と役務の提供に係る対価の額に合理的に区分します(消基通6-13-6)。
転貸する場合
借主が他に転貸する場合であっても、転貸後において住宅として使用されることが契約上において明らかにされている場合は、住宅の貸付けとして非課税とされます(消基通6-13-7)。
例えば、事業者が社宅として借り受ける場合であり、契約において従業員等が居住の用に供することが明らかであれば非課税とされます。この場合において、貸主へ支払われる家賃と社員から徴収される賃料のいずれも非課税となります。
居住用マンションの所有者等が不動産業者等に一括して貸し付ける場合のいわゆる丸貸しマンション等も非課税となります。
用途変更の場合
住宅として貸し付けられた建物について、契約当事者間で住宅以外の用途に契約変更した場合には、契約変更後のその建物の貸付けは課税となります(消基通6-13-8)。
賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに、その賃借人において事業の用に供した場合、その建物の借受けは、当初の契約により非課税となります(消基通6-13-8(注))。
例えば、建物の用途を住宅として賃貸借契約している場合、後日、賃借人が賃貸人に無断(契約変更を行っていない場合)で事業所として使用しても、当該建物の借受けは、賃借人の課税仕入れに該当せず、当該賃借料は仕入税額控除の対象とすることはできません(消法2①十二カッコ書き、30①)。
非課税となるのは、契約において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合に限られるため、その契約を変更しない限り当初の契約により非課税となります。
対価たる家賃の範囲
対価たる家賃の範囲は以下の通りです(消基通6-13-9)。
イ 家賃には、月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分を含みます。
ロ 共同住宅における共用部分に係る費用(エレベーターの運行費用、廊下等の光熱費、集会所の維持費等)を入居者が応分に負担する、いわゆる共益費も家賃に含まれます。
共益費以外の専有部分の電気、ガス、水道等の利用料は、非課税とされる住宅の貸付けに該当しないことから、課税されます。
〇国税庁HP質疑応答事例「集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm
住宅用として貸し付けている建物の譲渡
住宅用として貸し付けている建物の譲渡は、課税の対象となります。
関連記事
令和6年3月15日裁決(関裁(諸)令5第30号)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 審査請求人Xは、不動産賃貸業を営む個人事業者である。
Xは、平成31年4月1日から令和元年6月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)から消費税課税事業者を選択しており、また、その課税期間は、平成31年4月1日以降、3月ごとの期間であった。
② 合同会社Aは、不動産の所有、賃貸、管理等を目的として設立された法人である。
なお、本件課税期間において、XはAの業務執行社員であり、Xの妻がAの代表社員であった。
③ Xは、平成24年12月20日に、建築管理会社Kとの間で、注文者をX、請負者をKとし、構造を木造2階建て1棟6戸とする共同住宅(以下「本件建物」という。)に係る工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)を締結し、本件工事請負契約に係る契約書(以下「本件工事請負契約書」という。)を交わした。
なお、本件工事請負契約は、平成30年7月7日から平成31年4月25日までの間に4回にわたる契約変更を経て、最終的な契約内容は、請負代金総額が8406万円〔消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含めた金額〕、建物の構造が鉄骨造3階建て1棟9戸となった。
④ Xは、平成31年3月31日に、Aとの間で、XがAに対し、本件建物及び本件建物に付随する駐車場(以下「本件駐車場」といい、本件建物と併せて「本件建物等」という。)を賃貸する旨の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」といい、本件賃貸借契約による本件建物の貸付けを「本件貸付け」という。)を締結し、本件賃貸借契約に係る契約書(以下「本件賃貸借契約書」という。)を交わした。
なお、本件賃貸借契約書には、要旨次のとおり記載されていた。
(イ) Xは、本件建物については、たとえ居住用と明記されていたとしてもその本心は事業用・居住用などの制限を設けることなく、賃貸経営の安定化と収益基盤の確立のために、その用途を問わないと考えている。そのため、本件建物について、賃借人である不動産賃貸業を目的とするAに対し、使用用途を問わない旨の意思表示を本件賃貸借契約において明らかにする。ただし、Aの転貸用途を制限するものではない。
(ロ) 賃借人の使用用途については、Xの確固として完全な意思表示に基づきその使用用途を問わない。
⑤ Aは、平成31年4月24日に、Kとの間で、賃貸人をA、賃借人をKとする旨の本件建物等に係る賃貸借契約(以下「本件一括賃貸借契約」という。)を締結し、本件一括賃貸借契約に係る契約書(以下「本件一括賃貸借契約書」という。)を交わした。
なお、本件一括賃貸借契約書には、要旨次のとおり記載されていた。
(イ) 本件一括賃貸借契約は、Kが本件建物等を一括賃借の上、これを居住用の目的にて任意に第三者に転貸し、Aに一定の賃料を支払うことを目的とし、Aは、Kに対し、Kが本件建物を居住用の目的にて任意に転借人に転貸することをあらかじめ承諾する。
また、Aは、Kが一括賃借した本件建物等に関して行う上記目的に従った運用を妨げる行為をしてはならない。
(ロ) A及びKは、本契約期間中において、本契約に特段の定めがある場合を除きいずれか一方による一方的な解約の申し入れはできないものとする。
⑥ Xは、平成31年4月25日に本件建物の引渡しを受け、同日付で、Xを所有者とする本件建物の所有権保存登記がされた。なお、当該登記において、本件建物の種類は、共同住宅とされている。
⑦ Xは、令和元年8月28日に、本件課税期間の消費税等について、確定申告書(以下「本件申告書」という。)を原処分庁に提出して、確定申告した(以下、本件申告書に係る申告を「本件申告」という。)。
なお、Xは、本件申告書の作成に当たり、課税標準額に対する消費税額から控除する消費税額(以下「控除対象仕入税額」という。)の計算において、個別対応方式を採用し、本件建物等に係る課税仕入れについては、用途区分を課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとして控除対象仕入税額を計算していた。
⑧ 原処分庁は、これに対し、本件貸付けは非課税取引である「住宅の貸付け」に該当するとして、令和4年11月14日付で、本件課税期間の消費税等の更正処分等(以下「本件更正処分等」という。)をした。
⑨ Xが、本件貸付けは「住宅の貸付け」に該当しないとして、原処分の全部の取消しを求めた。
(2)本件の主な争点
本件貸付けが、非課税取引である「住宅の貸付け」に該当するか否かである。
(3)判断要旨(棄却)
① 住宅の貸付けが非課税取引とされている趣旨は、住宅の貸付けを行う事業者が賃借人に対し、消費税相当額を転嫁しないことにより、住宅賃借人を政策的に保護することにあると解される。
そして、建物の貸付けが非課税取引である「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において、最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。
② 本件貸付けが非課税取引である「住宅の貸付け」に該当するか否かは、最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かによることから、(イ)本件賃貸借契約書の契約条項だけでなく、(ロ)当該契約締結に至る経緯をはじめ、(ハ)本件建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を踏まえ、以下において検討する。
③ まず、(イ)本件賃貸借契約書の契約条項についてみると、賃貸借の金額については消費税等込の金額とされており、また、Xの確固として完全な意思表示に基づき、本件建物の使用用途は問わず、Xの本心も、本件建物について事業用・居住用などの制限は設けない旨記載されている。
しかしながら、賃貸借の内容である本件建物の名称は、Kが商標登録している賃貸「住宅」ブランドが使用されていることからすれば、本件賃貸借契約は、AがKに対し本件建物を住宅として転貸することが前提とされていたといえる。
④ 次に、(ロ)当該契約締結に至る経緯についてみると、本件建物は、Xの注文により建築されたものであるところ、本件工事請負契約書の記載からは、Xが、建物所有者に対するKによる賃貸住宅経営サポートを利用することを予定していたことが認められる。
また、本件建物に関する事業計画書におけるXの月手取収入及び借入金の返済計画は、Kからの一括賃料収入を前提に作成されており、Xは、本件工事請負契約の締結に際し、事業計画書のほか、建物完成後に締結予定の建物賃貸借契約等の内容の説明を確認したとして本件契約時確認書に署名及び押印しており、さらに、本件着工確認書には、X及びKが本件工事請負契約書における上記特約事項を再度確認する旨のほか、Xの都合により当該建物賃貸借契約を締結しない場合には、Xは損害賠償責任等を負う旨が記載されている。
そして、本件建物の名称は、本件工事請負契約の段階から、仮称ながら、Kの賃貸「住宅」ブランドと同一名称になっていた。
これらの事実関係からすれば、本件賃貸借契約の締結に至る経緯の点でみても、本件建物は、住宅として賃貸されることを予定して建築され、その後も、Kが本件建物を住宅として転貸借の目的とすることが一貫して予定されており、Xもそのことを認識した上で、本件建物を注文し、本件賃貸借契約が締結されるに至ったといえる。
⑤ さらに、(ハ)本件建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情についてみると、本件建物の引渡時における建物の種類は、共同住宅として登記されている。
Xは、Kの展開する賃貸「住宅」ブランドである名称を用い、賃貸住宅経営サポートの利用を予定して本件賃貸借契約を締結している。
これらによれば、本件建物の種類や用途等によっても、本件賃貸借契約の締結時点において、本件建物は、共同住宅として、最終的な用途を居住用としていたものといえる。
本件賃貸借契約書は、本件建物をKに転貸することを前提とした内容であり、また、本件賃貸借契約の締結から約1か月後に締結された一括賃貸借契約書には、Kが本件建物等を一括賃借の上、これを居住用の目的にて任意の第三者に転貸する旨、AはKの目的に従った運用を妨げる行為をしてはならない旨、及び契約当事者のいずれか一方による一方的な解約の申し入れはできない旨を定めていることからしても、X、A及びKの3者は、本件賃貸借契約締結以前より、本件建物等をKに対し一括賃貸の上、これを居住用として任意の第三者に転貸する予定であったことを認識していたといえる。これらによれば、本件賃貸借契約書において、本件建物の使用用途を問わない旨明記されていたとしても、Xは、本件賃貸借契約の締結時点で、最終的に本件建物を借り受ける者により、本件建物が居住用以外の用途に利用されることを想定していなかったといえる。
⑥ 以上によれば、本件賃貸借契約は、Aが本件建物をKに転貸し、本件建物を居住用として再転貸することを前提にしたものであり、本件貸付けは、本件賃貸借契約において、最終的に本件建物を賃借する者により本件建物が居住の用に供されることが明らかにされているものであると認められるから、別表第一(現行、別表第二)第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。