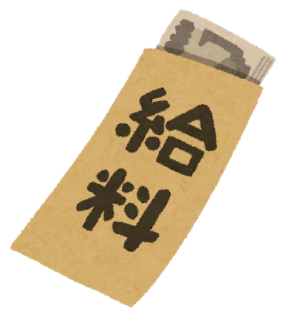概要
国税通則法によれば、法人税の申告をしたが、納付すべき税額に不足があるときは、税務署長の更正があるまでは、修正申告をすることができます(国法19)。また、納付すべき税額が過大であるときは、更正の請求により課税所得の是正を求めることになります(国法23)。
一方、法人税基本通達によれば、当該事業年度前の各事業年度においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するとされています(法基通2-2-16)。
つまり、当期に契約の解除又は取消し、返品等の事実が生じた場合は、前期以前において計上した売上高等(益金)については、過去に遡って直す(更正の請求)のではなく、当期の損金(前期損益修正損)として計算をするということです。
このような処理をする理由について、法人税基本通達逐条解説(税務研究会出版局)では、以下のように解説しています。
「法人税における課税所得の計算は、いわゆる『継続企業の原則』に従い、当期において生じた収益と当期において生じた費用・損失とを対応させ、その差額概念として所得を測定するという建前になっている。この場合の当期の収益又は費用・損失については、その発生原因が何であるかを問わず、当期において生じたものであれば全て当期に属する損益として認識するという考え方がとられているから、仮に既往に計上した売上高について当期に契約解除等があった場合でも、その契約解除等は、当期に売上げの取消しによる損失が発生する原因にすぎないとみることになる。」
なお、過去の多くの裁判例でも、この通達の取扱いは容認されています(横浜地裁昭和60年7月3日判決・昭和56年(行ウ)23号、東京高裁昭和61年11月11日判決・昭和60年(行コ)59号、最高裁昭和62年7月10日判決第二小法廷判決・昭和62年(行ツ)18号、東京地裁平成25年10月30日判決・訟務月報60巻12号2668頁、東京高裁平成26年4月23日判決・訟務月報60巻12号2655頁、大阪地裁平成30年1月15日判決・税資268号-2(順号13107)、最高裁令和2年7月2日第一小法廷判決・税資270号-66(順号13426))。
問題は、国税通則法における更正の請求(国法23)と、法人税基本通達2-2-16における前期損益修正損との関係をどのように考えるかということです。また、国税通則法における修正申告(国法19)と、前期損益修正益との関係をどのように考えるかということです。
これについては、法人税基本通達2-2-16で記載されているような場合、つまり、過去の事業年度の経理処理自体は正しかったが、当期に契約解除等のような特別なことがあった場合は、当期において前期損益修正損で処理をするが、そのような場合でないときは、対象の過去事業年度分において、更正の請求をすべきではないかと思われます。
例えば、過去事業年度において損金算入すべきであったが、自社の単なる経理処理のミスで資産計上した(損金算入しなかった)というような場合は、そのミスした事業年度分について、更正の請求により課税所得の是正を求めることになると思います。
なお、更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内に限りできるものであるため、その期限を過ぎると更正の請求はできません。更正の請求の期限が過ぎている過年分(7~8年前)の外注費漏れを当期の損金の額に算入する処理をしたが、認められないとされた事例(東京地裁平成27年9月25日判決・税資265号-142(順号12725)、東京高裁平成28年3月23日判決・税資266号-52(順号12830)、最高裁平成28年10月27日決定・税資266号-147(順号12925))があります。
また、過去事業年度において資産計上すべきであったが、自社の単なる経理処理のミスで損金算入したというような場合は、修正申告をすべきことになると思います。
前期損益修正益・前期損益修正損の経理処理で全て済むならば、会社側で所得のコントールが簡単にできてしまいます。そのため、法人税基本通達2-2-16で記載されているような特別な場合に、前期損益修正損として経理処理ができ、そうではない単なる経理ミスの場合はできないと考えるべきかと思われます。
東京高裁平成28年3月23日判決(税資266号-52(順号12830))では、この点につき、以下のように判示しています。
「ある事業年度に損金として算入すべきであったのにそれを失念し、それを後の事業年度に発見したという単なる計上漏れのような場合において、企業会計上行われている前期損益修正の処理を法人税法上も是認し、後の事業年度で計上することを認めると、本来計上すべきであった事業年度で計上することができるほか、計上漏れを発見した事業年度においても計上することが可能となり、同一の費用や損失を複数の事業年度において計上することができることになって、こうした事態は、恣意の介在する余地が生じることとなり、事実に即して合理的に計算されているともいえず、公平な所得計算を行うべきであるという同法上の要請に反するものといわざるを得ず、また、同法上、修正申告や更正の制度があり、後に修正すべきことが発覚した場合、過去の事業年度に遡って修正することが予定されているから、過年度の計上漏れを修正するための前期損益修正を公正処理基準に該当すると認めることができない。」
法人税基本通達2-2-16(前期損益修正)
当該事業年度前の各事業年度においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
破産会社が過払金返還債権に係る不当利得返還義務を負うことが確定したとしても、その義務に係る損失はその損失が生じた日の属する事業年度において損金の額に算入すべきであり、更正の請求が認められないとされた事例-大阪地裁平成30年1月15日判決(税資268号-2(順号13107))、大阪高裁平成30年10月19日判決(税資268号-94(順号13199))、最高裁令和2年7月2日第一小法廷判決(税資270号-66(順号13426))
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 破産者株式会社A(以下「A社」という。)は、各事業年度(平成7年度~平成17年度のうち平成11年度を除いた年度。以下「本件各事業年度」という。)において、利息制限法1条に規定する制限利率(以下、「制限利率」という。)を超える利息の定めを含む金銭消費貸借契約に基づき、制限利率を超える約定利息及び遅延損害金(以下、併せて「制限超過利息」という。)の支払を受け、これに係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告(以下「本件申告」という。)をした。
② その後、A社に対する破産手続(以下「本件破産手続」という。)において、一般調査期間の経過をもって総額555億3373万円余の過払金返還請求権が破産債権として確定し(以下、当該過払金返還請求権を「本件過払金返還債権1」という。)、更に、特別調査期間の経過をもって総額3億0119万円余の過払金返還請求権(以下、当該過払金返還請求権を「本件過払金返還債権2」という。)が破産債権として確定した。
③ そこで、A社の破産管財人であるX(原告、控訴人、被上告人)は、本件過払金返還債権1が破産債権者表に記載され、確定判決と同一の効力により確定したことを前提に、本件各事業年度に計上した益金のうち、本件過払金返還債権1に対応する制限超過利息部分が過大であったとして、国税通則法(以下「通則法」という。)23条2項1号に基づき、A社の本件各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の請求(以下「本件各更正の請求」という。)をしたところ、所轄税務署長から、更正をすべき理由がないとする各通知処分(以下「本件各通知処分」という。)を受けた。
④ Xは、これを不服とし、本件各通知処分の取消しを求めて、本訴を提起した。
(2)本件の主な争点
本件過払金返還債権1が破産債権者表に記載され、当該債権に係る不当利得返還義務が確定判決と同一の効力により確定したことをもって、本件各更正の請求が通則法23条1項及び2項所定の要件を満たすかである。
(3)一審判決要旨(棄却)(控訴)
① 当事者間において約定の利息・損害金として収受され、貸主である法人において制限超過部分が元本に充当されたものとして処理することなく、依然として従前どおりの元本が残存するものとして取り扱っている以上、当該制限超過部分をも含めて、現実に収受された約定の利息・損害金の全部は益金の額に算入され、当該法人の所得として課税の対象となるものと解される(最高裁昭和46年11月16日判決)。そうすると、当該利息を益金の額に算入した当初の申告は、法人税法に照らして正当な計算に基づくものであるということができる。
② 制限超過利息を当該利息が収受された事業年度の収益に計上することが法人税法に照らして正当な計算といえる場合において、その後の事業年度に、当該利息が私法上は無効な利息の契約に係るものであることにより当該利息等に係る不当利得返還義務を負うことが判決等により確定したときには、当該義務に係る損失が生じた日の属する事業年度において、不当利得として返還すべき利息を損金と取り扱い、企業会計原則における前期損益修正と同様の処理をすることが、事業年度による期間損益計算に基づいて課税を行うという法人税法の所得計算及び課税の在り方に合致するものといえる。
③ 平成22年度税制改正後の法人税法は、破産手続開始決定を受けて解散した法人に対しても、通常の法人と同様に各事業年度の所得(同法22条)を課税標準とする法人税を課税するものとしている。
④ 以上検討したところによれば、A社につき、過払金返還債権1のとおりの不当利得返還義務を負うことが確定判決と同一の効力を有する破産債権者表により確定したという事情があったとしても、当該事情による本件破産会社の所得の計算は、前期損益修正により、前記義務に係る損失が生じた日の属する事業年度において、当該損失を損金の額に算入する方法で処理されるものと解するのが相当であって、本件申告に係る課税標準等又は税額等の計算を遡って修正すべきものということはできない。したがって、前記事情をもって、通則法23条1項1号に該当するということもできない。
(4)控訴審判決要旨(原判決一部取消)(国側上告受理申立て)
① 当裁判所は、XがA社についてした各事業年度の決算を修正する会計処理は法人税法22条4項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に合致するものであり是認されるべきであったから、国税通則法23条1項1号に該当するところ、本件破産手続において破産会社が過払金返還債権に係る不当利得返還義務を負うことが確定判決と同一の効力を有する破産債権者表の記載により確定し、その結果、破産会社に生じていた経済的成果が失われたか又はこれと同視できる状態に至ったと解されることにより、本件申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実と異なることが確定したというべきであるから、同確定の日から2か月以内にされた各更正の請求は理由があり、これに理由がないとした各通知処分はいずれも違法であると判断する。
② 本件のように、制限超過利息を収受した法人が、当該利息を益金の額に算入して申告を行った後、破産手続開始決定を受け、その後の清算事業年度に、当該利息が私法上は無効な利息の契約に係るものであることにより当該利息相当額の不当利得返還義務及びこれに対する法定利息の支払義務を負うことが確定判決と同一の効力を有する破産債権者表の記載により確定した場合の収益・費用等の帰属年度に関し、前期損益修正による処理又は過年度遡及会計基準による遡及処理のみが公正処理基準に合致する唯一の会計処理としなければならないと解するのは相当ではない。
③ A社の場合は、(イ)企業会計基準が全面的に適用されるべき理由はなく、(ロ)会社法上も計算書類関係諸規定は適用されない上、(ハ)過去の確定決算を修正しても、通常の株式会社の場合のような弊害が生じることもないのであるから、本件会計処理は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行と矛盾しないし、(ニ)Xが本件会計処理を行うことは、破産手続の目的に照らして合理的なものというべきであり、法人税法の企図する公平な所得計算という要請に反するものでもないから、法人税法上も、公正処理基準に合致するものとしてこれを是認すべきものと解すべきである。
④ 本件会計処理は公正処理基準に合致するから、各事業年度に計上した益金の額のうち、過払金返還債権1に対応する制限超過利息部分が過大であったことになり、後発的事由により結果的に納税申告書に記載した課税標準等及び税額等の計算が国税に関する法律(法人税)の規定に従っていなかったことになる。
したがって、本件各更正の請求に理由がない旨を通知した各通知処分は違法であり、Xの主位的請求に基づき、更正すべき範囲の額は、Xの当審における不服の範囲内において取消しを免れない。
(5)上告審判決要旨(原判決破棄・被上告人の控訴棄却)(確定)
① 原審は、本件各更正の請求は国税通則法23条2項1号及び同条1項1号の各要件を満たすとして、主位的請求を認容した。しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。
② 法人税法は、事業年度ごとに区切って収益等の額の計算を行うことの例外として、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し(57条)等の制度を設け、また、解散した法人については、残余財産がないと見込まれる場合における期限切れ欠損金相当額の損金算入(59条3項)等の制度を設けている。課税関係の調整が図られる場合を定めたこのような特別の規定が、破産者である法人についても適用されることを前提とし、具体的な要件と手続を詳細に定めていることからすれば、同法は、破産者である法人であっても、特別に定められた要件と手続の下においてのみ事業年度を超えた課税関係の調整を行うことを原則としているものと解される。
③ そして、同法及びその関係法令においては、法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし、その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合に前期損益修正と異なる取扱いを許容する特別の規定は見当たらず、また、企業会計上も、上記の場合に過年度の収益を減額させる計算をすることが公正妥当な会計慣行として確立していることはうかがわれないことからすると、法人税法が上記の場合について上記原則に対する例外を許容しているものと解することはできない。このことは、上記不当利得返還請求権に係る破産債権の一部ないし全部につき現に配当がされ、また、当該法人が現に遡って決算を修正する処理をしたとしても異なるものではない。そうすると、上記の場合において、当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは、公正処理基準に従ったものということはできないと解するのが相当である。
④ これを本件についてみると、本件各事業年度に制限超過利息等を受領したA社が、これを本件各事業年度の益金の額に算入して行った本件各申告はもとより正当であったといえるところ、その後の事業年度に本件債権1が破産手続において確定したことにより、本件各事業年度に遡って益金の額を減額する計算をすることは、本件債権1の一部につき現に配当がされたか否かにかかわらず、公正処理基準に従ったものということはできない。したがって、上記の減額計算を前提とする本件各更正の請求が国税通則法23条1項1号所定の要件を満たすものでないことは明らかである。
⑤ 以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこれと同旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。
更正の請求の期限が過ぎている過年分(7~8年前)の外注費漏れを当期の損金の額に算入する処理をしたが、認められないとされた事例-東京地裁平成27年9月25日判決(税資265号-142(順号12725))、東京高裁平成28年3月23日判決(税資266号-52(順号12830))、最高裁平成28年10月27日決定(税資266号-147(順号12925))
(1)事案の概要
本件は、一般小型貨物自動車運送事業を営む有限会社X(原告、控訴人、上告人)が、平成21年3月期の法人税について、B株式会社(以下「本件外注先」という。)に対する過年分(7~8年前)の外注費980万円余(以下「本件外注費」という。)を損金の額に算入して確定申告を行ったところ、所轄税務署長が、本件外注費は平成21年3月期の損金の額に算入することはできないとして、法人税更正処分等(以下「本件法人税更正処分等」という。)を行ったのに対し、本件外注費を損金に算入する処理は法人税法上違法なものではないと主張して、Xが本件法人税更正処分等の取消しを求めた事案である。
(2)本件の主な争点
本件外注費は、平成21年3月期の損金の額に算入されるか否かである。
(3)一審判決要旨(棄却)(控訴)
① 本件外注費は、外注先からトラック乗務員の派遣を受けたことに対する対価であるから、これは、Xの営む運送事業の収益を得るために直接要する費用であって、売上原価等の原価に該当するものと認められる。そして、証拠によれば、本件外注費は、平成12年11月から平成13年10月までの間に外注先がXに派遣した従業員に係る給与の合計額に基づいて算定されており、Xが本件外注費に係る役務の提供等を受けたのは、平成12年11月から平成13年10月までの間であると認められる。したがって、本件外注費は、平成21年3月期において、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額に該当するということはできない。
② 法人税法上、修正申告や更正の制度があり、後に修正すべきことが発覚した場合、過去の事業年度に遡って修正することが予定されているのであって、企業会計上固有の問題に基づき行われているにすぎない前期損益修正の処理を、それが企業会計上広く行われているという理由だけで採用することはできないというべきである。そうすると、単なる計上漏れのように、本来の事業年度で計上すべきであった損益を、後の事業年度において、前期損益修正として計上するような処理を公正処理基準に該当するものとして認めることはできないといわざるを得ない。
③ Xの請求はいずれも理由がないからこれを棄却する。
(4)控訴審判決要旨(棄却)(上告及び上告受理申立て)
① 当裁判所も、Xの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却するのが相当であると判断する。当審におけるXの主張に対する判断を付加するほかは、原判決を引用する。
② ある事業年度に損金として算入すべきであったのにそれを失念し、それを後の事業年度に発見したという単なる計上漏れのような場合において、企業会計上行われている前期損益修正の処理を法人税法上も是認し、後の事業年度で計上することを認めると、本来計上すべきであった事業年度で計上することができるほか、計上漏れを発見した事業年度においても計上することが可能となり、同一の費用や損失を複数の事業年度において計上することができることになって、こうした事態は、恣意の介在する余地が生じることとなり、事実に即して合理的に計算されているともいえず、公平な所得計算を行うべきであるという同法上の要請に反するものといわざるを得ず、また、同法上、修正申告や更正の制度があり、後に修正すべきことが発覚した場合、過去の事業年度に遡って修正することが予定されているから、過年度の計上漏れを修正するための前期損益修正を公正処理基準に該当すると認めることができない。
③ 原判決は、法人税法上は修正申告や更正の請求という救済の制度が用意されているから、救済制度を利用すれば過年度の前期損益修正によらなくとも納税者の権利は救済されると理解しているようであるが、Xのように更正の請求の期限が徒過した納税者の権利救済の機会を排除することになるとXは主張する。しかしながら、Xも、所定の期限までに更正の請求をすることによって本件外注費の計上漏れを修正することができたにもかかわらず、所定の期限までに更正の請求をしなかったというだけのことであって、Xには外注費計上漏れを修正する機会が確保されていたのであるから、Xの上記主張は採用することができない。
④ Xの請求はいずれも理由がないからこれを棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当である。よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却する。
(5)上告審判決要旨(棄却・不受理)(確定)
① 本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。