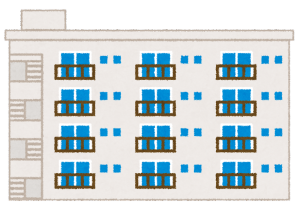
概要
社宅(賃貸物件)の会計処理は、会社が貸主に賃料を支払い、「地代家賃」等として経費処理します。そして、入居者である役員・従業員から「受取賃貸料(家賃)」として一定の賃料を受け取ります。
なお、社宅であるためには、会社が所有する住宅又は会社が家主と賃貸契約を締結した住宅であることが必要です。入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
会社が役員・従業員に対して社宅を貸与する場合は、役員・従業員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、 役員・従業員は給与(経済的利益)として課税されません。
なお、社宅制度を採用する場合は、社宅規定を整備する必要があります。
役員に社宅などを貸す場合の賃貸料相当額
役員に対して社宅を貸与する場合の賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、以下のように計算します。
ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない豪華社宅である場合は、別計算になります。
なお、下記の賃貸料相当額の算式では、「固定資産税の課税標準額」となっており、ここでいう課税標準とすべき金額は固定資産税であり都市計画税は含まれません。
「固定資産税の課税標準額」とは、地方税法の規定により、原則として「固定資産課税台帳に登録された価格」によるものとされています(国税庁HP質疑応答事例「社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額」)。
なお、専ら人の居住の用に供する家屋等の敷地の用に供されている住宅用地で一定のものについては、固定資産税の課税標準となるべき価格が3分の1又は6分の1の額となる特例があります(地法349の3の2)。
固定資産税評価額(特例適用前の金額)と特例適用後の金額は、いずれも地方税法の規定による「固定資産課税台帳に登録された価格」と解されていますが、どちらを使うべきなのか判断に迷います。
一般的には、社宅コストを計算するためのものである以上、住宅特例適用後の金額、すなわち現実に賦課された固定資産税に係る固定資産税課税標準額で計算できると考えられています。
一方、「価格」とは、あくまでも土地課税台帳登録証明書に記載されている「価格」と解すべきであるため、特例適用前の金額であるという考え方もあります(ネット情報では一番多い説)。
ただし、私のクライアントの複数名がそれぞれの所轄税務署に問い合わせた結果は、全て、住宅特例適用後の金額でよいとの回答となっています。
(2024/8/6)国税庁に照会結果
住宅特例適用「後」の金額が正しいとのこと。住宅特例適用後の金額が正しいので、多くのネット情報は間違いです。
社宅が分譲マンションの場合
分譲マンションのような区分所有の家屋については、区分所有者の専有部分と共用部分(廊下、階段・エレベーター室など)とに分けられます。
登記簿に記載されている床面積(登記床面積)は、各専有部分の床面積であり、共用部分の床面積は含まれていません。
これに対して、固定資産税の課税床面積は、共用部分の面積を各戸の専有床面積の割合であん分した床面積と専有床面積を合計した面積になりますので、登記簿上の床面積とは異なっています。いわゆる、現況床面積です。
社宅がこのような分譲マンションの場合、「固定資産税の課税標準額」は共用部分を含めて計算します(国税庁HP質疑応答事例「役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い」)。
よって、評価証明書に記載されている登記床面積ではなく、共用部分含む現況床面積で計算、判定します。
「固定資産税の課税標準額」の調べ方
大家(所有者)に聞いて、「固定資産税の課税標準額」を教えてもらうのが良いのですが、拒絶されることもあるでしょう。
その場合は、借地・借家人自ら、賃貸物件の所在地の市町村の役所の固定資産税課で「公課証明書」を取得して調べます(地方税法382の3)。
平成15年度からは、所有者だけでなく、借地・借家人についても公課証明書を請求できるようになりました。
なお、評価証明書は、「評価額のみ」の証明のためだけであるため、公課証明書を取得してください。公課証明書には、「評価額」に加えて、「課税標準額」「税相当額」が記載されています。
また、家屋と土地はそれぞれ別の証明書となります。
取得するために必要書類としては、①賃貸借契約書、②本人確認書類(運転免許書等)、③会社代表者印等ですが、取得する役所に行く前に、電話で事前確認して、必要なものを用意してください。
役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物(木造家屋)の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます(所基通36-41)。
賃貸料相当額=(A)その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2% + (B)12円×(その家屋の総床面積㎡/3.3 ㎡ ) + (C)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
他から借り受けた家屋を社宅として貸す場合には、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要となります。なお、実際に計算してみると、実際の賃料の10~20%程度となっていることが多いです。
役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります(所基通36-40)。
(1) 自社所有の社宅の場合
賃貸料相当額=【(A) その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(※) + (B)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6% 】×1/12
※ 木造家屋以外の家屋の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。この場合の「家主に支払う家賃」には、エレベーター保守料、火災報知機保守料、共用部分電気料、火災保険料等の管理費等を含めても問題ありません(国税庁HP質疑応答事例「役員に貸与したマンションの管理費」)。
役員に貸与する社宅が豪華社宅である場合
豪華社宅である場合には、一般の役員社宅と同様に評価することができず、第三者間で授受されるような賃貸料の時価、すなわち世間の家賃相場等をもって、賃貸料相当額とすることとなっています。
豪華社宅であるかどうかは、床面積が240 ㎡ を超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。
なお、床面積が240 ㎡ 以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人の嗜好等を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。
役員に貸与する社宅が豪華社宅である場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
(1) 自社所有の社宅の場合
その住宅の近隣の賃貸物件のうち類似する同規模同程度の住宅の賃貸料の額や、不動産鑑定士による賃貸料の査定額等を参考に算定
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が支払っている賃貸料の額
非常勤役員に貸与する社宅
非常勤役員に対し社宅を貸与することは一般的ではないため、上記の「役員に貸与する社宅が豪華社宅である場合」同様に、時価をもって賃貸料相当額とすべきでしょう。
役員の持ち家をその役員の社宅とする場合
既に持ち家があり、社宅入居の必要性がない役員について、その持ち家を会社において社宅として借り上げた上で、その役員本人に貸し付けるという取引は、社宅制度の趣旨から妥当性を欠くものであるため、同族会社等の行為又は計算の否認規定等が適用される可能性があると考えられます。
その場合、会社が役員に支払う賃借料は、役員の不動産所得となるのではなくて、その賃借料と役員から社宅の賃貸料として徴収した金額との差額は、その役員の給与として課税されると考えられます。
給与として課税される範囲
(1) 役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が、給与(経済的利益)として課税されます。
(2) 役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
(3) 現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。
継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは定期同額給与に該当するものとされています(法令69①二)ので、社宅の賃貸料の場合の給与(経済的利益)も、毎月規則的、継続的に発生するものであることから定期同額給与として取り扱われます。よって、原則として、損金に算入されますが、過大役員給与には注意をしてください。
従業員に社宅などを貸す場合の賃貸料相当額
従業員に対して社宅を貸与する場合の賃貸料相当額は、以下のように計算します(所基通36-45、36-41)。
賃貸料相当額=(A)その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2% + (B)12円×(その家屋の総床面積㎡/3.3 ㎡ ) + (C)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
他から借り受けた家屋を社宅として貸す場合には、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要となります。なお、実際に計算してみると、実際の賃料の10~20%程度となっていることが多いです。
給与として課税される範囲
(1) 従業員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が、給与として課税されます。
(2) 従業員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。しかし、従業員から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません(所基通36-47)。
(3) 現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。
(例) 実際の賃料が5万円で、賃貸料相当額が1万円の社宅を従業員に貸与した場合
(1) 従業員に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。
(2) 従業員から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。
(3) 従業員から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円との差額の4千円は給与として課税されません。
社宅が月の中途で役員・従業員の居住の用に供された場合
社宅が月の中途で役員・従業員の居住の用に供された場合は、その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員・従業員に対して貸与した社宅としての賃貸料相当額を計算します(所基通36-42(4))。
社宅についての固定資産税の課税標準額が改訂された場合
会社が役員に対して貸与した社宅についての固定資産税の課税標準額が改訂された場合には、原則として、その改訂後の課税標準額に係る固定資産税の第1期の納期限の属する月の翌月分から、その改訂後の課税標準額を基として賃貸料相当額の改算を要します(所基通36-42(2))。
一方、会社が従業員に対して貸与した社宅の固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その改訂後の課税標準額が現に賃貸料相当額の計算の基礎となっている課税標準額に比し20%以内の増減にとどまっているときには、あえて改算する必要はありません(所基通36-46)。
住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算
会社が住宅等を貸与した 全ての役員又は全ての従業員から、その貸与した住宅等の状況に応じてバランスのとれた賃貸料を徴収している場合において、その徴収している賃貸料の額の合計額が、 役員又は従業員それぞれについて上記により計算した賃貸料の額の合計額(従業員の場合は合計額の50%)以上であるときは、 全ての役員又は全ての従業員につき住宅等の貸与による経済的利益はないものとします(所基通36-44、36-48)。
社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
自社所有又はリースによる家具等を役員又は使用人に貸与する場合の経済的利益については、社宅の賃貸料相当額の計算とは原則として区分して評価することとなります。
家具等を貸与した場合の経済的利益の額は、自社所有の家具等については、定額法によって計算したその減価償却費相当額にその家具等の維持管理のために通常要する費用相当額を加算するなどの方法によって合理的に見積もった額とし、リースを受けた家具等については、リース料相当額となります(国税庁HP質疑応答事例「社員に家具等を貸与した場合の経済的利益」)。
社宅がある場合、そこでかかる水道光熱費を会社が払った場合
所得税基本通達36-26における寄宿舎とは、労働基準法等に規定する寄宿舎のようなものを予定しており、社宅などと異なり、一般的に多人数が起居及び食事をともにしている宿舎を想定してます。これらの水道光熱費の使用料については、一般家庭のように多額ではないことと、各人ごとの使用料が明らかでないことから、課税を要しない少額な経済的利益として取り扱われています。
ですから、通常の社宅の場合で、そこでかかる水道光熱費を会社が払った場合は給与課税の問題があると考えられます。
所得税基本通達36-26(課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等)
使用者が寄宿舎(これに類する施設を含む。以下この項において同じ。)の電気、ガス、水道等の料金を負担することにより、当該寄宿舎に居住する役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該料金の額がその寄宿舎に居住するために通常必要であると認められる範囲内のものであり、かつ、各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合に限り、課税しなくて差し支えない。
社宅への入居時及び退去時の引越し費用
役員や従業員の社宅への入居時及び退去時の引越し(転居)費用は、その役員等の個人的費用と認められるため、原則として、その役員等個人が負担すべきものとなります。よって、その個人的な費用である引越し費用を会社が負担した場合には、役員等に対する給与として課税されます。
ただし、上記のことはあくまでも原則論であり、役員等の個人的な都合ではなく、賃貸人たる会社における事情や必要性に基づき、どうしても引っ越しをせざるを得ない場合は、給与として課税されないと思います。
例えば、社宅として利用していた物件が、家主の都合(住宅の老朽化に伴う取壊しを理由とする立退き要請)等により立退きをしなくてはいけなくなった場合や、会社・事務所の遠方への移転等は、これに該当すると思います。もっとも、 引越し費用が合理的な金額である必要はありますが。
社宅に関する消費税
社宅に関する消費税は、以下の通りです(国税庁HP質疑応答事例「社宅に係る仕入税額控除」)。
- 受取家賃 役員や従業員から受け取る家賃は非課税売上
- 建物取得 家賃を徴収する社宅は、居住用賃貸建物に該当しますので、事業者が、国内において行う社宅の取得に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象となりません。
- 他の者から借り上げている社宅の借上料 仕入税額控除の対象となりません。
- 社宅の維持費 修繕費用、備品購入費用等は仕入税額控除の対象となります。管理人の給与、固定資産税など不課税となるもの及び非課税取引に該当するものは、仕入税額控除の対象になりません。


