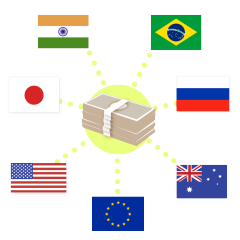
外貨預金の利子
国内銀行に外貨預金を行った場合は、円での預金と同様に、利子に20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)の源泉分離課税が行われ、申告は不要です。納税手続きを銀行が行い、そこで終了します。
ただし、国外銀行(外国銀行の海外支店の口座)で外貨預金を行って利子を得た場合は、源泉徴収は適用されず、利子所得として総合課税の対象となります。
為替差損益
円貨から外貨預金に預け入れた場合は、為替差損益を認識する必要がありません。ただし、将来、また円貨にする場合もあると思いますので、その預入時のレート(原則TTM、電信売買相場の仲値)による金額を控えておく必要があります。
例えば、1ドル100円の時に、100万円を1万ドルにした段階では、為替差損益を認識する必要がありません。その後、1ドル130円の時に、その1万ドルを130万円とした場合に、(130円-100円)×1万ドル=30万円の為替差益を認識する必要があります。
レートは、原則として、取引日においてのTTM(電信売買相場の仲値)で換算します(所基通57の3―2)。
このように、外貨預金を円貨として引き出した場合、為替差損益を所得として認識する必要があり、その所得は「雑所得」に含まれ総合課税の対象となります。
この為替差損益は、自分で、いくらなのか計算をする必要があります。なお、為替差損が出た場合には、他の雑所得と通算(相殺)できますが、他の所得とは損益通算できません。
円貨として引き出した時の為替レートが、預け入れ時よりも円安になっていれば為替差益となり、円高になっていれば為替差損が生じるということです。
また、外貨建預金を払出し外国株式に投資した場合も、為替差益を雑所得として認識する必要があります。よって、頻繁に外国株式を購入等する方は、外貨預金ではなく外貨MMFで保有をしておく方がよいということになりますが、新型コロナウイルス禍で世界的な金利低下に拍車がかかり、金融機関において外貨MMFの運用が難しくなっている状況です。そのため、利用しようと思っても利用できない方はいるでしょう。
雑所得となる問題点
為替差損益が雑所得(総合課税)となる場合、国内FXの雑所得(分離課税)と違って、税務上、非常に厳しい取り扱いとなっています。
プラスがでれば総合課税により、他の所得(給与所得、事業所得、不動産所得等)と合算されて税金がかかりますが、総合課税の税率は累進税率の為、プラスがでればでるほど、税負担率が重くなります。
一方、マイナスとなった場合は、他の雑所得のプラスとは相殺できますが、他の所得(給与所得、事業所得、不動産所得等)とは相殺(損益通算)できません。また、そのマイナスを翌年に繰り越すようなこともできません。
外貨取引自体による為替差損益が事業所得に該当することが難しい理由
一般の個人の方の外貨取引自体による為替差損益は、原則として、雑所得となりますが、個人事業主が決済するため等事業の遂行上保有している外貨建預金を円貨に交換することによって生じた為替差損益は事業所得の計算上総収入金額または必要経費に算入します(下記の方で説明しています)。
なお、外貨取引自体による為替差損益も、事業とよべる規模で行っていれば、事業所得となる可能性はありますが、暗号資産の取引が事業所得と認められることが難しいのと同様に、外貨取引自体による為替差損益を事業所得とするのは、相当、ハードルが高いといえます。為替ディーラーのように専属でその業務をし、大量に取引を行い、生活ができるぐらいの利益を継続的に出し続けていないと認められることは難しいでしょう。
令和2年3月10日裁決(東裁(所)令元第84号)において、以下のように判断しています。
「請求人は、資金調達手段や情報収集のための特別な機構を有することなく、また特別の人的・物的設備を整えることもなく本件外貨取引を行っていたといえる。また、請求人は、個人事業主として、その後会社を設立して給与により、多額の所得を得ているのに対し、外貨預金口座からの払出しの回数は少なく、本件外貨取引による利益も得ていないことからすれば、請求人は、客観的にみれば、本件事業又は本件会社を営み、これらによる安定した収入を得て生活費を賄いつつ、その傍らで、本件外貨取引を行っていたものというほかない。これに加え、本件外貨取引は、その実態を踏まえると、相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性も乏しいものといえるから、本件外貨取引は、社会通念に照らして、対価を得て継続的に行う事業に該当するということはできない。したがって本件為替差損に係る所得は、事業所得に該当せず、雑所得に該当する。」
為替差損益が譲渡所得に該当しない理由
令和2年3月10日裁決(東裁(所)令元第84号)において、以下のように判断しています。
「平成28年分及び平成29年分の本件為替差損に係る所得は、事業所得に該当せず、また、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないから、いずれも雑所得に該当する。」
「譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいい(所得税法33条1項)、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものであるところ(最高裁昭和47年12月26日第三小法廷判決・民集26巻10号2083頁、最高裁昭和50年5月27日第三小法廷判決・民集29巻5号641頁参照)、為替差損益は、外貨と円貨との相対的な換算レートが変動することによって生じるものであって、外貨そのものの価値が値上がり又は値下がりして生じるものではないから、平成28年分及び平成29年分の本件為替差損に係る所得はいずれも譲渡所得に該当しない。」
総平均法に準ずる方法
預入れが随時可能な外貨預金の為替差損益の算定方法は「総平均法に準ずる方法」により算定します。具体的な計算方法については、「外貨預金の払出しに伴って生じる為替差損益の具体的な算定方法(総平均法に準ずる方法)」のページまで。
外貨預金の円換算額(取得価額)が不明の場合
概算取得費とは、いわゆる5%規定であり、売却価額の5%を取得費とすることができる規定で譲渡所得の場合、利用できます。土地建物等の取得費(措法31の4、措通31の4-1)、土地建物等以外の資産の取得費(所基通38-16)、株式等の取得価額(措通37の10・37の11共-13)、有価証券の取得価額(48-8)となっています。
為替差損益と同じ雑所得に該当する暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められています(所基通48の2-4)が、為替差損益は概算取得費の適用はありません。
ですから、外貨預金の円換算額(取得価額)が不明の場合、理論値で納税者にとって一番不利なレートを利用して申告すれば、税務署も否認はしてこないと考えられています。
例えば、いつからいつまでに取得したという事がわかれば、その間の納税者にとって一番不利なレートで取得したとすればよいでしょう。
なお、いつ取得したかもわからない場合は、過去の納税者にとって一番不利なレートで取得したとすればよいでしょう。例えば、円とドルの関係でいえば、過去最大の円高としては2011年10月31日の1ドル=75円32銭となります。
国外在住の時から所有していた外貨預金から円貨にする
今で説明した通り、円貨から外貨にし、その外貨を円貨にした場合、そのタイミングで為替差損益を認識する必要があるということでした。
では、国外において勤務していて外貨により支給された給与を預金していたような場合ですが、帰国後、その外貨を円貨にした場合、為替差損益を認識する必要があるかどうかです。
これについて、課税庁は公にはっきりと明言はしていませんが、為替差損益は認識し得ないとして取り扱っていると思われます。
下記の国税庁HPの所得税質疑応答事例の「為替差損益の取扱い」の取扱いを見てもらうとわかるのですが、全て、円からドル(外貨)への交換からストーリーが始まっています。外貨スタートはひとつもないです。
また、「保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い」の回答要旨の中で「為替差損益は、一般的には異なる通貨の交換(往復)により発生するもの」と記載されていますが、外貨から円貨にするという取引では往復はしてないということになります。
そもそも、国外において数十年勤務していて外貨により支給された給与を預金し、その口座から生活費等引き出しいて、利息も入ったりということをしている口座にある外貨預金の正しいレート計算なんかできるわけないですが。
〇外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
〇預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/40.htm
〇預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/43.htm
〇保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/41.htm
年度末換算
法人ならば事業年度末の時点で、事業年度末にある外貨を年度末のレートにて円換算し直し、為替差損益を計上します。しかし、個人では年度末での円換算行いません。所得税法は法人税法と異なり、外貨建資産負債に関する期末時換算の定めがないためです。
個人事業主の場合
為替差損益
個人事業主の場合も、原則として、上記までの考え方がベースとなりますが、若干、考え方が違う部分があります。
原則として、取引日においてTTM(電信売買相場の仲値)で換算しますが、継続適用を条件に、収益・資産はTTB(電信買相場)、費用はTTS(電信売相場)を適用することも認められています(所基通57の3―2)。
また、取引ごとに換算をするのが原則ですが、多通貨での取引がある場合は、換算方法の原則を貫こうとすると所得計算が煩雑になります。
そのため、外貨建取引を取引発生時には外国通貨で記録し、各月末等一定の時点において日本円に換算するといういわゆる多通貨会計を採用している場合において、外貨建取引の換算に当たり、各月末等の一定時点で一括して日本円に換算することができます(所基通57の3―3)。
この方法では、各月末等において、1月以内の一定期間ごとの一定時点での為替相場か、一定期間の平均値をもって円換算します。つまり、取引ごとではなく、一定時点を外貨建取引の発生時として処理してよいということになります。
所得区分
事業上生じた為替差損益は、事業所得となります。例えば、事業の遂行上保有している外貨建預金を円貨に交換することによって生じた為替差損益は事業所得の計算上総収入金額または必要経費に算入します。
年度末換算
個人事業主の場合も、一般の個人と同じで、年度末での円換算行いません。よって、為替差損益は生じないことになります。
サラリーマンと年金受給者のいわゆる20 万円以下規定
以下に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
① 給与所得者(給与年収 2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合
② 年金受給者(公的年金等の収入金額が 400万円以下の者に限る)で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合
よって、上記に該当するサラリーマンの方で為替差益による雑所得を含めて給与所得以外の所得が20万円以下であれば、所得税の申告が不要となるため、為替差益に対する所得税がかからないということになります。ただし、住民税の申告納税は必要です。
また、上記に該当する年金受給者の方も同様です。なお、公的年金は雑所得であるため、為替差損(雑所得のマイナス)が出た場合は、公的年金による雑所得のプラスと為替差損による雑所得のマイナスは相殺することができます。
年金受給者で税金を払っていて、かつ、為替差損が生じた場合は、相殺するために確定申告をするとよいでしょう。
支払調書
外貨預金の利子及び為替差益については、支払調書が提出されません。ここが、為替差益が生じている人で申告が必要な人でも、申告していない最大の理由であると思います。



