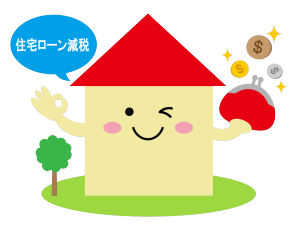概要
地主個人が法人に対して建物所有を目的とする土地の賃貸を行った場合や、地主個人所有の土地建物のうち、建物のみを法人に譲渡した場合は、借地権の設定があったとみなされます。
地主個人と法人が全く関係ない他人同士であるならば、地主個人は法人に借地権相当額の権利金を要求するでしょう(その地域に権利金を収受する取引慣行がある場合)。
しかし、法人が地主個人が役員となっている同族会社の場合、地主個人は法人に借地権相当額の権利金を要求しないことがよくあります。
この場合、借地権に相当する利益供与があったものとして認定課税が行われます。
ただし、無償返還届出書(地主個人と同族会社との間で契約を締結)を所轄の税務署に提出している場合には、権利金の収受が行われなくとも、権利金の認定課税はありません。
相続時
無償返還届出書を提出していて、地主個人が亡くなった場合には、賃貸借、使用貸借で、以下のように相続税の評価額の取扱いが変わってきます。
賃貸借
地主個人 自用地評価額×80%
同族会社 (同族会社の株式評価)自用地評価額×20%
使用貸借
地主個人 自用地評価額×100%
同族会社 (同族会社の株式評価)評価しない
相当地代通達8(「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の貸宅地の評価)
借地権が設定されている土地について、無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価する。
なお、被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸し付けている場合には、43年直資3-22通達の適用があることに留意する。この場合において、同通達中「相当の地代を収受している」とあるのは「「土地の無償返還に関する届出書」の提出されている」と読み替えるものとする。
(注) 使用貸借に係る土地について無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額によって評価するのであるから留意する。
土地売却時
土地売却時に無償返還届出書が提出されている場合は、地主個人の譲渡所得の総収入金額は借地権価額相当額を控除することはできないという事例(大阪地裁令和7年1月17日判決・令和4年(行ウ)第181号)があります。
土地売却時に無償返還届出書が提出されている場合は、地主個人の譲渡所得の総収入金額は底地部分に相当する金額に加えて借地権部分に相当する金額を含んだ金額とすべきとされた事例-大阪地裁令和7年1月17日判決(令和4年(行ウ)第181号)(棄却)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 原告Xは、所有している各土地(以下「本件各土地」という。)をA社(Xが代表者)に建物所有目的で賃貸し、A社は本件各土地上に建物(以下「本件建物」といい、「本件各土地」と併せて「本件不動産」という。)を所有していた。具体的には、以下のとおりである。
X及びA社は、平成27年4月1日、本件各土地に関し、Xを賃貸人、A社を賃借人とする賃貸借契約(以下、「本件賃貸借契約」といい、本件賃貸借契約におけるA社の本件各土地の賃借権を「本件借地権」という。)を締結した。本件賃貸借契約の契約書には次の定めがある。
(ア) A社は、建物を所有する目的で本件各土地を使用し、他の目的、用途に使用しない。
(イ) 本契約の賃貸借期間は、平成27年4月1日から平成57年3月31日までの満30年とする。
(ウ) 賃料は月額400万円とする。
(エ) 本契約においては権利金その他名目のいかんを問わず、権利設定の対価の授受は行わない。
(オ)a 本契約が終了したときは、A社は、何らの対価なくして直ちに本件各土地を現状に復した上で返還する。
b A社はXに対し、契約終了原因に関わらず、本件各土地の返還に際し名目のいかんを問わず何らの金品も請求しない。
② X及びA社は、平成27年4月1日、所轄税務署長Hに対し、本件各土地の賃貸借について、Xが本件賃貸借契約により本件各土地を平成27年4月1日からA社に使用させることとしたが、当該契約に基づき将来借地人から無償で土地の返還を受けることになっていること、本件各土地の所有又は使用に関する権利等に変動が生じた場合には速やかにその旨を届け出る旨記載した無償返還届出書(以下「本件無償返還届出書」という。)を提出した。
A社は、本件賃貸借契約締結後、その貸借対照表において本件借地権を計上しておらず、平成28年度3月期の貸借対照表においても本件借地権を計上していなかった。
③ 平成28年5月26日、X及びA社は、B社に対し本件不動産を売却した。
④ Xは、譲渡所得につき、A社との合意に基づき土地代金の80%を収入金額として申告したところ、Hから、分離短期譲渡所得の金額に誤りがあるなどとして、更正処分等を受けた。
(2)本件の主な争点
本件は、Xの譲渡所得の総収入金額に本件各土地に係る借地権価額相当額を算入すべきか否かである。
(3)判決要旨(棄却)
① 地主が個人で借地人が法人である場合であっても、地主(個人)が借地人(法人)との連名で無償返還届出書を提出することは可能であるから、借地権の設定にあたり、権利金等が授受されておらず、地代の額が相当の地代に満たない場合であっても、無償返還合意がされ、無償返還届出書が提出されている場合、借地人である法人については、法人税基本通達13-1-7が適用され、相当の地代の額と実際に収受している地代との差額を借地人等に対して贈与したものとして取り扱われ、権利金の認定課税は行われない。
② 法人税基本通達13-1-7の趣旨からすれば、無償返還届出書が提出されている場合に、権利金の認定課税が行われないのは、借地契約当事者間においては、地主に当該土地の自用地としての価額がそのまま残されていて、借地権部分に相当する経済的価値が借地人に移転していない経済実態があるからであると解される。そうすると、無償返還届出書の提出とは、課税関係において、借地権部分に相当する経済的価値が借地人に移転していないという経済実態があることを、地主自らが、所轄の税務署長に対して明らかにする趣旨の届出であるものと解するのが相当である。
③ 無償返還届出書を提出することによって、地主(個人)は、法人税基本通達13-1-7の適用を受けることはないものの、借地人(法人)は、法人税基本通達13-1-7が適用され、借地権部分に相当する経済的価値が借地人(法人)に移転していないという経済実態を前提にした課税上の取扱いを受けることになる。そして、無償返還届出書の提出とは、借地権部分に相当する経済的価値が借地人に移転していないという経済実態があることを、地主自らが、所轄の税務署長に対して明らかにする趣旨のものであり、無償返還届出書の提出がされた場合の借地権に係る課税関係については、法人税のみならず、相続税や贈与税等に係る課税関係においても上記経済実態を前提にした取扱いがされるべきものである。
④ したがって、地主が個人で借地人が法人である場合で、無償返還届出書が提出されているときには、地主(個人)の譲渡所得に係る課税関係においても、地主が自ら届け出た上記の経済実態〔借地権部分に相当する経済的価値が借地人に移転していない結果として、当該土地賃貸借契約の相手方である地主(個人)の下に借地権部分に相当する経済的価値が残っているという経済実態〕を前提にした取扱いがされるべきものと解するのが相当である。
⑤ Xは、平成27年4月1日、A社との間で、本件賃貸借契約において、本件各土地の無償返還の合意をし、Hに対し、無償返還届出書を提出したこと、その後もA社の貸借対照表には借地権が資産として計上されておらず、本件売買契約締結時(平成28年5月26日)までの間に、本件無償返還届出書に係る土地の使用に関する権利等に変動が生じた旨の届出はされていなかったことが認められる。
そして、Xは、本件無償返還届出書の提出により、課税関係において、借地権部分に相当する経済的価値がX(地主)からA社(借地人)に移転していない結果として、本件賃貸借契約の相手方であるX(地主)の下に借地権部分に相当する経済的価値が残っているという経済実態があることを、自ら税務当局に対して明らかにしたものと認められ、また、本件借地権の設定から本件売買契約締結に至るまでの間において、XからA社に本件借地権の経済的価値の移転があったとみるべき事情(経済実態)があるとは認められない。
そうすると、本件売買契約締結時において、本件各土地の借地権部分に相当する経済的価値はXに帰属していたものと認められる。
⑥ さらに、本件売買契約書には、売買代金の内訳が記載されており、売主(X及びA社)と買主(B社)との間においては、Xの所有に係る本件各土地を合計54億2180万円余で売却し、A社の所有に係る本件建物を7820万円で売却する旨の意思表示の合致があったものと認められる。そして、本件各土地の売買代金である54億2180万円余という金額は、本件売買契約締結時に、借地権部分に相当する経済的価値がXに帰属していたという経済実態を前提に決定されたものであって、本件各土地の底地部分に相当する金額に加えて、借地権部分に相当する金額を含むものと認められる。
⑦ 以上によれば、本件売買契約の売買代金(対価)のうちのXの所有する本件各土地という資産の増加益が具体化された金額とは、本件各土地の底地部分に相当する経済的価値に加えて、借地権部分に相当する経済的価値の移転による増加益が具体化された金額であるというべきであるから、本件各土地の底地部分に相当する金額に加えて、借地権部分に相当する金額を含むものと解するのが相当である。
法人税基本通達13-1-7(権利金の認定見合せ)
法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合(権利金を収受した場合又は特別の経済的な利益を受けた場合を除く。)において、これにより収受する地代の額が13-1-2《使用の対価としての相当の地代》に定める相当の地代の額に満たないとき(13-1-5《通常権利金を授受しない土地の使用》の取扱いの適用があるときを除く。)であっても、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、その旨を借地人等との連名の書面により遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。以下13-1-14までにおいて同じ。)に届け出たときは、13-1-3《相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定》にかかわらず、当該借地権の設定等をした日の属する事業年度以後の各事業年度において、13-1-2に準じて計算した相当の地代の額から実際に収受している地代の額を控除した金額に相当する金額を借地人等に対して贈与したものとして取り扱うものとする。
使用貸借契約により他人に土地を使用させた場合(13-1-5の取扱いの適用がある場合を除く。)についても、同様とする。
(注) 本文の取扱いを適用する場合における相当の地代の額は、おおむね3年以下の期間ごとにその見直しを行うものとする。この場合において、13-1-2の(注)1中「その借地権の設定等の時」とあるのは「当該事業年度開始の時」と読み替えるものとする。