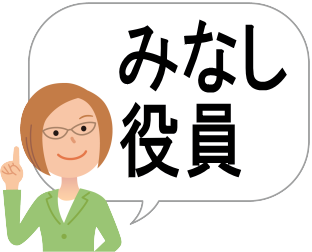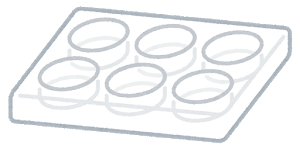
概要
従業員などから源泉徴収した所得税等は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国(税務署)に納付しなければなりません(所法181ほか)。とはいっても、毎月給与から所得税等を源泉徴収して税務署に納めるのは非常に手間のかかることです。
ですから、給与の支払いを受ける役員・従業員(給与の支給人員)が常時10人未満の小さな会社については、本来であれば毎月しなければならない納税を年2回にまとめてできるという特例があります(所法216)。
「常時10人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期などにおいて臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです(所基通216-1(1))。
そのような場合に、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、1月から6月までに源泉徴収した所得税等は7月10日までに、7月から12月までの分は翌年の1月20日までに納付すればよい、ということになります。提出先は、給与支払事務所などの所在地の所轄税務署となります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出時期はとくに定められていませんが、申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます(所基通216-2)。
例えば、2月中に承認申請書を提出し税務署長から承認又は却下の通知がない場合は、2月支給分の給与の源泉所得税の納期限は3月10日までとなります。そして、3月~6月支給分の給与の源泉所得税の納期限は7月10日までとなります。
ただし、2月中に承認申請書を提出し、法定納期限である3月10日までに承認通知書が到達した場合は、2月中に支払った給与等に係る源泉徴収税額からこの特例の適用を受けることができます。
なお、顧問税理士(個人)がいる場合は、その税理士報酬の源泉所得税についても、給与の源泉所得税と一緒に納付をすることになります。
| 給与の所得税等を源泉徴収 | 納付期限(原則) | 納付期限(特例) |
|---|---|---|
| 1月に1万5000円を徴収 | 2月10日までに1万5000円を納付 | 7月10日までに1万5000円×6か月分を納付 |
| 2月に1万5000円を徴収 | 3月10日までに1万5000円を納付 | |
| 3月に1万5000円を徴収 | 4月10日までに1万5000円を納付 | |
| 4月に1万5000円を徴収 | 5月10日までに1万5000円を納付 | |
| 5月に1万5000円を徴収 | 6月10日までに1万5000円を納付 | |
| 6月に1万5000円を徴収 | 7月10日までに1万5000円を納付 |
常時10人未満であるかどうかの判定
常時10人未満であるかどうかの判定は、実務的には、下記の所得税基本通達216-1により判断します。なお、注意点としては、平常の状態で雇用されているならば、正社員に限らずアルバイトやパートであっても対象となります。
所得税基本通達216-1(常時10人未満であるかどうかの判定)
法第216条かっこ内に規定する「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定するものとし、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。
(2) 建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。
新設法人は注意
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、会社を設立したら、すぐに提出するのが一般的となっています。ただし、会社を設立して、すぐに給与を支払う場合は注意をしてください。
例えば、9月に会社を設立して、すぐに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しても、9月に給与を支払う場合は、その分の源泉所得税の納期限は10月10日までとなります(上記記載のように、法定納期限である10月10日までに承認通知書が到達した場合は別)。
この場合、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)」という源泉所得税の納付書で納めることになりますが、会社設立して間もない場合は、所轄税務署も納付書を会社に送ってないでしょうから、所轄税務署に取りに行ってください。その際に、書き損じた場合等にそなえて3枚ぐらい貰っておくと良いでしょう。
また、その後の納期の特例による源泉所得税の納付にそなえて「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例用)」も3枚ぐらい貰っておいた方が良いでしょう。
なお、切手を貼った返信用封筒と「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)3枚と(納期の特例用)3枚を、それぞれ欲しいので郵送してください」と書いたメモ書きを同封して、所轄税務署に郵送すれば、送り返してもらえます。
ただし、源泉所得税の納期限の間際ですと、所轄税務署から送り返してもらえるのが納期限を過ぎてしまう場合がありますので、その場合は、所轄の税務署に取りに行って、その場で納税するのが良いでしょう。
| 給与の所得税等を源泉徴収 | 納付期限 |
|---|---|
| 9月に1万5000円を徴収 | 10月10日までに1万5000円を納付 |
| 10月に1万5000円を徴収 | 翌年1月20日までに1万5000円×3か月分を納付 |
| 11月に1万5000円を徴収 | |
| 12月に1万5000円を徴収 |
納付期限が休日の場合
源泉所得税の納付期限が日曜、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります(通法10②、通令2②)。
納付期限までに納付がない場合
納付期限までに納付がない場合には、源泉徴収義務者は延滞税や不納付加算税を負担する必要があります(通法60、67、68)。
中小企業の場合、経理担当者を雇用することが難しいことが多いですが、そのことが、法定納期限までに納付できなかった理由になることはありません。令和2年10月13日裁決(大裁(諸)令2第17号)では、そのことにつき、以下のように判断しています。
「経理担当者の不在状態の継続等により事務処理が間に合わなかったなどという事情は、請求人(編注、納税者)の組織内部の事情にすぎないのであって、源泉徴収義務者である請求人としては、経理担当者の有無にかかわらず、その責任において本件源泉所得税等を法定納期限内に納付できるように、あらかじめ準備するなど必要な措置を講じておくべきであったというほかない。」
源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)が0円の場合
納付する税額がない場合でも、0円と記載した源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)を所轄税務署に提出します。納付税額が0円の場合には、金融機関の窓口に提出をすることはできないので、所轄税務署に提出します。
提出する理由は、税額が0円であることを示すためです。提出していないと、通常、お尋ねのハガキが送られてきます。
なお、年末調整等で過納額の充当又は還付をした結果、納付すべき税額がなくなった場合でも、給与等の支給がある場合には、その事績を納付書(所得税徴収高計算書)に記入して税務署に提出することとされています(所規別表第三(三)備考17)。
令和6年において行われた定額減税によって納付すべき税額がなくなった場合も、給与等の支給がある場合には、その事績を納付書(所得税徴収高計算書)に記入して税務署に提出することとされています。
所轄税務署の窓口に直接持参すればいいのですが、忙しいなどの理由で郵送する場合は、郵送先が所轄税務署ではなく業務センターになる場合があります。
現在、課税庁は、源泉所得税等の管理を業務センターで一括処理する動きとなっています。
特例の対象となるもの
源泉所得税の納期の特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。
よって、それら以外のもの(例えば、デザイン等の外注費)については、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出していても、納期の特例の対象とはならないため、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
納税の仕方
一般的には、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」という納付書を税務署からもらってきて、それに納税金額等を書き込んで金融機関や税務署で納税します。
納期の特例により、給与や税理士顧問料だけで年2回の納税で済むなら、それでよいかと思いますが、源泉徴収が必要な外注先があり、毎月、納税をするとなると、結構、面倒かと思います。
その場合は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用した源泉所得税の納付がお勧めです。インターネットにアクセスできるパソコンをお持ちの方は、e‐Taxを利用した電子納税ができ、わざわざ金融機関や税務署まで行く必要がありません。
〇国税庁HP(e‐Taxを利用して源泉所得税が納付できます!)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r04/pdf/14.pdf
給与の支給人員が常時10人以上になった場合
給与の支給人員が常時10人以上になった場合は、納期の特例の要件に該当しなくなるため、遅滞なく、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出してください。
そして、この届出書を提出した場合には、その提出をした日の属する納期の特例の期間内に源泉徴収した税額のうちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月10日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、毎月翌月10日までに納付することになります。
平成24年6月30日までの制度
平成24年6月30日までは、「納期の特例」の承認を受けるだけでは、徴収した源泉所得税を年2回(7月10日、翌年1月10日)にまとめて納付することができただけでした。
つまり、7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税については、翌年1月10日までに納税の必要がありました。
そのうえで、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税については、届出書を提出し一定の要件を満たすことで納期限を翌年1月10日ではなく翌年1月20日とできる「納期限の特例」の制度が設けられていました。
つまり、「納期の特例」だけでは、7月から12月までの間に徴収した源泉所得税の納期限は翌年1月10日であり、翌年1月20日の納期限とするためには、別途、「納期限の特例」の届出書を提出する必要がありました。
明らかに無駄な手続きのため、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等から、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限は翌年1月20日とされ、「納期限の特例」の届出制度は廃止とされました。
「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、改正が行われておりませんので、その源泉徴収義務者が 12月に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限は従前どおり翌年1月10日です。