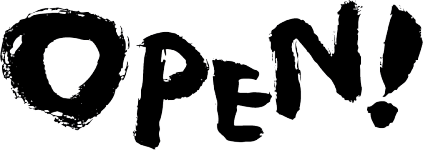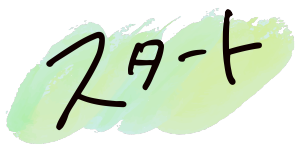概要
中小企業の場合、代表者の配偶者や子供を役員、従業員にすることが多いです。人を採用するといっても、中小企業ですと難しい場合が多く、会社運営にとって、配偶者や子供は貴重な戦力といえます。
会社運営上、配偶者や子供を、役員にするのか、従業員にするのか迷う場合もあるでしょう。
役員給与なのか従業員給与なのかで税務上の違いはありますが、そこを考慮して選択をするのではなく、経営に関与するか否以下で役員とするかどうかを選択すべきだと思います。
代表者の配偶者や子供に給与を支払う場合の注意点
1つ目の注意点
1つ目の注意点は、役員給与(役員報酬)にしろ、従業員給与にしろ高すぎると問題となります。
まず、役員給与のうち「不相当に高額な部分」の金額は損金の額に算入されないことになっています(法法34②、法令70)。多額の給与を支払い、法人税の負担軽減を図ることを防止するためです。
例えば、売上5000万円、役員給与4000万円、その他経費1000万円の場合、会社の利益(所得)が0円(5000万円-4000万円-1000万円)だったとします。この場合、法人税は0円となります。
ただし、役員給与4000万円の適正金額が2500万円であり、過大金額が1500万円だったということになると、この1500万円の部分に法人税がかかってしまいます。
問題は、役員給与が何と比べて高いと問題となるのかですが、同業類似法人の役員給与支給状況と比べてです。ただし、同業類似法人のデータを課税庁側は持っていますが、会社側は調べることはできません。ですから、その意味で会社側は不利といえます。
また、役員給与と同様に従業員給与の場合であっても、会社代表者がその配偶者や子供に多額の給与を支払い、法人税の負担軽減を図ることができるという問題もあり、役員の親族等に対して支給する過大な従業員給与(不相当に高額な部分の金額)についても、損金の額に算入しない措置が講じられています(法法36)。
役員給与と違い、従業員給与の場合は、経営に関与せず経営責任もないため、純粋に実労働をしていることが求められます。また、世間相場の単価と乖離するのはおかしいということになります。
2つ目の注意点
2つ目の注意点は、配偶者や子供に給与を支払う場合は、実際に働いてもらう必要があります。当たり前だと思われる方も多いと思いますが、働いていない配偶者や子供に給与を払っている会社も世の中にはあります(税務裁判例等によれば)。
給与所得控除、基礎控除等の所得控除や所得税の累進課税制度の仕組みからいって、同じ給与の金額を払うにしても、複数でもらった方が所得税の金額が小さくなります。
例えば、2000万円の給与を支払う場合、1人で2000万円もらうより、2人で1000万円ずつもらった方が所得税の金額は小さくなります。つまり、1人の所得税より、2人の所得税の合計額の方が小さくなります。
同様に、2人で1000万円ずつもらうより、4人で500万円ずつもらった方が所得税の金額は小さくなります。所得税の計算の仕組みから、そういうことがおこるのです。
この仕組みを悪用して、実際には働いていないんだけど、働いているという形にして配偶者や子供に給与を支払い、会社代表者である自分の給与を下げている人がいます(税務裁判例等によれば)。
このようなことは、節税ではなく脱税です。税務調査で指摘された場合、悪質ということで重加算税という重たいペナルティーの税金がかけられることになるでしょう。
3つ目の注意点
3つ目の注意点は、「みなし役員」です。
みなし役員の説明前に、役員給与と従業員給与の大きな違いを説明したいと思います。役員にボーナスを支払う場合は、支給時期、支給額を記載した書類をあらかじめ税務署に届け出(事前確定届出給与に関する届出)をしないと損金とできません。
例えば、今期は利益が結構でたので、臨時の決算賞与を従業員に支払う場合があると思います。役員に支払っても届出をしていないと損金とできないため、法人税の削減とはなりません。
このように、臨時のボーナスを払うことを考慮して、あえて、配偶者等を役員にしないで従業員という立場にされている会社代表者はいます。
ただし、税務の世界には「みなし役員」といって、一定の場合、登記上の役員ではなくても役員とみなされてしまいます。
従業員と思ってボーナスを払っても、みなし役員ということになると、このボーナスは、役員に対する臨時のボーナスということで損金とならないということになります。
では、どういう場合に「みなし役員」に該当するかというと、小さい会社の場合、その者が「経営に従事」しているか否かがポイントとなります(詳しくは、実質的に法人の経営に従事して、意思決定に大きな影響力を持つ「みなし役員」とは?)。
冒頭で書いた通り、配偶者等を役員とするのか従業員とするのかは、経営に関与するか否以下で選択すべきだということです。
配偶者を非常勤役員とする場合
現在のトレンドに、代表者の役員報酬を増やしたくないために配偶者を役員として役員給与を支払うケースが増えています。また、その配偶者を社会保険の被保険者にさせたくないために、配偶者を非常勤役員とするケースが増えています。
ただし、非常勤役員だからといって、社会保険の被保険者にならないとは言い切れません(報酬0円なら、被保険者になりませんが)。(非常勤)役員が社会保険の被保険者となるか否かの判断は難しいのですが、日本年金機構から示されている判断材料は以下のとおりとなっています。
| 1 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか 2 当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか 3 当該法人の役員会等に出席しているかどうか 4 当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか 5 当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか 6 当該法人等より支払いを受ける報酬が、社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか なお、上記項目は、あくまでも例として示すものであり、それぞれの事案ごとに実態を踏まえ判断されたい。 |
上記6項目を総合勘案をして判断をすることになるのですが、あくまでも6項目は例示でしかありません。ですから、判断に悩む場合は、管轄の年金事務所に相談・確認しておいたほうがいいでしょう。結構、年金事務所によって、判断が違っています。
なお、合同会社の場合、業務執行社員は業務執行をする権利があるので、役員給与をもらっている以上は、社会保険の被保険者になるという考え方があります(同じ役員といっても、株式会社の取締役とは違うという考え方)。
ですから、合同会社の設立を考えていて、かつ、非常勤業務執行社員の採用を検討の方は、事前に、管轄の年金事務所に相談・確認をしてください。
また、税務上、非常勤役員については、名目的存在であり職務の執行が十分になされていない場合が多くあるため、職務の内容に照らして支給された役員給与が過大であると判定されることがあるので注意をしてください。
簡単にいうと、税務調査が入った際に否認される可能性が高いということです。例えば、月20万円払っていたが、月6万円が適正金額とされるというようなことが起こりえるということです。
なお、職務の執行を全くしていないことが確認されてしまうと0円が適正金額となってしまうので、非常勤とはいえ、何らかの職務の執行はしている必要があるということです。
過大役員給与となるかどうかについては、税務署に相談に行っても答えてもらえないでしょう。自分で判断するしかありません。
過大役員給与であると税務署が判断をするためには、同業類似法人のデータが必要となりますが、自分の管轄のデータだけというわけではなく、他の数カ所の税務署のデータも取り寄せて、取捨選択をする必要があります。
いちいち、事前相談の段階で、そんなことまでするほど、税務署は暇ではありません。
代表者の妻である取締役の役員報酬額について、類似法人の非常勤役員の報酬額との比較をした上で、不相当に高額な部分があり、その部分は損金算入できないとした東京地裁平成22年9月10日判決(税資260-151(順号11507))
(1)事案の概要
本件は、同族会社である原告Xが、平成16年5月期、平成17年5月期及び平成18年5月期(以下「本件各事業年度」という。)のXの法人税につき、X代表者甲の妻である取締役乙の役員報酬をそれぞれ800万円、2400万円及び2400万円とし、これらの全額を損金の額に算入して所得の金額を計算して確定申告をしたところ、所轄税務署長が、上記各報酬の額には法人税法34条1項(当時)に定める「不相当に高額な部分の金額」があるから上記各報酬の額のうち当該部分の金額を損金の額に算入することはできないなどとして、更正処分等をしたことに対し、Xが、上記各報酬の額はいずれも相当なものであるから処分は違法であると主張して、これらの処分の取消しを求める事案である。
(2)争点
本件の争点は、本件各報酬額に法人税法に定める「不相当に高額な部分の金額」があるか否か、すなわち、本件各報酬額の相当性である。
(3)判示要旨
① 乙は、Xにおける経営方針の決定、しょうちゅうの製造販売に関する業務、資金繰りに関する業務、経理業務等に直接従事することはなく、取引先等の接待業務等に従事したことはあるものの、その日数は極めて少なく、さらに、Xへの出勤日数も1か月に1、2回程度であることから、乙は、日常的にXの役員として業務執行に従事していたのではなく、いわゆる非常勤の役員としていくつかの職務に従事していたものと認めるのが相当であり、乙の役員としての職務の内容として固有のものがあったとは認められないというべきである。
② 本件類似法人調査に当たって、K国税局長が抽出する法人をXとの類似性を有する法人に限定するための条件として付したものは、Xとの報酬額の比較のための資料として用いることができるだけの類似性を有する法人を抽出するためのものとして合理的であり、法人税法施行令69条1号に規定する「その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するもの」を選定するための条件として相当なものと認められる。そして、乙の職務の内容に照らせば、抽出対象役員を非常勤の役員としたことについても相当であるというべきである。
③ 乙の適正報酬額について検討すると、製造業を営む法人の役員に対して支給される報酬の額は、基本的に、当該役員の現に遂行する職務の内容に基づいて定められるべきものと解されるところ、乙の遂行した職務の内容については、本件各事業年度を通じて、酒類製造業を営む法人の非常勤の役員として一般的に想定される範囲を超えるものであったとは認められず、このことからすれば、本件各事業年度における乙の適正報酬額は、いずれも認定した比準法人における非常勤の役員に対する平均報酬額を超えるものとは直ちに認め難いというべきである。そして、認定判断した本件各事業年度におけるXの収益及びその使用人に対する給料の支給の状況に照らしても、上記の判断が不合理であるとみるべき事情はうかがわれない。
④ 以上によれば本件各報酬額については、平成16年5月期については36万円余、平成17年5月期については130万円余、平成18年5月期については123万円余を超える部分の金額をもって、「不相当に高額な部分の金額」であると認めるのが相当である。
学生や未成年の子供を役員とする場合
将来の後継者となる者として、学生や未成年の子供を役員としている中小企業は確かにあります。ただし、一般的には役員ではなくアルバイトをしている者が多い世代でしょう。
ですから、税務調査が入った際には、実態がどうなっているかを必ず調べられると思ってください。過大役員給与と認定されたり、実際は代表者である親の役員給与であると判断されないように注意が必要です。
例え、子供が将来自分の後継者となる者であるとしても、知識、経験、勤務状況、職務内容等からみて給与が過大であれば、当然、否認されます。
以下のような否認事例があります。
- 大学に在籍中の取締役(代表取締役の長女18才)に対して支給した役員報酬の額が過大であるとされた事例(東京地裁昭和51年7月20日判決・訟月22巻11号2621頁、東京高裁昭和53年11月30日判決・昭和51年(行コ)55号、最高裁第一小法廷昭和54年9月20日判決・昭和54年(行ツ)36号)
- 大学に在籍中の監査役(代表取締役の息子)に対して支給した報酬全額が否認された事例(長崎地裁昭和42年10月6日判決・昭和41年(行ウ)6号、福岡高裁昭和43年3月29日判決・昭和42年(行コ)14号)
- 海外在住の学生である役員(取締役の息子及び娘)に対して支給した役員報酬全額が、実質的に代表者に支払われたものとされた事例(東京地裁平成8年11月29日判決・判例時報1602号56頁、東京高裁平成10年4月28日判決・税資231号866頁、最高裁平成11年1月29日第三小法廷判決・税資240号407頁)
東京地裁昭和51年7月20日判決(訟月22巻11号2621頁)
(判示要旨)
原告会社Xが取締役丙(Xの代表取締役甲の長女)に対して取締役報酬として昭和41事業年度分に93万円を支払った旨の申告をしたところ、被告税務署長Yがそのうち60万円を超える分についてこれを否認したことは当事者間に争いがない。
なお、次の各事実が認められる。
丙は、Xの代表取締役甲の長女で、Xの従業員として就労し、月額3万円の給与の支給を受けていたところ、甲の後継者という立場から、昭和41事業年度中の昭和41年5月、Xの取締役に就任したが、就任当時同人は18才であって、しかも大学国文科第1学年(昼間)に在籍し、学業の余暇を利用して、Xの経理関係の帳簿の整理、自動車運転等の職務に従事していたものである。
ところでXの右事業年度中の取締役に対する報酬額は、代表取締役の甲に対し240万円(月額20万円)、専務取締役の乙(Xの代表取締役甲の妻)に対し、126万円(月額10万5000円)、X設立以来の非常勤の取締役である山田(同族ではない)に対して60万円(月額5万円)、同じく非常勤の取締役である鈴木(同族ではない)に対して24万円(月額2万円)であり、使用人に対する給料の最高額は23才の成年男子に対する月額3万円である。
認定事実からすると、丙は将来甲の後継者となる者であるとしても、丙の知識、経験、取締役として就任間もない事実、勤務状況、職務内容等からみた同人の会社経営に参画する程度と他の取締役、使用人に対する報酬、給与の額等を併せ考えると、丙に対して支払われるべき報酬の客観的相当額は、いかに高くみても山田に対する報酬額以上には出ないものというべきであるから、丙に対する報酬額93万円のうち、60万円を超える分は、不相当に高額な金額であると認めるべきである。
従って、Yが法人税法34条1項(当時)に基づき、申告額のうち60万円を超える分の損金算入を否認したことは違法ではないといわなければならない。
遠方の年老いた親に給与を支払う場合
現在では、リモートワークの普及により、遠方にいたとしても業務はできます。ただし、税務調査が入った際に、実態がどうなっているのかは必ず調べられます。
実態として、親に生活費を渡しているような場合ですと、当然、給与として認められることはないでしょう。