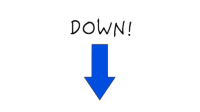
概要
民法上、「売買」はお金と財産権との交換です(民法555)。財産権相互の交換は、「交換」となります(民法586)。
売買契約に関しては、民法上では個人間だけに限定しているわけではありません。そのため、個人と法人、または法人間で売買が行われることもあるということになります。税法上、問題になるのは時価と売買価格が違う場合です。ここでは時価よりも低い価格で売買が行われる低額譲渡について説明したいと思います。
低額譲渡における個人と法人の関係は、以下の4つの形式に分類することができます。
①個人から個人への低額譲渡、②個人から法人への低額譲渡、③法人から個人への低額譲渡、④法人から法人への低額譲渡、となります。
形式によっては、物を売った人である「売り手」と、物を買った人である「買い手」の両者とも税金がかかります。
個人から個人への低額譲渡
贈与税がかかるのは、個人が個人への低額譲渡した場合です。「売り手」は、実際の売却金額(譲渡価額)を譲渡収入(所法36①)とし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。
取得価額よりも低い金額で売却した場合(譲渡損失が発生した場合)は、原則的に税金はかかりません。また、時価の2分の1未満の価額による譲渡の場合は、その譲渡損失はなかったものとみなされます(所法59②、所令169)。
一方、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた「買い手」には、時価と売買価格の差額に対して贈与税がかかります(相法7)。ここでいう時価とは、売買されたものが不動産など(土地・借地権・家屋・構築物)の場合には、他人(第三者)との間で取引される売買金額(取引時価)のことをいいます。また、売買されたものが不動産等以外の財産の場合は、相続税評価額が時価となります(平元・3直評5外)。詳しくは、「親から安く土地を買ったら?(みなし贈与)」のページまで。
なお、「買い手」が将来その譲渡所得の基因となる資産を譲渡して譲渡所得の金額の計算をすることとした場合、控除する取得費の額はいくらとすればよいかということについては、低額譲渡により取得した資産の取得費等は、実際に取得した時期に、実際に取得に要した金額を基にして算定するのが原則です。
ただし、例外として、時価の2分の1未満の価額による譲渡で、かつ、その譲渡により譲渡損失が生ずる取引により取得した資産に限って、直前の所有者の取得価額等を引継ぐことにしています(所法60①二、59②、所基通60ー1、措令②③)。
個人から法人への低額譲渡
〇 時価
ここでいう「時価」とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額をいうものと解されています。
ただし、「時価」といっても簡単に金額が算定できるものでないため、東京地裁令和2年10月23日判決(税資270号-113(順号13473))では、評価通達に定める路線価方式に基づいて算出された評価額を0.8で割り戻し(公示価格水準への割戻)、これに時点修正を加えて算定しています。つまり、公示価格がベースとなります。
千葉地裁平成3年2月28日判決(税資182号499頁)及び東京高裁平成3年11月21日判決(税資187号157頁)では、「公示価格は、客観的な取引価格に近いものであるが、通常は時価をある程度下回るものであることは公知の事実である。」と判示し、公示価格が所得税法上の時価を意味するというよりも、公示価格で課税することは時価課税の範囲内に納まるから違法にはならないものであることを示唆しているものと解されています。
また、東京地裁平成元年9月25日判決(税資173号913頁)でも、「地価(公示価格)は、(略)、実際にも時価に近いものであるが、通常は、標準地の時価をある程度下回るものであり、その意味で堅い評価であるとされていることは、公知の事実である。」と判示し、法人税法上の時価も、所得税法上の時価と同じような考え方となっています。
〇 法人税
財産を時価よりも低い値段で買う「買い手」である(通常の)法人には法人税がかかります。財産の取得価額は時価となり、時価と売買価格の差額は、受贈益になるからです(法法22②)。仕訳は以下の通りになります。
土地 ×××(時価) 現預金 ×××(売買価格)
受贈益 ×××
法人税においては、下記の所得税や贈与税における「著しく低い価額の対価」の場合とされていなく、「譲渡の時における価額(時価)に比して低い」場合に、受贈益が生じます。
つまり、著しく低い価額で譲渡を受けた場合でなくても、譲渡時の時価に比して低い価額で譲渡を受ければ、差額については受贈益が発生するということになります。
〇 所得税
「売り手」である個人も、財産を所得税法上の時価の2分の1未満(無償も含まれる。)で売った場合、時価により譲渡があったものとして「みなし譲渡所得課税」がかかります(所法59①、所令169)。
1つの契約により2以上の資産を一括譲渡した場合に低額譲渡に該当するかどうかは、譲渡したすべての資産の対価の額の合計額を基として全体的に判定します(所基通59-4)。
注意点は、この場合には、財産をもらった法人だけでなく、あげた個人も、財産を路線価ではなく「時価(公示価格水準等)」で税金を計算するということです。
なお、「みなし譲渡所得課税」とは、文字どおり譲渡所得があったとみなして、税金をかけるということです。財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。
そのため、含み益がある財産(例えば、購入したときより値上がりしている土地)を、法人に時価の2分の1未満(無償も含まれる。)で売った場合、財産を売った個人にも税金がかかることになります。
また、時価の2分の1以上の対価による法人に対する譲渡であっても、その譲渡が「同族会社等の行為又は計算の否認」(所法157)の規定に該当する場合には、「みなし譲渡所得課税」は、かかります(所基通59-3)。
「同族会社等の行為又は計算の否認」とは、同族会社等がある取引を行うことによって、株主等の所得税を不当に減少させる場合、その取引がなかったものとされるということです。
〇 贈与税
同族会社に時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合、株式等の価額が増加したならば、増加した部分に相当する金額を株主は贈与されたとされます(相基通9-2(4))。よって、「売り手」と「買い手」に税金がかかるだけではなく、その同族会社の株主にも贈与税がかかることになります。
「同族会社」に限定している理由は、利益の授受の認定について同族会社の行為計算否認規定(相法64)を前提にしているからとされています。
なお、この場合における「時価より著しく低い価額の対価」について、東京地裁令和2年10月23日判決では、評価通達による通常の相続財産の評価額と同程度であれば、「著しく低い価額の対価」とはいえないと解しています。
同族会社への不動産譲渡が低額譲渡であったとして所得税、相続税、法人税の更正処分等で争われた事例-東京地裁令和2年10月23日判決(税資270号-113(順号13473))(一部認容)(控訴)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 平成24年10月12日、Dは死亡した。原告Aは、Dの養子である。原告Bは、Dの子であり、Aの妻である。
原告C社は、発行済株式総数100株の特例有限会社として存続することとなった株式会社であり、平成24年9月15日まではDが、同日以降はBが代表取締役を務めていた。C社の株式(以下「本件株式」という。)は、同年10月6日当時、Dが60株、Bが40株をそれぞれ保有していた。
遺言により、A及びBが2分の1ずつ、C社の株式60株を含むDの権利義務を承継した(以下「本件相続」という。)。
② Dは、生前(平成24年10月6日)、C社に対し、Dが所有する33の不動産(以下「本件各不動産」という。)を、代金1億2000万円で売り渡した(以下「本件譲渡」という。)。
③ Dの相続人であるA及びB並びにDから本件各不動産の譲渡を受けたC社が、本件譲渡は低額譲渡であったとして、所轄税務署長Yから、所得税(甲事件)、相続税(乙事件)、法人税(丙事件)等につきそれぞれ更正処分等(以下「本件各更正処分」という。)を受けたことから、Aらはそれらの処分の取消しを求め本訴を提起した。
④ DがC社に対し、1億2000万円で譲渡した本件各不動産について、Yは、不動産鑑定により価額は4億840万円と評価している。
(2)本件の主な争点
① 所得税(甲事件)に関する争点は、本件譲渡が所得税法59条1項2号の低額譲渡に該当するか否かである。
② 相続税(乙事件)に関する争点は、本件譲渡により、B保有の本件株式が増加し、その増加益をBがDから贈与により取得したか否かである。
③ 法人税(丙事件)に関する争点は、本件譲渡により、C社に受贈益が発生し、益金に加算すべきであるか否かである。
(3)判決要旨(一部認容・棄却)(控訴)
① 不動産の評価額
本件各不動産の時価を評価する必要があるところ、その評価方法は、評価通達に定める路線価方式に基づいて算出された評価額を0.8で割り戻し(公示価格水準への割戻)、これに時点修正を加えて評価額を算定する方式(評価通達を準用した方法)によるのが相当である。
これによれば、本件各不動産の本件譲渡時点における評価額(裁判所認定額)は、2億3489万円余である。
② 甲事件
所得税法59条1項2号、所得税法施行令169条により、譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時の価額の2分の1に満たない金額により法人に対する譲渡があった場合には、譲渡時の価額に相当する金額により資産の譲渡があったものとみなされるが、本件譲渡に係る売買代金1億2000万円は、本件各不動産の譲渡時点における各不動産の評価額2億3489万円余の2分の1(1億1744万円余)に満たない金額とはいえないから、本件譲渡に所得税法59条1項2号を適用することはできない。
③ 乙事件
C社はDとBの2名が発行済株式総数の全部を保有する同族会社であり、Bは、本件譲渡時点で本件株式40株を保有していた。そうすると、本件譲渡が「時価より著しく低い価額の対価で財産を譲渡した場合」に該当する場合には、本件譲渡によるB保有の本件株式の増加益は、BがDから贈与により取得したものとみなして(相続税法19条1項の規定により)相続税の課税価格に加算されることとなる。
評価通達が、公示価格の80%程度となることが想定されている路線価を基準に相続財産の価額を評価することとしていることに鑑みると、評価通達による評価額を0.8で割り戻した「評価通達を準用した方法」により算定した時価(公示価格水準)の80%程度あれば、評価通達による通常の相続財産の評価額と同程度であるから、「著しく低い価額の対価」とはいえないと解されるが、これを大きく下回る価額は、特段の事情がない限り、「著しく低い価額の対価」に当たると解される。
これを本件についてみると、本件譲渡の対価は1億2000万円であり、「評価通達を準用した方法」により算定した本件各不動産の評価額2億3489万円余の約51.1%であるから、所得税法59条1項2号の関係においては「著しく低い価額の対価として政令で定める額」による譲渡に当たらないとしても、相続税法9条の関係においては、「著しく低い価額の対価」で利益を受けさせたものに当たると解するのが相当である。
本件譲渡により、本件株式の1株当たりの増加益は32万7875円である。本件譲渡時点でBが保有する本件株式は40株であるから、増加益は合計1311万円余となり、この額が、BがDから贈与により取得したものとみなして相続税の課税価格に加算すべき額となる。
④ 丙事件
本件譲渡は、内国法人であるC社が、本件各不動産の譲渡時の時価である2億3489万円余に比して低い1億2000万円で各不動産の譲渡を受けたものであるから、差額の1億1489万円余についてはDから実質的に無償で経済的利益の供与を受けたものとして、C社に受贈益が発生するため、益金に加算すべきである。
法人から個人への低額譲渡
「売り手」である法人は、いくらで財産を売却したとしても、財産を時価で売却したとして法人税がかかります(名古屋地裁平成4年4月6日判決・税資189号24頁)。
法人税においては「有償又は無償による資産の譲渡」から収益が生じるとされています(法法22②)が、低額譲渡については、「有償による資産の譲渡」と「無償による資産の譲渡」の2つの取引で構成されていると考えるため、同様に、収益が生じます。
仕訳は以下の通りになります。
貸方(右側)は、時価と取得価額との差額が「売却益」となります。また、借方(左側)は、時価と売買価格の差額は、寄付金等になります。法人と個人間に雇用関係等(従業員・役員)があれば「賞与・役員賞与」(法基通9-2-9(2))になり、雇用関係がなければ「寄付金」となります。
取得価額300万円(時価1000万円)の土地を600万円で売却した。
現預金 600万円 土地 300万円
寄付金等 400万円 売却益 700万円
一方、「買い手」である個人には、時価との差額は経済的利益と認められ所得税がかかります(所基通36-15(1))。法人と個人間に雇用関係等(従業員・役員)があれば「給与所得」(名古屋地裁平成4年4月6日判決・税資189号24頁)になり、雇用関係がなければ「一時所得」となります。
関連記事
法人から法人への低額譲渡
「売り手」である法人は、上記と同じように財産を時価で渡したとして法人税がかかります。「買い手」である法人は、財産を時価で買ったことになり、受贈益として法人税がかかります。
まとめ
| 売買形式 | 売り手の課税 | 買い手の課税 |
|---|---|---|
| 個人から個人への低額譲渡 | 所得税がかかる | 贈与税がかかる |
| 個人から法人への低額譲渡 | みなし譲渡所得課税 | 法人税がかかる |
| 法人から個人への低額譲渡 | 法人税がかかる | 所得税がかかる |
| 法人から法人への低額譲渡 | 法人税がかかる | 法人税がかかる |

