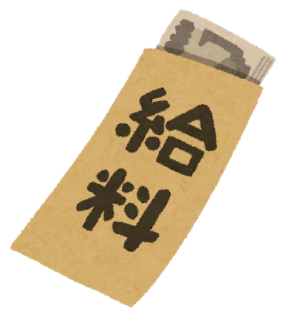概要
株式会社と違い、合同会社では社員の死亡によって当然に社員の地位が相続人に引き継がれるものではありません(会社法607①三)。
合同会社では社員同士の結びつきや信用関係が重要視されているため、ある社員が死亡した場合に、当然にその相続人が社員になってしまうならば、他の社員に影響を与えてしまい、会社の運営がうまくいかなく場合があるからです。
合同会社における社員とは、株式会社における株主と取締役を併せ持った性格があり、原則として、業務を執行する立場であるからです。
なお、合同会社の場合は、死亡または合併による消滅は社員の法定退社の事由となります。そして、相続人その他の一般承継人は持分の払い戻しを受けます(会社法611①)。
社員1名の合同会社の場合、社員が亡くなると法定解散事由となってしまいます(会社法641四)。
ただし、社員が死亡した場合または合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができます(会社法608①)。定款に記載する場合は、「社員及び出資」の章の中に記載するとよいでしょう。
社員1名の合同会社の場合は、必ず、定款で定めておいてください。また、合同会社の社員である経営者が亡くなったときでもスムーズに後継者に事業承継をしたいと思うなら、定款で定めることが必要です。
なお、「承継する旨」の定款の定めがある場合には、相続人その他の一般承継人(社員以外の者)は持分を承継したときに、その持分を有する社員となります(会社法608②)。そして、その一般承継人にかかわる定款の変更がされたものとみなされます(会社法608③)。
また、相続による一般承継人が2人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者1人を定めなければ、その持分についての権利を行使することができません。ただし、合同会社が各一般承継人が権利を行使することに同意したならば、かまいません(会社法608⑤)。
定款の定め方
定款の定め方は、いろいろなパターンが考えられます。
「例えば、社員の死亡時に特定の相続人が持分を承継するという定めも可能である(省略)。また、①相続人が希望する場合に持分を承継する、②他の社員が同意をした場合に相続人が持分を承継する、③相続人は(他の社員の同意や相続人の意思表示などがなくとも)当然に持分を承継する、といった定めもいずれも可能である(省略)。合併の場合も、同様に他の社員の同意を条件としたりするなどの定め方が可能となろう」(神田秀樹(編)会社法コンメンタール第14巻239ページより引用)
なお、特定の相続人に持分を承継させる場合には、その旨についての定款の記載だけでなく遺言書の作成も必要になります。
定款例
(社員の相続)
第○条 社員山田太郎が死亡した場合には、当該社員の相続人山田花子は、社員山田太郎の持分を承継して社員となる。
(社員の相続)
第○条 社員が死亡した場合には、当該社員の相続人は、当該社員の持分を承継して社員となることができる。
(社員の相続)
第○条 社員が死亡した場合には、当該社員の相続人は、他の社員全員の承諾を得て、当該社員の持分を承継して社員となる。
(社員の相続)
第○条 社員が死亡した場合には、当該社員の相続人は、当該社員の持分を承継して社員となる。
(社員の相続及び合併)
第○条 社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継して社員となる。