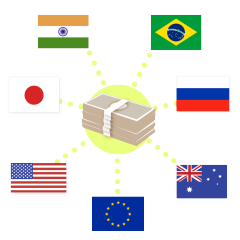概要
株式等の譲渡益は、一般的には、譲渡所得に該当しますが、場合によっては、雑所得や事業所得とすることができます。
ただし、現在は分離課税の適用を受けない有価証券と違い、そこまで神経質に区別をする必要がないのが実情です。
「昭和63年12月の改正で、株式等の譲渡益は、平成元年4月1日以降は、それが事業所得にあたるか、譲渡所得にあたるか、それとも雑所得にあたるかを問わず、他の所得と分離して(略)課税されることとなった」(租税法第二十四版/金子宏著/弘文堂)
所得区分の判定
株式等の譲渡による所得が雑所得、事業所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定します。
ただし、一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えないとされています(措通37の10・37の11共-2)。
(1) 上場株式等で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得
(2) 一般株式等の譲渡による所得
この理由について、租税特別措置法通達逐条解説(大蔵財務協会)では、以下のように解説しています。
「まず、株式等の性質から上場株式等と一般株式等に区分の上、上場株式等は流動性が高いことから『営利・継続取引』される可能性が高いとして事業・雑所得に区分し得るものとする一方、一般株式等は流動性が低いことから『営利・継続取引』される可能性が低いとして譲渡所得に区分することになる。次に、上場株式等であっても、その上場株式等の所有期間が長期(所有期間1年超)にわたるものの所得の実現は保有期間中の値上り益の実現とみて、譲渡所得に区分するものである。」
なお、投資一任口座における上場株式等の売買から生じる所得区分は、雑所得に該当すると考えられています。その理由は次のとおりです(国税庁HP質疑応答事例「投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分」)。
・投資一任契約は、所有期間1年以下の上場株式等の売買を行うものであること。
・投資家が報酬を支払って、有価証券の投資判断とその執行を証券会社に一任し、契約期間中に営利を目的として継続的に上場株式等の売買を行っていると認められること。
(株式等の譲渡に係る所得区分)措置法通達37の10・37の11共-2
株式等の譲渡(措置法第37条の10第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づき一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、その者の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない。
(1) 上場株式等で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得
(2) 一般株式等の譲渡による所得
(注) この場合において、その者の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記(1)に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない。
所得区分の意義
株式等に係る譲渡所得等の金額は、株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいうこととされており、この各種所得ごとの計算においては次のように特例や必要経費の控除が認められていることから、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算過程上、所得区分は意味を持つことになります。
1 譲渡所得の場合、次のような特例が認められています。
イ 相続税の取得費加算の特例(措法39)
ロ 保証債務を履行するために株式等を譲渡した場合で、その保証債務の主たる債務者などに対する求償権の行使ができなくなった場合の特例(所法64②)
2 雑所得、事業所得の場合、次のような必要経費の控除が認められています。
イ 証券会社等に支払う口座保管料、投資顧問料、残高手数料、管理費等
ロ インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などで株式の売却のために直接必要な支出であると認められる部分(FX取引や仮想通貨の必要経費と、基本的には同じような考え方)
例えば、口座保管料等は、雑所得、事業所得の場合は必要経費となりますが、譲渡所得の譲渡費用には該当しないということです。
最近では、残高連動手数料(レベルフィー)について、譲渡所得の譲渡費用なのか雑所得の必要経費なのかという議論があります。
譲渡費用(資産の譲渡に要した費用)とは、「資産の譲渡のため直接に必要な経費である」(金子宏・租税法第24版284頁より引用)、「譲渡を実現するために必要な経費に限られ(る)」(大阪高裁昭和61年6月26日判決・税資152号540頁)と、学説、裁判例共に限定的に解釈されています。
「株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われている」とは
株式等の譲渡益を譲渡所得として申告する場合は、実務上、問題になることはないでしょう。問題は、雑所得あるいは事業所得として申告できるのかということです(信用取引や投資一任契約による取引、いわゆるラップ取引に係る上場株式等の譲渡所得は雑所得あるいは事業所得として取扱って差支えないこととされています)。
措置法通達37の10・37の11共-2では、「事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定する」と記載されていますが、具体的には、これだけではよくわかりません。
なお、同通達注書きで「上場株式等で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない」と記載されています。
では、1年を超えて持っていたものを譲渡した場合、必ず、譲渡所得としないといけないのか、また、多くの銘柄を持っていた場合、銘柄ごとに所有期間を管理しておかないといけないのか等いろいろ疑問が生じます。
ここで、ある程度、参考になるのが、平成元年3月31日まで規定されていた「継続的取引基準」ではないでしょうか。
平成元年3月31日まで規定されていた「継続的取引基準」
昭和63年度税制改正により、平成元年4月1日以後の株式譲渡による所得は全て課税されることになったのですが、それまでは、昭和30年代から、一定の取引等を除いて非課税とされていました(もともとは、昭和28年以降、資本市場育成などの目的から株式等譲渡益は非課税であった)。
当時の状況は、誰が何万株売ったという資料が課税庁に行かず、課税庁が株式等の譲渡益を正確に捕捉する手段を持たなかったため、全てを課税対象としてしまうと譲渡損ばかりが申告されてしまうという技術上の問題もありました。
当時は、株式の譲渡損(事業所得ならば)は総合課税(当時の税制では)により給与所得等他の所得と損益通算ができていたため、譲渡損ばかりが申告されてしまうと課税上問題であり、原則、非課税としてしまえば譲渡損を申告できないため、その方が課税上都合よかったのです。
昭和63年度税制改正前(平成元年3月31日以前の株式譲渡について)の所得税法9条では「次に掲げる所得については、所得税を課さない。」とし、同条1項11号で「有価証券の譲渡による所得のうち、次に掲げる所得以外のもの」とし、原則、株式譲渡による所得は非課税とし、同号イ「継続して有価証券を売買することによる所得として政令で定めるもの」等一定の取引に該当した場合には、課税すると規定されていました。
所得税法9条1項11号イを受けて、所得税法施行令26条では以下のように規定されていました。
1 法第9条第1項第11号イ(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、有価証券の売買を行なう者の最近における有価証券の売買の回数、数量又は金額、その売買についての取引の種類及び資金の調達方法、その売買のための施設その他の状況に照らし、営利を目的とした継続的行為と認められる取引から生じた所得とする。
2 前項の場合において、同項に規定する者のその年中における株式又は出資の売買が次の各号に掲げる要件に該当するときは、その他の同項に規定する取引に関する状況がどうかであるかを問わず、その者の有価証券の売買による所得は、同項の規定に該当する所得とする。
一 その売買の回数が50回(昭和63年以後は、30回)以上であること。
二 その売買をした株数又は口数の合計が20万(昭和63年以後は、12万)以上であること。
3、4項は省略
このように、昭和30年代から昭和62年12月31日までは、原則として、株式譲渡による所得は非課税であったのですが、年50回以上かつ20万株以上の取引から生じた所得は、営利を目的とした継続的行為と認められる取引から生じた所得として雑所得(事業的規模なものは事業所得)として課税されていました。
なお、昭和62年度税制改正により、昭和63年1月1日以後に譲渡するものから、売買回数50回以上を30回以上とし、売買株数を20万株以上を12万株以上とする課税対象の拡大が行われましたが、昭和63年度税制改正により、平成元年4月1日以後の株式譲渡による所得は全て課税(また、総合課税から分離課税へ転換)されることになったのです。
つまり、長年にわたって、年50回(30回)以上かつ20万(12万)株以上の取引から生じた所得は、営利を目的とした継続的行為と認められる取引から生じた所得として雑所得(事業的規模なものは事業所得)として課税されていたため、ある程度の目安となるのではないでしょうか(もっとも、当時と現在では証券状況が違いますが)。
この場合のポイントは、回数等をどう判定するかということになり、当時の所得税基本通達9-15等で規定されていましたが、その解釈を巡って、納税者と課税庁で争われていました。
なお、「年50回(30回)以上かつ20万(12万)株以上の取引」と、具体的に法令で規定されていたため、株式の譲渡において「営利を目的として継続的に行われる」とは何ぞやについて争われる理由がありませんでした。
そのため、租税特別措置法通達逐条解説(大蔵財務協会)の37の10・37の11共-2の解説において、参考判例として記載されているのが、絵画の譲渡が営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡に当たるか否か争われた東京高裁平成10年12月17日判決(税資料239号528頁)ということになっています。
大阪地裁平成8年8月28日判決(税資220号346頁)要旨
所得税法9条1項11号イ(昭和62年法律第96号による改正前のもの)、同法施行令26条1項(昭和62年10月政令第356号による改正前のもの)によると、有価証券の譲渡による所得は、営利を目的とした継続的行為と認められる取引から生じた所得のみを課税の対象とし、営利を目的とした継続的行為か否かは、有価証券の売買の回数、数量、金額、取引の種類、資金の調達方法、売買のための施設その他の状況に照らして判断するものとされている。そして、同法施行令26条2項によると、当該年中における株式又は出資の売買の回数が50回以上であり、かつ、売買をした株数又は口数の合計が20万以上である場合には、その他の同条1項に規定する取引に関する状況がどうであるかを問わず、右売買による所得は、営利を目的とした継続的行為と認められる取引から生じた所得に該当するものとされている。
平成3年2月18日裁決(名裁(所)平2第77号)要旨(昭和60年分所得税)
証券会社に委託して株式の売買を行った場合における株式の売買回数は、証券会社との間の委託契約ごとに1回と計算するのが相当であり、当該委託契約の内容につき、値段の変更など重要な要素の変更が行われたときは、当該変更の時において別個の委託契約が締結されたものとして売買回数を計算する。
証券会社に委託して行う株式の売買が証券会社との間の一の委託契約に基づいて行われたものであるかどうか明らかでない場合には、証券会社から交付を受けた売買報告書に記載されている取引ごとに1回とすることとする。ただし、同一銘柄につき同一日付で交付を受けた売買報告書が2以上ある場合においては、その日の当該銘柄に係る取引は、売買報告書の数のいかんにかかわらず、売付け又は買付けの別にそれぞれ1回と計算することが相当である。
証券会社との間の一の委託契約に基づいて行われたことが明らかな売買、例えば、委託の際に証券会社が交付した総括表に記載されている内容に従って行われた売買は、証券会社との間の一の委託契約に基づいて行われた売買であることが明らかであるから、当該総括表により売買回数を計算することとなる。この場合、当該総括表に記載されている同一銘柄に係る取引が2回以上にわたって行われた場合には、当該銘柄に係る売買報告書に、その内出来である旨の表示がされることになっており、この表示がされているものについては、当該総括表に基づく売買回数を1回と計算するのが相当である。
当審判所の調査したところに基づき判断すると、総括表の交付を受けている株式の売買回数は計32回、総括表の交付を受けていない株式の売買回数は計9回となり、請求人の株式売買回数は計41回と認められる。したがって、請求人の売買株数は20万株以上であるが、売買回数は50回未満となるので、請求人の株式の売買による所得は所得税法施行令第26条第2項の規定の要件に該当せず、所得税法第9条第1項第11号イの規定により非課税所得となり、更正は違法であるから、その全部を取り消すべきである。
東京高裁平成10年12月17日判決(税資料239号528頁)要旨
ある資産の譲渡による所得が「営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得」に当たるか否かの判断に当たつては、その者の行っている資産の譲渡の客観的な態様・状況からみて経常的、計画的に発生する所得か否かを判断すべきであり、具体的には、①譲渡人の既往における資産の売買回数、数量又は金額、②売買のための資金繰り、③当該譲渡に係る資産の取得及び保有の状況等を総合して判断するのが相当である。
各事実を総合的に判断すれば、納税者Xは、多数の絵画を銀行からの借入金によつて購入、保有し、多数回にわたつて売買し、また、現実にも、多額の譲渡益を生じていることからして、本件絵画の売買は、「営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡」に該当するものというべきである。したがつて、本件絵画の売買による所得は法33条2項1号に定める「営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得」に該当し、譲渡所得には該当しないというべきである。
Xは、前記の①ないし③の要素に加え、④広告と宣伝の有無、⑤諸施設の規模等も判断要素として考慮すべきであり、これらの要素を検討すれば、本件絵画の売買が「営利を目的」とするものでないことは明らかであり、右売買による所得は譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、広告・宣伝を行い、又は相当規模な保管施設等を設けて行われた資産の譲渡は、経常的・計画的に行われたものであることを推認する事実となり得るが、広告・宣伝を行わず又は保管施設等を設けていないからといつて、直ちに資産の譲渡が臨時的・偶発的に行われたものであるということにはならないというべきである。
雑所得なのか事業所得なのか
株式の譲渡による所得が譲渡所得でないとすると、今度は、雑所得なのか事業所得なのかの問題が生じますが、ほとんどの場合、雑所得に該当するでしょう。
ただし、現行の所得税においては、雑所得なのか事業所得なのかでは大きな問題にならないため、さほど気にする必要はないでしょう。
上場株式等の譲渡損益について譲渡所得、雑所得、事業所得があった場合には区分ごとに計算をし、損失がある場合は、他の譲渡所得、雑所得、事業所得から控除(通算)し、控除しきれない損失があれば、申告分離課税を選択して申告をした上場株式等の配当等と損益通算ができ、また、3年間の損失の繰越ができます。
例えば、上場株式の譲渡損が雑所得に該当したとしても、分離課税で他の株式の譲渡益等と通算できますし、損失の繰越ができるということになります。
つまり、上場株式の譲渡益が雑所得、事業所得のどちらに該当したとしても、通算や損失の繰越(相対取引の場合等は除く)には影響を与えないため、そこでの争いは不毛だということです。
あえて、雑所得、事業所得の違いをいうならば、事業所得の場合、青色申告の適用が考えられます。ただし、事業所得ならば、前提として株式取引の売買回数が大量にあることとなり、それを全て記帳管理することは事務量がかなりかかるので、法人化してない個人の納税者がするのは現実的ではないといえます(将来的には、クラウド会計で簡単に同期化し記帳管理できると思いますが)。
よって、現在は、譲渡所得なのか、それとも雑所得なのかだけを判断すればよいということになりますが、株式の譲渡益が原則非課税で、一部の取引が雑所得あるいは事業所得として課税されていた時代は、その雑所得あるいは事業所得は総合課税の対象とされていました。
つまり、雑所得か事業所得なのかで、給与所得等他の所得と損益通算できるか否かの違いがあったので、雑所得なのか事業所得なのかについて、納税者と課税庁で争われていました(結果は、ほとんどが損益通算できない雑所得認定)。
当時の所得税基本通達9-13(1)では、以下のように規定されていただけで、雑所得なのか事業所得なのかの線引きについては具体的にはよくわからない状態でした。
「同号(所得税法9条1項11号)イ又はロに掲げる所得は、有価証券の取引のための施設、その者の職業その他諸般の事情に照らし、その者が常業として有価証券の取引又は買集めを行っていると認められる場合には、事業所得とし、その他の場合には雑所得とする。」
東京地裁昭和48年7月18日判決(税資70号637頁)要旨
本件株式取引における売買回数や売買株数は所得税法施行令26条2項に定める要件を大きく上廻つており、営利性有償性および継続性・反覆性が認められるけれども、原告は訴外会社の代表取締役として生活の資のほとんど大部分を同会社より得ていること、株式取引のための人的物的設備を設けておらず、証券会社の外務員の勧奨によつてこれを開始し、その助言によつて投機的目的のために行なつたものであり、自らの責任において企画をたてこれを遂行したり、あるいは相当程度の精神的ないし肉体的労力を用いたものとは思われないことなどの点から考えれば、本件株式取引は社会通念上いまだ事業と認めるに足りない。したがつて、本件株式取引によつて生じた損失は事業所得金額の計算上生じたものとは認められず、雑所得金額の計算上生じたものというべきであるから、その損益通算は許されない。
大阪高裁昭和50年3月26日判決(昭和49年(行コ)8号)要旨
株式等の取引行為が、所得税法上の事業に該当するか否かは、結局、一般社会通念に照らしてきめるほかないと思われるが、その判断に際しては、営利性・有償性の有無、継続性・反覆性の有無のほかに事業としての社会的客観性の有無が問われなければならず、この観点からは、当然にその取引の種類、取引における自己の役割、取引のための人的・物的設備の有無、資金の調達方法、取引に費した精神的、肉体的労力の程度、その者の職業・社会的地位などの諸点が、検討されなければならない。そして、事業としての社会的客観性が認められうるというためには、相当程度安定した収益を得られる可能性がなければならないと解される。
昭和55年11月3日裁決(裁事21集19頁)要旨
株式の取引が事業に当たるか否かは、一般社会通念に照らして判断するほかはないが、そのためには事業としての社会的客観性が問われるべきであり、この観点からすれば、その取引の種類、取引におけるその者の役割、取引のための人的、物的設備の有無、資金の調達方法その他諸般の状況等を総合勘案して判断すべきものであり、単に所得税法施行令第26条第2項各号に規定する株式の売買回数及び売買株数を充足しているだけでは足りず、株式のために投下若しくは動員された資金の額及び人的物的設備等が相当程度の規模によっていることを要すると解されるところ、請求人の株式取引のために費やした精神的、肉体的労力の程度、取引のための資金調達の方法、その人的、物的設備の組織的な利用状況、請求人の社会的地位等から判断して、本件の株式取引は事業に当たるとする社会的客観性を有しているものとは認められないので、当該株式取引から生じた損失の額を、雑所得を生ずべき営利を目的とした継続的行為から生じた損失の額と認定した原処分は適法である。
広島高裁昭和58年8月31日判決(税資133号583頁)要旨
本件有価証券の取引については、イ)年間売買回数は47回であること、ロ)従業員、事務所等の設備は設けていないこと、ハ)納税者1人でもつぱら投機的目的のために、日経新聞や証券会社のパンフレツトを参考にし、取引の注文は電話又は証券会社のセールスマンを通じて行つていたという程度のものであること、ニ)前2年分には、有価証券売買による所得の申告はしなかつたこと、ホ)納税者は、その生活の資を給与所得、事業所得及び不動産所得から経常的に得ていたこと、ヘ)青色申告の承認を得ていたが、有価証券取引について帳簿は備付けていなかつたことが認められ、右事実に照らすと、右有価証券取引によつて生じた損失は、非課税所得に係るものであつて、少くとも事業所得に係るものではないから、他の所得と損益通算することはできない。