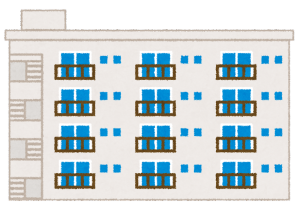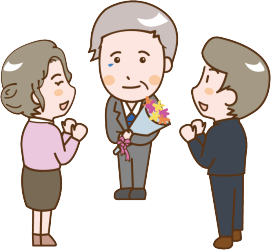役員貸付金の利息
会社は利益を追求するものであるため貸付けをした場合は利息をとる必要があります。そして、会社の役員に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります(所基通36-49、租法93②)。
(1) 会社が他から借り入れて貸し付けたものが明らかである場合は、その借入金の利率
(2) その他の場合は、利子税特例基準割合による利率
平成30年~令和2年中に貸付けを行ったものについては、年1.6%
令和3年中に貸付けを行ったものについては、年1.0%
令和4年~令和7年中に貸付けを行ったものについては、年0.9%
令和8年中に貸付けを行ったものについては、年1.3%
会社が役員に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、原則として、役員に対して経済的利益の供与がなされたものとして給与として課税されることになります。
また、会社側の処理としては、その役員に対して定期同額給与を支給している場合には、給与として課税される利息の差額が毎月おおむね一定であれば、定期同額給与として処理できる可能性があります(法法34,法令69①,法基通9-2-9(7)、9-2-11(2))が、その額が毎月著しく変動するものは除かれることになっています。
法人税基本通達逐条解説(9-2-11、税務研究会出版局)では、以下のように解説しています。
「金銭の貸付けであれば、元本の返済状況等により利息の額が遁減していき毎月の経済的利益の額が一定しないものもあろうが、そのような場合であってもその額が毎月著しく変動するものでなければ、『その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの』として取り扱われる。」
なお、役員に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合であっても、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、給与として課税しなくてもよいことになっています(所基通36-28)。
(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員に対して金銭を貸し付ける場合
(3) (1)及び(2)以外の貸付金の場合で、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合
所得税基本通達36-49(利息相当額の評価)
使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》に規定する利子税特例基準割合による利率により評価する。
所得税基本通達36-49(利息相当額の評価)の定めは合理的
東京地裁平成27年5月26日判決(税資265号-86(順号12669))では、所得税基本通達36-49(利息相当額の評価)の定めは合理的なものであると以下のように判示しています。
| 使用者が役員等に貸し付けた金銭が、使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかでない場合に、利息相当額を個別に評価することとすると、貸主と借主の関係、担保の有無とその種類、貸付期間など種々の要素により異なった評価額が生じることとなり、納税者の予測可能性を害する上、課税事務の統一的な執行が困難になるおそれを生じさせるから、客観性を有する基準によって画一的に評価するという基本通達36-49の定めは、納税者の予測可能性の向上、納税者間の公平、納税者の便宜及び徴税費用の節減という見地から見て合理的なものというべきである。 (略) 基本通達36-49は、利息相当額を評価する利率として、利子税における特例基準割合を採用したものであるが、利子税の割合は税法上の基準金利(国から延納税金に相当する金銭を借り入れた場合の約定利率に相当するもの)と考えられ、客観性を有することに加え、特例基準割合が、国民にとって最も分かりやすい基準割引率を基準とし、かつ、変動要素を持った利率であることに照らすと、特例基準割合を採用したことには合理性があるというべきである。 |
認定利息は複利計算しないといけないのか?
本来、会社は役員に貸し付けをしていたら利息を現預金でもらわないといけませんが、そうでない場合があります。その場合、 認定利息を計算した上で以下のような仕訳をします。
未収金 〇円 受取利息(雑収入) 〇円
問題は、この認定利息の集積された未収金の残高に対しても、更に認定利息を計算しなくてはいけないのかということです。例えば、役員貸付金残高が100万円、認定利息の集積された未収金残高10万円の場合、100万円に対して利息計算するのか、それとも10万円プラスして計算しなくてはいけないのかということです。
原則としては、利息計算に当つては、複利計算によるようなことはしないで、元本である役員貸付金100万円についてだけ利息を認定することとし、認定利息の集積された未収金10万円については、利息を認定しません。
ただし、その利息を元本に繰り入れた場合または元本についてだけ返済があり、利息について未収のまま放置している場合等特に課税上弊害があると認められるような場合には、この限りでないとされるため、注意が必要です(「認定利息の取扱について」昭和29年9月15日・直法1―165・国協178)。
ですから、認定利息の集積額として、未収金を積み上げたまま放置するようなことはせずに、定期的に精算するようにしましょう。
期中で役員貸付金残高が変わったら
期中で役員に追加で貸し付けたり、又は、返済してもらって役員貸付金残高が変わる場合があるでしょう。この場合の認定利息の金額は、貸付金残高にあった利息が合理的と考えられます。
例えば、利率1%で、1事業年度中(365日)に200万円の貸付金だった日数が165日で、100万円の貸付金だった日数が200日の場合、以下のように利息計算をします。
200万円×1.0%×(165/365)+ 100万円×1.0%×(200/365) =14,520円
内部文章(法事例2054 他からの借入資金を役員に貸し付けた場合の利息の計算額)
〔問〕 会社が役員に金銭の貸付けを行った場合の利息の額の計算について、次の場合にはどのように取り扱われるか。
(1) 会社が、他の銀行等から借入れを行った資金を貸し付けた場合
(2) 会社の自己資金を貸し付けた場合
(3) 会社の定期預金を担保にして、不動産担保の場合より低い利率で借り入れた資金を貸し付けた場合
〔答〕 (1)会社が他の銀行等から借入れた資金を役員に貸し付けた場合は、原則としてその借入金と同じ利率により計算した額、(2)会社の自己資金を貸し付けた場合は、通常取得すべき利率により計算した額、(3)会社の定期預金を担保にして借り入れた資金を貸し付けた場合は、定期預金を担保にして借り入れた利率(不動産担保の借入利率より低い利率)により計算した額によればよい。
法人が、役員等に対し、通常より低い利率で金銭の貸付けを行った場合には、通常の利率により計算した利息の額から、その役員等から徴収した利息の額を差引いた差額は、その役員に対する給与として取り扱われる。〔法基通9-2-9(7)〕
銀行等からの借入金を貸し付けた場合とは、通常借入れがない法人が、一時的に納税資金等の調達のために借入れをした場合は、その借入資金を貸し付けたことにはならず、この場合の利率は利息の認定とは関係がないことになる。
〔法法34〕
内部文章(法事例3318 一括評価金銭債権となる役員に対する貸付金)
〔問〕 役員に対する貸付金は貸倒引当金の設定の対象となる一括評価金銭債権に該当するか。
〔答〕 役員に対する貸付けの事実が明らかであれば貸金に該当する。
貸倒引当金の設定の対象となる一括評価金銭債権とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で、個別評価の対象となった金銭債権及び非適格合併等により合併法人等に移転する金銭債権を除いたものとされており、役員に対する貸付金が排除される規定はない。〔法法52(2),法令96(6)〕
したがって、役員に対する貸付金は一括評価金銭債権となる。同族会社の役員であっても同様である。
なお、役員に対する貸付けの事実が明らかであることの証明として、「金銭消費貸借契約」が結ばれているか、貸付金に対する認定利息の計上があるかなどがポイントとなる。
役員借入金の利息
会社は利益を追求するものであるため借入をしても利息を払わなくてよければ払わなくてもよいです。中小企業の役員が、会社にお金を貸して(会社からすれば役員借入金)、利息をもらっていないケースは多いです。この場合でも通常は、よっぽどでない限り、個人に利息認定はされていない状態です。個人の担税力を増加させるような経済的価値が流入していないからです。
会社代表者から同族会社への3,000億円を超える無利息融資に対して、同族会社の行為計算否認規定を適用し、会社代表者には利息相当分の雑所得があるものとしたパチンコ平和事件(東京地裁平成9年4月25日判決・税資223号500頁、東京高裁判決・税資243号127頁、最高裁平成16年7月20日第三小法廷判決・集民214号1071頁)がありますが、一般の中小企業のレベルには当てはまらない事案だと思います(ただし、無利息でも絶対に大丈夫とは言い切れませんが)。
会社が役員借入金に対して利息を支払っている場合は損金に算入できますが、その利息支払いの際に源泉徴収義務の必要はないです(役員が居住者の場合)。また、役員がもらう利息は利子所得ではなく、通常は、雑所得(事業から生じたと認められる場合は事業所得)となります(所法23①、所基通35-1(1)、35-2(6))。
なお、同族会社の役員などについては、その法人から給与所得のほかに、貸付金の利子をもらっている場合は、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合でも確定申告をしなければならないことになっています(所法121①柱書但書、所令262の2)。同族会社を用いた租税回避への対抗措置として規定されているのです。
役員が個人的に銀行から、お金を借り、それを銀行借入利息と同率で会社に貸した場合
例えば、役員甲がZ銀行から1億円を借入し、そのうち5,000万円円を会社Aへ貸付け、その貸付利息がZ銀行のレートと同じの場合、このZ銀行に対する支払利息(5,000万円/1億円相当)は、役員甲の雑所得の必要経費として認められると考えられます。
結果的に、役員甲の会社Aへ貸付け利息としての雑所得は、収入金額=必要経費であるため、0円となります。
平成17年10月21日裁決(東裁(所)平17第49号)判断要旨
同族会社A社が利息相当額として支払った金員のうち、適正利率(A社に対する金融機関によるスプレッド貸しに準じて算定)までの部分については、実質的な「法人への貸付金」に係る利息と認めるのが相当であり、所得税法35条1項に規定する雑所得に該当する。適正利率を超える部分については、請求人がA社の取締役として受けた利益供与であり、役員報酬に該当すると認められるから、その所得区分は給与所得である。
関連記事
パチンコ平和事件-東京地裁平成9年4月25日判決(税資223号500頁)要旨
株主等から同族会社に対する無利息貸付けについて検討するに、ある個人と独立かつ対等で相互に特殊関係のない法人との間で、当該個人が当該法人に金銭を貸し付ける旨の消費貸借契約がされた場合において、右取引行為が無利息で行われることは、原則として通常人として経済的合理性を欠くものといわざるを得ない。そして、当該個人には、かかる不自然、不合理な取引行為によつて、独立当事者間で通常行われるであろう利息付き消費貸借契約によれば当然収受できたであろう受取利息相当額の収入が発生しないことになるから、結果的に、当該個人の所得税負担が減少することとなる。そして、右の消費貸借が株主等の所得税を減少させる結果となるときは、同族会社が当該融資金を第三者に対する再融資の用に供する場合でなくとも、不当に株主等の所得税を減少させる結果となるものというべきである。
したがつて、株主等が同族会社に無利息で金銭を貸し付けた場合には、その金額、期間等の融資条件が同族会社に対する経営責任若しくは経営努力又は社会通念上許容される好意的援助と評価できる範囲に止まり、あるいは当該法人が倒産すれば当該株主等が多額の貸し倒れや信用の失墜により多額の損失を被るから、無利息貸付けに合理性があると推認できる等の特段の事情がない限り、当該無利息消費貸借は所得税法157条(同族会社等の行為又は計算の否認)の適用対象になる。
そして、本件貸借には、特段の事情は認められない。
同族会社への無利息貸付けは、経済的合理性を欠くものと認められ、受取利息相当額を雑所得の総収入金額に算入すべきであるとされた事例-令和6年6月10日裁決(東裁(所)令5第120号)(棄却)
(1)事案の概要
請求人Xが、同族会社(3社)に無利息で金銭の貸付けをしたところ、原処分庁が、当該貸付けはXの所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものであるとして同族会社の行為又は計算の否認規定を適用し、当該貸付けに係る受取利息相当額の雑所得があるとして所得税等の更正処分等をしたのに対し、Xが、当該貸付けはXの所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものではないなどとして、その全部の取消しを求めた。
(2)本件の主な争点
本件各無利息貸付けは、所得税法157条1項に規定する「所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当するか否かである。
(3)裁決要旨(棄却)
① 所得税法157条1項の趣旨、内容からすれば、同項にいう「所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、所得税の負担を減少させる結果となるものをいうと解するのが相当である。そして、株主等からの同族会社等に対する金銭の無利息貸付けが経済的合理性を欠くものであるかどうかについては、当該貸付けの目的、金額、期間等の融資条件、無利息としたことの理由等の諸事情を総合的に考慮して判断すべきである。
② 本件各無利息貸付けは、本件各社に需要が生じた資金を融通するなどの目的で行われたものであるところ、いずれも総額で多額に及ぶ金銭を無利息、無期限、無担保で貸し付けるものであって、その金額、期間等の融資条件は、独立かつ対等で相互に特殊関係のない当事者間で通常行われる取引とは大いに異なる点があるというべきである。また、本件各無利息貸付けについては、Xが自らの経営責任を果たすためにこれを実行したなどの事情をうかがうこともできない。
③ 以上の諸事情を総合すると、本件各無利息貸付けは、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、所得税の負担を減少させる結果となるものとして、所得税法157条1項に規定する「所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当するというべきである。
④ Xは、一般に、個々の貸付けにおける金利は、無リスク金利に当該貸付けにおける貸倒れリスクを加味して決定されるものであるところ、Xファミリーの間で行われる貸付けにおいては、その構成員間の信用の相互補完によって実質的に貸倒れリスクがないといえることから、本件各無利息貸付けは、Xの所得税の負担の軽減を図るものではなく、本件各社に経済的利益が生じるものでもない旨主張するとともに、実質的に貸倒れリスクがないといえる理由として、現にXファミリーの構成員が外部の金融機関からの借入れとスワップ取引を組み合わせた一体の取引によって実質的にマイナス金利での資金調達を行った実績もある旨主張する。
⑤ しかしながら、個々の貸付けにおける貸倒れリスクの有無は飽くまで当該貸付けにおける貸付金額等に左右されるというべきものであるところ、本件各無利息貸付けがいずれも総額で多額に及んでいることからすれば、本件各社に本件各無利息貸付けに係る貸倒れリスクがないとはいえず、このことは、金融機関からの借入れとスワップ取引を組み合わせた一体の取引によって実質的にマイナス金利での資金調達を行った実績があるからといって左右されるものでもない。したがって、Xの主張は前提において理由がなく、採用できない。