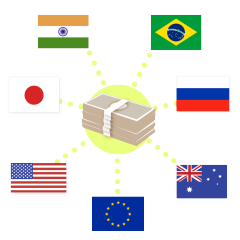概要
借入金で株式等を取得した場合には、その年中に支払った利子を、配当収入か株式譲渡収入のいずれかから控除することができます。
株式等を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものがある場合には、原則として、その利子の額のうちその株式等を所有していた期間に対応する部分の金額をその年中の配当等の収入金額から控除することとされています(所法24②)。
ただし、譲渡所得等の基因となった株式等の取得に要した負債の利子については、譲渡所得等の金額の計算上控除することとし、配当等の収入金額から控除しないこととされています(所法24②かっこ書き、33③、措法37の10⑥二、三、37の11⑥)。
配当所得の計算
株式等を取得するために借入れをした場合、株式等の取得時期や取得価額、資金の借入時期や借入金額等からその借入れが株式等を取得するためのものであることが明らかなときは、配当所得の計算上その株式の所有期間に対応する部分の借入金の利子を配当収入から控除することができます(所法24②)。
なお、「株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子」については、次のことに留意します(所基通24-5)。
| (1) 株式その他配当所得を生ずべき元本(以下「株式等」という。)を取得するために要した負債の利子で、その年中における当該株式等の所有期間に対応して計算された金額は、当該負債によって取得した株式等の配当等からだけでなく、他の株式等の配当等からも控除できること。 (2) 負債によって取得した株式等を処分した場合には、その処分したときまでの期間の利子に限り控除できること。 |
配当について確定申告する際、配当所得の金額は、次のように計算します。
| 配当収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式等を取得するための借入金の利子= 配当所得の金額 |
ただし、譲渡した株式に係るものや、確定申告をしないことを選択した配当に係るものについては、配当収入金額から差し引くことができる借入金の利子には当たりません。
損益通算
配当所得の金額の計算上生じた損失は損益通算の対象から除外(所法69①)されているため、配当所得の収入金額を超える負債の利子があり、配当所得の金額の計算上損失が生じても、その損失を他の所得から控除することはできません。
配当所得に係る損失を損益通算の対象から除外された理由は、下記のためです。
「無配の株式を取得するために巨額の負債を負っている者が、たまたま他に少額の有配の株式を有することによりその配当の収入金額から負債利子を控除して多額の配当所得計算上の損失を生じせしめ、これを給与所得等から控除している事例が発生している。元本価値の値上がりを期待して投資される株式の性格を考えると、負債利子のうち相当部分は、現在一般的には非課税(編注:原則、非課税の時代があった)とされる株式の譲渡所得に対応すべきものと考えられ、また、家事費上の負債の利子が混入する危険性もある」(国税庁HP「損益通算制度について―タックス・シェルターへの対応を含めて―」高倉明著)
譲渡所得の計算
上記のように、株式等を取得するために借入れをした場合の利子は、配当収入から控除されるのが原則です。
ただし、株式等を譲渡した年は、配当収入から控除はできず、株式等の譲渡所得等(雑所得や事業所得を含む)の計算上、譲渡費用(雑所得や事業所得の場合は必要経費)として控除されます(所法24②かっこ書き、33③、措法37の10⑥二、三、37の11⑥)。
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する株式等を取得するために要した負債の利子の額は、株式等に係る譲渡所得等の基因となった株式等を取得するために要した負債の利子で、その年中における当該株式等の所有期間に対応して計算された金額とします(措通37の10・37の11共-15)。
株式等の譲渡所得等について確定申告する際、譲渡所得等の金額は、次のように計算します。
| 譲渡収入金額-取得費-株式等を取得するための借入金の利子= 譲渡所得等の金額 |
なお、株式ごとに配当所得、譲渡所得のどちらから借入金利子を控除するかを判断します。例えば、A株式、B株式とも借入金で取得した場合で、A株式は譲渡し、B株式は譲渡しなかった場合は、A株式については譲渡収入から借入金の利子を控除し、B株式については配当収入から借入金の利子を控除します。
区分することが困難な場合
実務上、借入金の利子を譲渡収入から控除するのか、配当収入から控除するのかを区分することが困難な場合が多々あります。
そのような場合には、次のように計算することができます(措通37の10・37の11共-16)。
① 譲渡所得等の計算上控除すべき借入金の利子=株式等を取得するために借入れをした利子×(借入金利子を差し引く前の株式等の譲渡所得等/Z)
② 配当所得の計算上控除すべき借入金の利子=株式等を取得するために借入れをした利子×(配当収入/Z)
Z=借入金利子を差し引く前の株式等の譲渡所得等+配当収入
計算例
(Q)令和6年4月1日に銀行から5,000万円を借りてA株式を5,000万円で取得し、令和8年10月3日に7,000万円で譲渡して、同日、借入金も一括返済した。
受取配当金と支払利子の状況は以下の通りであったが、各年分の所得計算はどうなるのか?
| 令和6年中 | 令和7年中 | 令和8年中 | |
|---|---|---|---|
| 受取配当金 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
| 支払利子 | 75万円 | 80万円 | 60万円 |
(A)
令和6年 配当所得 125万円(200万円-75万円)
令和7年 配当所得 120万円(200万円-80万円)
令和8年 配当所得 200万円
譲渡所得 1,940万円(7,000万円-5,000万円-60万円)
特定口座における株式等の譲渡と一般口座における株式等の譲渡とで負債利子の控除に関する取扱いが異なる
措置法通達37の11の3-14は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算において準用すべき取扱いから同通達37の10・37の11共-15(株式等を取得するために要した負債の利子)及び37の10・37の11共-16(配当所得の収入金額等がある場合の負債の利子)の取扱いを除いています。
措置法通達37の11の3-14(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用)
特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算、信用取引等(措置法第37条の11の3第2項に規定する信用取引又は発行日取引をいう。37の11の4-1において同じ。)に係る上場株式等の譲渡による雑所得等の金額の計算等については、37の10・37の11共-1から37の10・37の11共-12まで、37の10・37の11共-14、37の10・37の11共-18から37の10・37の11共-21まで、37の10・37の11共-24、37の11-1から37の11-13まで及び37の12の2-1の取扱いを準用する。