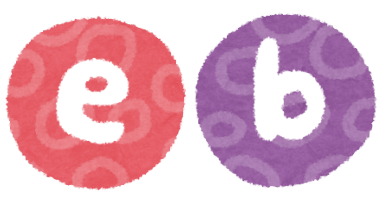概要
企業価値向上のためのインセンティブを提供し、優秀な従業員等を誘致・確保するために、株式等を付与する制度を設けている企業は増えてきています。
リストリクテッド・ストック(譲渡制限付株式、RS)とは、一定期間中における第三者への譲渡が制限されている株式のことです。譲渡制限期間経過後に譲渡制限が解除され譲渡することができるようになりますが、譲渡制限期間の間に役職員の勤務状況や会社の業績等が一定の基準を達しない場合は、没収されるという条件が付されています。なお、譲渡制限付株式のうち、税法上の要件を満たしているものを特定譲渡制限付株式といいます。
これに対して、リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)とは、RSとは違い、譲渡制限付株式そのものではなく譲渡制限付株式ユニットのことです。一定期間を設け、その期間経過後において一定要件を満たしていれば権利確定となり株式を取得することができます。また、権利確定と同時に、譲渡制限が解除されます。
RSとは違い、株式そのものが付与されるわけではないので、株式を取得することができる一定期間経過後まで議決権等が発生しません。我が国と違い欧米においてはRS制度よりRSU制度の方が多く利用されているといいます。
特定譲渡制限付株式
所得税法上の取扱い
特定譲渡制限付株式の所得税法上の取扱いを具体例で説明します。
① 譲渡制限付株式付与時
権利付与時には、付与された特定譲渡制限付株式は譲渡制限がかけられており、かつ、条件によっては没収される可能性もあることから、取得者である役職員は利益が手に入っていない状態なので課税はされません。
② 譲渡制限解除時
例えば株価が2,000円(上場会社の場合は、公表された最終価格)になった時に譲渡制限解除となった場合は、役職員が得た経済的利益2,000円は、給与所得等として課税されます(所令84①)。そして、その「譲渡制限が解除された日における価額」が、特定譲渡制限付株式の取得価額とされます(所令109①二)。
③株式売却時
役職員が譲渡制限解除後の株式を、株価が2,500円になった時に売却した場合、差額500円(2,500円-2,000円)が株式の譲渡所得として課税されます。
特定譲渡制限付株式の要件
特定譲渡制限付株式は、次の①~③の要件を満たすことが必要です(所令84)。
① 役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであること。もしくは、実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。例えば、会社が役員に金銭債権報酬を付与し、当該金銭債権を現物出資する形で株式交付を行うという仕組みです。
② 譲渡についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間(以下「譲渡制限期間」という。)が設けられていること。
③ 法人がその株式を無償取得(没収)することとなる事由(その株式の交付を受けた者が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこと、勤務実績が良好でないことその他の勤務の状況に基づく事由又は法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他の法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限る。)が定められていること。
譲渡制限解除時の所得区分
(1)発行法人と付与を受けた者との間に雇用契約があるような取締役や従業員の場合は、給与所得となります。ただし、主として職務の遂行に関連しない利益が提供されている場合には雑所得となります。また、退職に起因して権利行使が可能となっていると認められる場合には退職所得となります(所法28、36、所基通23~35共-5の2、23~35共-6)。
(2)仕入れ先やコンサルタントなど付与を受けた者の営む業務に関連して付与された場合は、事業所得または雑所得となります。
(3)上記(1)、(2)以外の場合は、原則として雑所得となります。
同一銘柄で譲渡制限のあるものとないものがある場合の取得費
特定譲渡制限付株式に該当するA社株式(以下「制限付A社株式」といいます。)とは別に従来から譲渡制限のないA社株式(以下「普通A社株式」といいます。)を保有していたが、今回、制限付A社株式に係る譲渡制限期間中に、普通A社株式の譲渡を行った場合、その譲渡所得の計算上、取得費の計算は、普通A社株式の譲渡所得に係る取得費は、制限付A社株式の取得はないものとして総平均法に準ずる方法により計算した金額となります(国税庁HP質疑応答事例「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)に係る譲渡制限期間中の取得費の計算」)。
特定譲渡制限付株式については、その「譲渡制限が解除された日における価額」が取得価額とされます。このため、その譲渡制限期間中は特定譲渡制限付株式の取得価額を計算することができないことから、その譲渡制限期間中に特定譲渡制限付株式と同一銘柄の株式等を譲渡した場合には、その同一銘柄の株式等に係る取得価額の計算において、その特定譲渡制限付株式は総平均法に準ずる方法による計算の対象となりません。
法人税法上の取り扱い
特定譲渡制限付株式(法法54①、法令111の2①)については、平成29年度税制改正により、「事前確定届出給与」として損金算入の対象となっています。その損金算入時期については、所得税法上、給与等課税額が生ずることが確定した日(例えば、取締役の退任日)の属する事業年度に損金算入されます。
なお、所得税で退職所得に該当する譲渡制限付株式であっても、法人税法上の退職給与に該当しません。そのため、損金算入する場合には、事前確定届出給与に該当させることが必要となります。
「事前の届出不要な」事前確定届出給与に該当させるためには、一定のスケジュールに沿って特定譲渡制限付株式を交付する必要があり、具体的には、① 職務執行期間開始日から1か月以内に取締役会等で特定譲渡制限付株式に係る報酬債権の額等を定め、② ①の取締役会等から1か月以内に特定譲渡制限付株式を交付する流れとなります(法令69 ③一)。
法人税法基本通達9-2-27の2(退職給与に該当しない役員給与)
役員の将来の所定の期間における役務提供の対価として譲渡制限付株式又は譲渡制限付新株予約権が交付される給与(法第34条第5項《役員給与の損金不算入》に規定する業績連動給与に該当するものを除く。)であって、その役務提供を受ける法人においてその期間の報酬費用として損金経理(退職給付引当金その他これに類するものの繰入れに係るものを除く。)が行われるようなものは、例えばその譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間の満了日又はその譲渡制限付新株予約権を行使することができる期間の開始日がその役員の退任日であることによりその役員において所得税法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等に該当するものであっても、法第34条第1項の退職給与で業績連動給与に該当しないものには該当しない。
特定口座への受け入れ
譲渡制限が解除されたときに、その株式を管理している証券会社等の特定口座に預け入れることは可能です。
平成30年(2008年)4月1日以降、譲渡についての制限が解除された特定譲渡制限株式等を一定の方法により特定口座へ受け入れることができ、具体的には次のように取り扱われます(措令25の10の2⑭二十五)。
1 対象となる上場株式等の範囲
特定口座への受入れの対象となる株式等とは、特定譲渡制限付株式等(注)で、その特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の口座(NISA口座及びジュニアNISA口座を除く。)において、その取得日から引き続きその口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、又は保管の委託がされているものをいいます。
(注) 所得税法施行令84条1項に規定する特定譲渡制限付株式又は承認譲渡制限付株式をいいます。いわゆるRS(リストリクテッド・ストック)です。
2 特定口座への振替の方法
特定口座への受入れは、特定譲渡制限付株式等の譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てを、その特定口座以外の口座からその特定口座への振替の方法により行います。
3 特定口座へ受入れる際の取得日及び取得に要した金額
①取得日 特定譲渡制限付株式等を取得した日
②取得に要した金額 譲渡制限が解除された日における金融商品取引市場の最終の価格(終値)
源泉徴収
給与所得となる場合、発行会社は源泉徴収を行い、翌月10日までに所轄税務署に納付しなければなりません。源泉徴収額が取締役や従業員の給与から天引きできる金額であれば良いのですが、源泉徴収額が支給給与を超えているような場合は、一旦、取締役や従業員から金額を預かるようなことをしているケースがあります。
また、海外親会社から付与されたRSで、経済的利益に対して日本子法人等で源泉徴収されていない場合は、確定申告をする必要があります。
リストリクテッド・ストック・ユニットに係る経済的利益は退職所得ではなく給与所得に該当するとされた事例-令和3年7月12日裁決(東裁(所)令3第4号)(棄却)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 審査請求人Xは、平成17年9月、A社に入社し、平成27年7月に同社を退職した。Xの退職に当たっては会社都合退職の手続がとられている。
② A社の親会社である外国法人B社は、長期の企業目的達成のためのインセンティブを提供し、優秀な従業員等を誘致・確保し、普通株式や現金報奨を獲得する機会を提供することを目的として、「成功に対する貢献」などを基礎としてリストリクテッド・ストック・ユニット(以下「RSU」という。)を付与する制度(以下「本件RSU制度」という。)を実施している。
なお、RSUは、B社の普通株式1株に等しい価値を持つ譲渡制限付株式ユニットであり、RSUを付与された従業員等は、RSUが所定の時期に権利確定(vest)した際に、当該RSUの数に等しいB社の普通株式を取得することができる。
本件RSU制度の概要は、以下のとおりである。
| (イ)RSUは、「RESTRICTED STOCK UNIT AGREEMENT」と題する文書(以下「本件RSU規定書」という。)等に定められた条件を前提として、その一定数が対象者に対して付与される。なお、従業員に対しては、本件RSU制度上、B社の人事報酬委員会がRSUを管理・付与することとされている。 (ロ)RSUを付与された従業員は、以下の一ないし三の条件に基づき当該RSUに関する制限が失効する時まで、当該RSUについて売却、移転、譲渡、抵当に入れることその他の処分行為の制限(以下「本件譲渡制限」という。)がされる。なお、B社は、従業員が雇用終了後にB社とのあらゆる契約に違反する場合、本件譲渡制限の対象となるRSUに関する報奨の全て若しくは一部を取り消し、又は当該報奨から得られた株式又は金額の払戻しを求めることができる。 一 従業員の雇用が継続している場合、RSUの付与日の1年後から1年ごとにRSUの4分の1ずつ権利確定(vest)し、同時に、本件譲渡制限が解除される。 二 RSUの権利確定(vest)及び本件譲渡制限が解除される前に雇用が終了した場合、一定の場合を除き、RSUは没収される。 三 上記二にかかわらず、雇用終了の理由が、会社側が特別退職金等を支払う場合の退職に該当するとき、RSUは上記一に基づき引き続き権利確定(vest)し、本件譲渡制限が解除される。ただし、本件RSU規定書に記載された要件を遵守しない場合は、当該RSUは没収される。 (ハ)権利確定(vest)したRSUは、本件RSU規定書に定める権利確定日(vesting date)に、振替決済方式で交付される普通株式の形で決済される。 |
③ Xは、平成25年から平成27年までの間に、本件RSU規定書等に基づき、平成25年2月に3,467ユニットを、平成26年2月に2,056ユニットを、平成27年2月に1,631ユニットのRSUを付与された〔以下、Xが付与されたRSUを「本件RSU」といい、このうちXが退職する直前まで権利が確定(vest)せず、本件譲渡制限が解除されていなかったRSUを「本件未確定RSU」という。〕。
B社は、平成27年2月以後、Xに対し、RSUを付与していない。
④ 本件未確定RSUは、XがA社を退職した後も、没収されなかった。本件RSU規定書には、退職に基因してRSUを付与する旨の規定はなく、XがA社を退職した際に、XとA社との間で、本件RSUに係る付与契約変更書などが改めて作成された事実はない。
A社は、Xの退職に際して、Xに対し退職金として、退職一時金及び特別退職金を支払った。
⑤ Xは、平成28年分の所得税等の確定申告書を提出しなかった。Xは、平成29年分及び平成30年分の所得税等について、法定申告期限内に確定申告書を提出したが、各確定申告書には、本件未確定RSUが権利確定した場合に得られる経済的利益(以下「本件経済的利益」という。)に係る所得について記載されていなかった。 ⑥ 原処分庁は、本件経済的利益は平成28年分ないし平成30年分(以下「本件各年分」という。)の給与所得に該当するとして、令和2年6月、平成28年分の所得税等の決定処分等並びに平成29年分及び平成30年分の所得税等の各更正処分等をした。
(2)本件の主な争点
① 本件経済的利益は、給与所得又は退職所得のいずれに該当するかである。
② 本件経済的利益の収入すべき時期はいつかである。
(3)裁決要旨(棄却)
① ある金員が、所得税法30条1項にいう「退職所得、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」に当たるというためには、それが、(イ)退職すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること、(ロ)従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、(ハ)一時金として支払われることの3つの要件を備えることが必要であり、また、同項にいう「これらの性質を有する給与」に当たるというためには、それが、形式的には上記(イ)ないし(ハ)の各要件の全てを備えていなくても、実質的にみてこれらの要件の要求するところに適合し、課税上、「退職により一時に受ける給与」と同一に取り扱うことを相当とするものであることを必要とすると解すべきである。
② 本件RSU制度は、B社からB社の従業員等に対して、B社の「成功に対する貢献」などを基礎として、B社の株式を支給する制度であり、すなわち、B社における従業員等報奨制度であると認められる。そして、Xは、A社に入社後、平成27年7月に同社を退職するまでの間、継続して同社に勤務し、本件RSUを付与された年の前年の業績に対して本件RSU規定書に基づき本件RSUを付与され、その結果、Xは本件経済的利益を得たのであるから、当該利益は、XのA社への職務の遂行に対する対価としての性格を有することが明らかである。したがって、本件経済的利益は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものと認められ、給与所得又は退職所得のいずれかに該当することとなる。
③ 本件未確定RSUは、Xの退職によっても没収されていない。そして、XがA社を退職した際に作成された雇用保険被保険者資格喪失確認通知書には資格喪失原因がA社の都合による離職である旨記載されており、実際にA社からの退職の際に特別退職金の支給を受けている。これらの事実関係からすれば、Xの退職は、「会社側が特別退職金等を支払う場合の退職」に該当すると認められる。したがって、本件未確定RSUは、雇用が継続している従業員が有するRSUと同様の条件で権利が確定(vest)し、本件譲渡制限が解除されていくことになる。他方で、本件RSU規定書には、従業員等の退職に基因してRSUを付与する旨の規定は存在せず、実際にもRSUを付与する権限を唯一有しているB社が、Xの退職に際して、XにRSUを付与した事実はない。したがって、Xが退職したにもかかわらず本件未確定RSUが没収されなかった原因は、Xが本件RSU規定書の各条件を満たしたことであったといえる。
④ 本件経済的利益は、本件RSU規定書の条件を満たすことによって得たといえるのであって、Xの退職、すなわち雇用関係の終了という事実によって初めて給付されたものではないし、一時金として支払われたものでもない。そうすると、本件経済的利益は、上記①の(イ)及び(ハ)の各要件を満たしておらず、また、実質的にみて上記各要件の要求するところに適合するともいえない。したがって、本件経済的利益は、退職所得には該当せず、給与所得に該当する。
⑤ 所得税法36条1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、その年において「収入すべき金額」(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする旨規定している。これは、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとしてその権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用したものと解すべきであり、ここにいう収入の原因となる権利が確定する時期は、それぞれの権利の特質を考慮し決定されるべきものである(最高裁昭和53年2月24日第二小法廷判決・民集32巻1号43頁参照)。
⑥ 本件RSU規定書に基づき付与されたRSUは、雇用の継続等の一定の要件を満たすことによって、RSUに基づく権利が確定(vest)して没収されないものとなり、同時に譲渡制限が解除され、権利確定したRSUは、RSU規定書に定める権利確定日(vesting date)に振替決済方式で交付される普通株式の形で決済されるものである。以上のようなRSUの特質を考慮すれば、RSUから生じる経済的利益について、その収入の原因となる権利が確定したといえる時期は、RSU規定書に定められた権利確定日であるといえる。