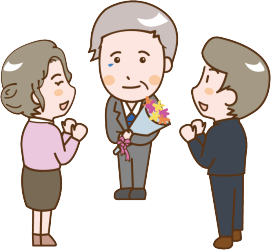
概要
個人事業を何年間していて、その後に、法人成りされた方は多いでしょう。また、この場合に、個人事業の時から引き続き、法人成りした会社に勤務する従業員がいる場合もあるでしょう。
では、その従業員が会社で何年間か働いた後、退職した場合に支払う退職金について、会社は個人事業当時からの勤続年数を通算して適正額を算出し、損金にしてよいのかという問題があります。
例えば、個人事業の時は5年間勤務し、法人成りした会社に10年間勤務した場合、退職金の支給額の算定根拠年数は、15年と10年のいずれにすべきかということです。
また、退職金をもらう従業員側にとっても、退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数は、個人事業当時からの勤続年数を通算してよいのかという問題があります。
個人事業当時、生計を一つにする家族従業員ではない一般の従業員であった者の場合
(法人側)
個人事業を引き継いで法人成りにより設立された法人が個人事業当時から引き続き在職する従業員の退職に際して退職金を支給した場合は、その退職が設立後相当期間経過後(一般的には、設立後5年間を超える期間後)に行われたものであるときは、個人事業当時の勤続年数を含めたところでの退職金を支給してもその金額を損金に算入することができるものとされています(法基通9-2-39)。
なお、法人設立後相当期間経過を経過しない段階で退職した従業員がいる場合は、個人事業当時の退職金分については、更正の請求により個人事業主としての必要経費になります。
つまり、個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。
(従業員側)
退職給与規程等に個人事業当時からの期間を含めた勤続期間を基礎として退職金を計算する旨が定められており、それに従って計算した退職金を支払うのであれば、原則として、個人事業当時の勤続年数を含めて(勤続期間の通算)退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数を計算することができます(所令69①、所基通30-10、国税庁hp質疑応答事例「個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数」)。
そのため、退職給与規程等により、退職金の支払額の計算の基礎とする期間が、法人成りしてからの期間によるものとされている場合には、個人事業当時の勤続期間との通算は認められません。
法人成りにより設立された法人で役員となった者について
法人税基本通達9-2-39においては、「個人事業を引き継いで設立された法人が個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職」と記載されています。
そのため、法人成りにより設立された法人で役員となった者については適用できないのかという疑問が生じますが、福島地裁平成4年10月19日判決(税資193号78頁)では、法人成り後に役員になった者についても、個人事業において退職給与として必要経費として認められる部分については別異に解する必要はないと、以下のように判示しています。
「『法人成り』の場合に、個人経営時から引き続き在職する役員に対する退職給与のうち、損金又は必要経費として認められる部分については、別異に解する理由はない。」
青色事業専従者であった者の場合
青色事業専従者であった者の場合は、あくまでも法人設立の日から退職するまでの期間が勤続年数となるので、個人事業当時の勤続期間を通算することはできません(福島地裁平成4年10月19日判決・税資193号78頁)。
所得税法には、生計を一つにする家族従業員に対する退職金の必要経費算入という考え方はないものと解されるからです。
個人事業主であった者の場合
個人事業主であった者の場合は、あくまでも法人設立の日から退職するまでの期間が勤続年数となるので、個人事業主当時の期間を通算することはできません(平成20年11月21日裁決・福裁(法・諸)平20第4号)。
そもそも、個人事業主自身に給料や退職金を支払い、必要経費算入することを所得税法上、想定していないからです。
まとめ
ある程度、個人事業で儲かっているならば、早めに法人成りしないと、経営者や、そこで働いている家族は、退職金を貰う段階で損をしてしまうということです。
通達
法人税基本通達9-2-39(個人事業当時の在職期間に対応する退職給与の損金算入)
個人事業を引き継いで設立された法人が個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職により退職給与を支給した場合において、その退職が設立後相当期間経過後に行われたものであるときは、その支給した退職給与の額を損金の額に算入する。
所得税基本通達30-10(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合)
令第69条第1項第1号ロ及びハただし書の規定は、法律若しくは条例の規定により、又は令第153条《退職給与規程の範囲》若しくは旧法人税法施行令第105条《退職給与規程の範囲》に規定する退職給与規程において、他の者の下において勤務した期間又は前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間(以下30-11においてこれらの期間を「前に勤務した期間」という。)を含めた期間により退職手当等の支払金額の計算をする旨が明らかに定められている場合に限り、適用するものとする。
福島地裁平成4年10月19日判決(税資193号78頁)(棄却)(確定)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 原告X法人は、精神科の病院を経営している医療法人であるが、その前身は、乙(X法人の現理事長である丙の父。)が、昭和35年2月に開業した個人病院(乙が院長であり医師。)であり、その後昭和61年3月3日に法人組織となり、現在に至つている。
X法人の設立に際しては、丙が理事長に就任し、丙の母甲が常務理事に就任した。なお、管理薬剤師であつた甲は、乙の個人病院開設時から常勤し、業務に従事してきたが、所得税法57条1項に定める青色事業専従者であった。
② 甲が昭和63年6月7日に死亡退職したため、X法人は同年9月30日、同人に対し、役員退職慰労金(以下「本件役員退職給与」という。)として9599万円を、遺族に対し、弔慰金として780万円をそれぞれ支給し、損金経理をした上で本件事業年度に係る法人税の確定申告を行つた。
なお、X法人は、本件役員退職給与の算定に当たっては、甲の退任時の報酬月額に役員在任年数及び最終役位係数(X法人の役員退職金規程による。)をそれぞれ乗じる方法を採用したが、甲の役員在任年数については、X法人設立前の乙の個人病院に業務に従事してきた年数(約26年)を含めた勤続年数とした。
③ これに対し、所轄税務署長である被告Yは、「役員退職慰労金9599万円のうち1757万6000円を超える7841万4000円」は不相当に高額な部分の金額に該当し、法人税法36条の規定により、損金の額に算入されないと更正処分等をした。
なお、Yは、甲の役員在任年数について、個人病院の業務に従事してきた年数(約26年)を含めないで算定した。
④ X法人は、同処分を不服として取消しを求めた。
(2)本件の主な争点
適正役員退職給与額を算定する場合、その算定要素である役員在任年数に、個人病院の業務に従事してきた年数(約26年)を含めることの適否についてである。
(3)判決要旨(棄却)(確定)
① 理論的には、「法人成り」の場合、個人事業主と法人とは別個の独立した法人格を有し、法人成りの前後で、経営主体及び納税主体が法的に異なるものであるから、使用人に対する退職給与が、個人事業主と法人のどちらの収入又は収益を得るために必要な経費であつたといえるかという見地から、(1)個人経営時の在職期間に対応する退職給与は、個人事業主の事業所得の必要経費に(一般的には個人事業主の最終年分の事業所得の必要経費として減額更正を行うべきことになる。)、(2)法人経営時の在職期間に対応する退職給与は法人の損金とすべきものである。
これは、個人経営時の在職期間に対応する分が未払退職給与という債務として法人に引き継がれているという事情によつても左右されない。
② 税務行政の実務の扱いでは、このような場合、使用人の退職が法人設立後相当期間の経過後に行われたものであるときは、個人経営時の在職期間に対応する分も含め退職給与の全額を法人の損金に算入することを認めている(法人税基本通達9-2-27、現行9-2-39)。この趣旨は、理論的には前記①で述べたとおりの処理をすべきではあるが、個人事業主が使用人に対し個人事業の廃業時点でその在職期間分の退職給与を支払つている事例は稀であり、法人が個人経営時の在職期間に対応する分もまとめて退職給与を支給する事例が多いという実情に鑑み、法人設立後相当期間の経過後(一般的には、個人事業主の最終年分の所得税について、国税通則法70条2項1号による減額更正ができなくなる5年の経過を想定していると解されている。)には、本来個人事業主の事業所得の計算上必要経費に算入すべき(本来法人の損金の額に算入できない)額を、便宜、法人の損金の額に算入することを許容しようというものであると解される。
③ 「法人成り」の場合に、個人経営時から引き続き在職する役員に対する退職給与のうち、損金又は必要経費として認められる部分については、別異に解する理由はない。すなわち、理論的には、役員に対する退職給与のうち、(1)法人経営時の在職期間に対応する部分で、相当と認められる金額は法人の損金に算入され、(2)個人経営時の在職期間に対応する部分で、個人事業主の事業所得の計算上必要経費として認められる金額はその最終年分の事業所得の計算上必要経費に算入されるべきであるが、法人設立後相当期間の経過後であれば、便宜(2)の部分も法人の損金に算入することが認められることになる。
④ しかしながら、本件の甲の場合、「法人成り」する以前の個人事業(乙及び丙)当時、所得税法57条1項に規定する青色事業専従者であつたのであるから、個人事業主である乙及び丙から、それぞれの個人事業の廃業時点で退職給与が支払われたとしても、同法56条により、個人事業主と生計を一にする親族に対する対価の支払として、個人事業主(乙及び丙)の事業所得の計算上必要経費に算入することはできないものであるから、仮に法人設立後相当期間の経過後であつても、当然に、「法人成り」したX法人の損金と認めることはできない。
平成20年11月21日裁決(福裁(法・諸)平20第4号)(棄却)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 請求人X社は、X社の役員であるAが個人で経営していた食肉小売業に係る事業を引き継ぎ、昭和62年5月1日、設立された。
② Aは、前記①の設立日から平成17年4月30日付で代表取締役を辞任するまでの間、X社の代表者として業務に従事した。
③ X社は、平成16年5月1日から平成17年4月30日までの事業年度において、Aに対する退職給与の額(以下「本件役員退職給与」という。)を損金経理した。
本件役員退職給与の算定に当たっては、退任時の報酬月額に役員在任年数及び功績倍率をそれぞれ乗じる方法(以下「功績倍率法」という。)が採用されているが、Aの役員在任年数については、法人設立前にAが個人事業として経営していた期間(以下「本件個人事業期間」という。)を含めた年数とした。
④ 原処分庁は、功績倍率法における役員在任年数は、法人税法施行令72条の規定により法人の業務に従事した期間となることから、Aの役員在任年数に本件個人事業期間を含めることはできないとして更正処分等をした。
⑤ これに対し、X社は更正処分等の取消しを求めた。
(2)本件の主な争点
適正役員退職給与額を功績倍率法により算定する場合、その算定要素である役員在任年数に、本件個人事業期間を含めることの適否についてである。
(3)判断要旨(棄却)
① 争点である役員在任年数については、法人税法施行令72条において、「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間」と規定しており、また、功績倍率法により同条に規定する退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を算定するためには、役員在任年数がその基準となることから、AがX社の業務に従事した期間となり、本件個人事業期間を含めることはできないこととなる。
② そうすると、Aは、X社が設立された昭和62年5月1日に代表取締役に就任し、平成17年4月30日に代表取締役を辞任しているから、本件役員退職給与の算定における役員在任年数については、AがX社の業務に従事した期間である18年とするのが相当である。
③ 原処分に違法はない。



