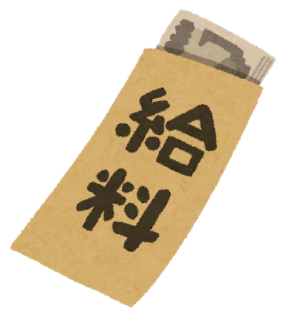概要
法人がその役員または使用人の海外渡航に際して支給する旅費(仕度金を含みます。以下同じ。)は、その海外渡航がその法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、その渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。
したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則としてその役員または使用人に対する給与となります(法基通9-7-6)。
この場合の給与は、臨時的な給与(賞与)として取り扱われますので、役員に対するものは、事前確定届出給与に該当するもの以外、損金の額に算入できないことになります。
なお、その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができます(法基通9-7-6注)。
横浜地裁平成17年1月19日判決(税資255号-18(順号9899))判示
海外渡航費が費用(法人税法22条3項2号)に該当するものとして損金の額に算入されるべきかどうかは、当該海外渡航の性質に照らし、それが当該法人の業務の遂行上必要な費用と認められるものであるかどうかによって判断すべきである。そして、当該海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかについては、渡航者と当該法人との関係、渡航の目的、渡航先、渡航先での当該渡航者の活動及び渡航期間等の諸般の事情を総合的に考慮して判断することが相当である。
業務の遂行上必要な海外渡航の判定
法人の役員または使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定することになりますが、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しません(法基通9-7-7)。
(1)観光渡航の許可を得て行う旅行
(2)旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
(3)同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
ただし、上記(1)から(3)に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金の額に算入されます(法基通9-7-10)。
(1)観光渡航の許可を得て行う旅行
相手国の事情により業務渡航ではビザがおりにくいため、業務のための渡航でも観光渡航の許可を得て渡航することもありえます。よって、このような場合には、当該旅行内容について実質的な判定をします。
すなわち、観光渡航の許可で渡航する場合でも、その海外旅行が、特定の取引先との商談、又は、特定の者との間の技術援助契約の交渉、締結等のためのものである場合のように、実質的に業務の遂行上必要と認められるものであるときは、その支出する海外渡航費は旅費として損金算入できます。
(2)旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行には、例えば、その目的地までは団体の一員として旅行し、目的地に到着した後は自由に行動できるもの、あるいは旅行経路及び旅行日程等を定め、特定都市における滞在中は自由に行動できるもの等、種々の形態のものがありますので、法人の役員又は使用人が、旅行業者が行う団体旅行に参加する場合でも、その旅行の途中で法人の業務の遂行上必要な行動をとる場合もあるでしょう。
そこで旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容等からみて、法人の業務に直接関係のあるものがあるときは、法人の支給する海外渡航に要する費用のうち、法人の業務に直接関係のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金算入が認められています。
業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費
法人の役員または使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、その役員または使用人に対する給与となります(法基通9-7-9)。
ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(その取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限ります。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につき、この「業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費」の規定が適用されます。
例
当社の社長が、ニューヨークの取引先との契約の締結のために海外渡航する予定です。その際、次の観光旅行を併せて行う場合、海外渡航費はどのように取り扱われるでしょうか。
(Q1)バンクーバーまで観光旅行をする。
(Q2)バンクーバーへは行かず、ニューヨーク近隣を観光する。
ニューヨークまでの往復旅費は、法人の業務の遂行上必要なものと認められ損金算入されますが、(A1)ニューヨーク以遠のバンクーバーまでの旅費、バンクーバーでの滞在費等は社長に対する給与になり、(A2)ニューヨークでの滞在費等は、業務遂行の日数と観光の日数との比等によって按分計算し、旅費として損金算入する額と社長に対する給与とする額を算定します。
海外渡航費に係る損金算入額の計算
海外渡航費に係る損金算入額の算定に当たっては、次に掲げる事項を具体的に説明する書類その他参考となる資料に基づき、その法人の海外視察等の動機、参加者の役職、業務関連性等を十分検討します(平成12年10月11日付「海外渡航費の取扱いについて(法令解釈通達)」1、以下「海外渡航費通達」とします。)。
(1) 団体旅行の主催者、その名称、旅行目的、旅行日程、参加費用の額等その旅行の内容
(2) 参加者の氏名、役職、住所
損金算入額の計算の方法
同業者団体等が行う視察等のための団体による海外渡航については、課税上弊害のない限り、その旅行に通常要する費用(その旅行費用の総額のうちその旅行に通常必要であると認められる費用をいう。以下同じ。)の額に、旅行日程の区分による「業務従事割合」を基礎とした損金算入の割合(以下「損金等算入割合」といいます。)を乗じて計算した金額を旅費として損金の額に算入します(海外渡航費通達2)。
ただし、次に揚げる場合には、それぞれ次によります。
(1) その団体旅行に係る損金等算入割合が90%以上となる場合 その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として損金の額に算入します。
(2) その団体旅行に係る損金等算入割合が10%以下となる場合 その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として損金の額に算入しません。
(3) その海外渡航が業務遂行上直接必要であると認められる場合(「業務従事割合」が50%以上の場合に限ります。) その旅行に通常要する費用の額を「往復の交通費の額(業務を遂行する場所までのものに限ります。以下同じ。)」と「その他の費用の額」とに区分し、「その他の費用の額」に損金等算入割合を乗じて計算した金額と「往復の交通費の額」との合計額を旅費として損金の額に算入します。
(4) 参加者のうち別行動をとった者等個別事情のある者がいる場合 当該者については、個別事情を斟酌して業務従事割合の算定を行います。
損金等算入割合
上記の「損金等算入割合」は、業務従事割合を10%単位で区分したものとしますが、その区分に当たり業務従事割合の10%未満の端数については四捨五入します(海外渡航費通達3)。
業務従事割合
上記の「業務従事割合」は、旅行日程を「視察等(業務に従事したと認められる日数)」、「観光(観光を行ったと認められる日数)」、「旅行日」及び「その他」に区分し、次の算式により計算した割合とします(海外渡航費通達4)。
| 視察等の日数÷(視察等の日数+観光の日数) |
業務従事割合の計算の基礎となる日数の区分は、おおむね次によります(海外渡航費通達5)。
(1) 日数区分の単位
日数の区分は、昼間の通常の業務時間(おむね8時間) を1.0 日としてその行動状況に応じ、おおむね0.25日を単位に算出します。
ただし、夜間において業務に従事している場合には、これに係る日数を「視察等の業務に従事したと認められる日数」 に加算します。
(2) 視察等の日数
視察等の日数は、次に掲げるような視察等でその参加法人の業種業態、事業内容、事業計画等からみてその法人の業務上必要と認められるものに係る日数とします。
イ 工場、店舗等の視察、見学又は訪問
ロ 展示会、見本市等への参加又は見学
ハ 市場、流通機構等の調査研究等
ニ 国際会議への出席
ホ 海外セミナーへの参加
ヘ 同業者団体又は関係官庁等の訪問、懇談
(3) 観光の日数
観光の日数には、次に掲げるようなものに係る日数が含まれます。
イ 自由行動時間での私的な外出
ロ 観光に附随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問
ハ ロータリークラブ等その他これに準ずる会議で、私的地位に基づいて出席したもの
(4) 旅行日の日数
旅行日の日数は、原則として目的地までの往復及び移動に要した日数としますが、現地における移動日等の日数でその内容からみて「視察等の日数」又は「観光の日数」に含めることが相当と認められる日数(観光の日数に含めることが相当と認められる当該移動日等の日数で、土曜日又は日曜日等の休日の日数に含まれるものを除きます。) は、それぞれの日数に含めます。
(5) その他の日数
その他の日数は、次に掲げる日数とします。
イ 土曜日又は日曜日等の休日の日数((4)の旅行日の日数を除きます。)。
ただし、これらの日のうち業務に従事したと認められる日数は「視察等の日数」に含め、その旅行の日程からみて当該旅行のほとんどが観光と認められ、かつ、これらの日の前後の行動状況から一連の観光を行っていると認められるような場合には「観光の日数」に含めます。
ロ 土曜日又は日曜日等の休日以外の日の日数のうち「視察等」、「観光」及び「旅行日」に区分されない休養、帰国準備等その他の部分の日数。
計算例
(Q) 当社の社長が、ニューヨークの取引先との契約の締結のために海外渡航する予定です。その際、ニューヨーク近隣も観光をします。
この場合の旅費として認められる金額及び役員給与とされる金額はいくらでしょうか。 旅費及び日程は以下となっています。
旅費
(1)往復の旅費、支度金、パスポート取得費用等 45万円
(2)業務遂行に直接要した費用15万円
(3)観光に直接要した費用 20万円
(4)業務、観光に区分できない費用 10万円
日程
(ア)業務遂行に要した日数 8日
(イ)観光に要した日数 4日(土日2日含む)
(ウ)ニューヨークまでの往復日数 3日
(A)旅行期間中に土日等の休日を利用して観光を行った場合には、その日数は原則として「その他」に含めて損金算入割合の計算要素から除くこととされているため、(イ)観光に要した日数は2日で計算します。
旅費
(1)+(2)+(4)×((ア)/(ア)+(イ))
=45万円+15万円+10万円×(8日/8日+2日)
=68万円
役員給与
(3)+(4)×((イ)/(ア)+(イ))
=20万円+10万円×(2日/8日+2日)
=22万円
同伴者の旅費
法人の役員が法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航に際し、その親族又はその業務に常時従事していない者を同伴した場合において、その同伴者に係る旅費を法人が負担したときは、その旅費はその役員に対する給与となります(法基通9-7-8)
ただし、その同伴が例えば次に掲げる場合のように、明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その旅行について通常必要と認められる費用の額は、旅費として損金の額に算入されます。
(1) その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
(2) 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合
(3) その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき
内部文章
法事例2112 海外渡航者のうち使用人兼務役員に対する給与
〔問〕 当社は、この度海外事情の視察のため当社の取締役営業部長をアメリカに派遺した。
この旅行費用のうち、当社の業務遂行上必要でない海外渡航費相当額についても全額当社が負担した。
したがって、海外渡航費のうち当社の業務遂行上必要でないものと認められる部分の金額はその役員に対する給与となることは承知しているが、その役員は使用人兼務役員であるから、給与のうち使用人分相当額は当社の損金として経理して差し支えないか。
〔答〕 業務遂行上必要でないと認められる金額の全部がその役員に対して支給した賞与として損金の額に算入されない。
(略)
法人が負担した海外渡航費のうち、法人の業務遂行上必要と認められない費用、すなわち、明らかに個人の負担すべき費用相当額は、法人がその使用人兼務役員に対して経済的利益の供与をしたものとして取り扱われる。その経済的利益の供与は海外渡航費という臨時的なものであるので、その使用人兼務役員に対する賞与に該当する。
ところで、使用人兼務役員に対して支給した賞与のうち使用人としての職務に対する賞与を損金の額に算入できるのは、その賞与を法人の使用人に対する賞与の支給時期に同時に支給する場合に限られる。〔法基通9-2-26〕
したがって、本問の場合は、使用人の地位に基づいて支給した賞与とは認められないので、海外渡航費のうち業務遂行上必要でないと認められる金額の全部が役員に対して支給した賞与として損金の額に算入されないことになる。
〔法法34〕
法事例2420 得意先の海外招待旅行に同伴した役員、従業員の海外渡航費
〔問〕 得意先の海外招待旅行に専務と役員でない営業部長が同伴した場合、両人の渡航費用は、観光目的の海外渡航のため両人に対する給与となるか。
〔答〕 招待旅行の同伴そのものは業務遂行上必要なものであるから、観光渡航の許可を得て行うものであっても同伴者に対する給与とはならない。
一般的には、役員又は使用人に支給する海外渡航費は、法人の業務の遂行上必要なものに限り旅費として認められるが、観光渡航の許可を得て行う旅行は、原則として業務の遂行上必要なものに該当しない。〔法基通9-7-6,9-7-7〕
その場合、法人の業務の遂行上必要と認められない海外渡航の際に支給される旅費は、原則として渡航する役員又は使用人の給与とされる。
一方、得意先を旅行に招待する費用は交際費に該当するが、その範囲には当該招待旅行のために要した一切の費用を含むので本問の同伴者の旅費はすべて交際費に該当する。
例えば専務の同伴旅費は交際費とし、営業部長の同伴旅費を給与とすると、後者は損金算入できるため法人にとって有利になるが、このような使い分けはもちろん認められない。
〔法法65,措法61の4〕
法事例2904 代表者が非常勤役員の夫人を同伴した場合の海外渡航費の処理
〔問〕 当社、代表者甲を中心とする同族会社で、甲の配偶者も非常勤監査役となっている。2か月甲が外国の取引先B社との商談等のために渡航したが、これには、甲の配偶者も同行した。これは、甲がかなりの齢(67歳)であることと、配偶者も役員としての地位にあることによる。
ところで、当社では、この両名の海外渡航費の全額を負担し、これを旅費の科目で損金に計上しているが、税務上の取扱いはこれでよいか。
〔答〕 本問の場合の代表者夫人の同伴については、その海外渡航の目的等からみて、その渡航目的を達成するために必要なものと認めることは困難と思われる。したがって、会社の負担した海外渡航費のうち代表者夫人に係る部分の金額は、一般的には損金算入できないものと判定されることになる。
法人の役員が法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航に際し、その親族又はその業務に常時従事していない者を同伴した場合において、その同伴者に係る旅費を法人が負担したときは、その旅費はその役員に対する給与とする。ただし、その同伴が例えば次に掲げる場合のように、明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その旅行について通常必要と認められる費用の額は、この限りでない。〔法基通9-7-8〕
(1) その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
(2) 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合
(3) その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき。
しかし、法人の役員又は使用人がその法人の業務上必要な会議に出席する場合に、夫人を同伴することが要件とされているようなこともあり、このような場合にも給与として取り扱うことは、その実情からみて適当ではないので、その同伴が明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要なものと認められる場合には、その同伴者の海外渡航費を法人が負担しても、その負担額については損金算入が認められている。
本問の場合には、法人税基本通達9-7-8ただし書には該当しないと思われる。
〔法法22〕
会社代表者の欧州旅行に要した費用が、当該会社の業務遂行上必要な費用ではないから損金に該当せず、右支出は当該代表者に対するかくれた賞与に該当するとされた事例-鹿児島地裁昭和42年10月12日判決(昭和41年(行ウ)3号)(棄却)(確定)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 原告X社は、石油その他の油類および各種塗料等の販売を業とする法人である。
② X社の代表者であつた甲が、昭和39年10月3日東京を出発し同月27日帰国した日本経営者団体連盟(以下「日経連」と略称する。)主催の欧州視察団に参加してなした出張(以下「本件欧州旅行」という。)に要した費用109万円余を販売費および一般管理費として経理し、法人税の申告をした。
③ これに対し、所轄税務署長Yは、本件欧州旅行は、その目的および成果などからみて、役員である甲個人の観光のための旅行であつて、X社の業務上必要な出張旅行ではないとし、右旅行に要した費用は甲個人が負担すべきものであり、その実質は役員個人の負担すべき費用を会社が支出したものであつて、かくれたる役員賞与と認むべきであるとし、更正処分等をした。
④ X社は、本件欧州旅行に要した費用は会社の業務遂行上必要な費用であるから損金であるとして、本訴を提起した。
(2)本件の主な争点
本件欧州旅行に要した費用は会社の業務遂行上必要な費用であつて損金として計上すべき性質のものであつたか否かである。
(3)判決要旨(棄却)(確定)
① (イ) 本件欧州旅行につき、甲は昭和39年8月11日鹿児島県知事に旅券発給の申請をしたが、その渡航目的は観光となつていること。
(ロ) 本件欧州旅行に関する欧州視察団編成要項によれば、旅行目的は、「欧州における主要都市の経営者団体、会社等を訪問し、経営管理の実際を視察調査するとともに、各国経営者との親善を深める。」というにあるけれども、右の目的自体が一般的内容を有するのみならず、予定された旅程表および実施された旅行の経過をみると、昭和39年10月3日航空機で東京を出発してから、順次スイス、イギリス、フランス、ベルギー、オランダ、西ドイツ、オーストリア、イタリアの各国を経廻り、同月26日スイスのチユーリツヒから帰国の途に就いたが右各国旅行中視察団は各地の有名な観光地に宿泊しまたはこれを通過し、旅行の全過程に近い大部分が観光に費されていること。
もつとも、道路など交通状況、国民所得、清費者物価、労使関係などについて一部調査した事実もうかがわれるが、これらはいずれも政治、経済、文化面の一般的な国民生活の状況に関するものであること。
の各事実が認められる。従つて以上の事実からすれば、X社の業務上、特にかかる観光旅行の形式等をとらざるを得なかつた如き特段の事情のない限り、本件欧州旅行は、やはり慰労その他主として観光のための旅行であつたと推認するのが相当である。
② 本件欧州旅行に要した費用は、たとい会社の旅費規定に基づいて甲に支給されたとしても、法人税法上においてはX社の業務遂行上必要な費用ではないから損金に該当せず、右支給は役員に対するかくれた賞与として利益金の処分に該当するものといわなければならない。したがつて、右旅費の損金算入を否認してなした本件更正処分には何ら取消すべき違法はない。
会社代表者のハワイ旅行等に要した費用が、当該会社の業務遂行上必要な費用でないから損金に該当せず、右支出は当該代表者に対する賞与に該当するとされた事例-岡山地裁昭和48年7月19日判決(昭和44年(行ウ)47号)、広島高裁岡山支部昭和49年7月26日判決(昭和48年(行コ)3号)(棄却)(確定)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① X社(原告、控訴人)は、敷物、織物等に関する記事を記載する新聞を発行することを目的とする新聞社である。
② X社は、その代表取締役である甲がした昭和39年2月のハワイ旅行に要した費用のうち50万円を調査費として同年7月31日同人に支払い、また昭和40年5月の中南米およびカナダ旅行に要した費用(ハワイ旅行に要した費用を含めて、以下「本件旅行費用」とする。)のうち30万円余を旅費として同年12月21日同人に支払い、前者を昭和39年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下昭和39事業年度という)の損金に、後者を昭和40事業年度の損金にそれぞれ計上したうえ右両年度分の法人税について確定申告をした。
③ これに対し、所轄税務署長Yは、本件旅行費用は、X社の業務上必要な費用とは到底認められず、損金に計上しえないものであり、これらはX社が甲に対し賞与として支出したものに他ならないとし、更正処分等をした。
④ X社は、本件旅行費用は会社の業務遂行上必要な費用であるから損金であるとして、本訴を提起した。
(2)本件の主な争点
本件旅行費用は会社の業務遂行上必要な費用であつて損金として計上すべき性質のものであつたか否かである。
(3)一審判決要旨(棄却)(控訴)
① X社の代表取締役甲は、昭和39年2月15日から同月21日までの間ハワイ旅行を、昭和40年5月1日から同月29日までの間中南米カナダ旅行をしたが、右旅行はいずれも日本交通公社海外旅行関西営業所の募集した、ハワイ旅行の場合ハワイ観光団に、中南米カナダ旅行の場合ニユーヨーク世界博覧会の見学を兼ねた中南米カナダ視察団に各参加したものであり、また右各旅行については、いずれもX社の業務命令、出張命令などは出されておらず、取材計画、用務終了の報告書ないし復命書の提出も全くなかつた。
しかも、それに要した旅費はX社から出発前には支給されず、旅行終了後相当の日時を経てから甲に支払われたがその算出の根拠は必ずしも明らかでない。
そして、ハワイ旅行の費用はX社の昭和39事業年度の中南米カナダの旅費は昭和40事業年度の各損金として計上された。
② 甲は主催者である日本交通公社海外旅行関西営業所の組んだスケジユール通り、参加団体と行動を共にし、スケジユールをはずれて行動したことはなく、いずれの旅行もその行程は殆んど観光に終始していた。
そして、X社は、その発行(毎月1、10、20日の3回)する敷物新聞に、昭和39年3月1日から同年4月20日までの間6回にわたつて美しいハワイと題する記事を昭和40年5月10日から同年9月1日までの間本紙社長の海外便りとして中南米から北米カナダへの旅と題する記事をそれぞれ記載したが、その内容は甲の旅行先の名所旧跡、産業、風土等の説明をしているものであつて、X社において甲が視察したと主張する敷物、住宅事情に関する内容の記事は殆んどみあたらない。
③ 以上①、②の事実を総合すれば、本件各旅行はいずれも旅行地における敷物、住宅事情の取材、調査を主としたものではなく、甲個人の観光旅行であつたと認めるのが相当である。
X社は、その発行する敷物新聞には、主として敷物に関連した記事を記載しているが、それ以外の記事も必要に応じ記載しており、本件旅行はいずれも同新聞に記載するための取材旅行であるから業務遂行目的を主とするものであると主張するが、本件各旅行はいずれも前記認定のとおり甲の観光を主たる目的とするものであり、X社が右に主張するように取材を主目的としたものとは解されず、右主張は採用しえない。
以上の考察からしてX社において支出したハワイ旅行に要した50万円および中南米カナダ旅行に要した30万円余は法人税22条3項所定のX社の業務遂行必要な費用とは認められず、甲に対する賞与といわざるをえない。
(4)控訴審判決要旨(棄却)(確定)
一審判決と同旨
会社代表者に同伴した代表者の長男の海外渡航費は、会社の業務の遂行上必要な費用ではないとされた事例-横浜地裁平成17年1月19日判決(税資255号-18(順号9899))(棄却)(確定)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 原告X社は、リヒテンシュタイン公国所在のC(以下「C社」という。)の日本総代理店として、貴金属洗浄液等の同社製品を輸入、製造、販売することを業務とする株式会社である。
甲及びその妻である乙は、いずれもX社の代表取締役であり(以下、両名を「甲ら」という。)、丙は、甲らの長男である。
② 甲らは、C社の主催する会議に出席するため、平成9年10月1日から平成10年9月30日までの事業年度(以下「平成10年9月期」という。)においてアメリカ合衆国等に1回、同年10月1日から平成11年9月30日までの事業年度(以下「平成11年9月期」という。)において同国に1回、同年10月1日から平成12年9月30日までの事業年度(以下「平成12年9月期」といい、これと平成10年9月期及び平成11年9月期とを併せて「本件各事業年度」という。)においてスイス連邦共和国及びアメリカ合衆国に各1回、それぞれ海外出張をし、その際いずれも、丙(当時7歳ないし9歳)を同伴した。
X社は、上記各海外出張について、丙に係る渡航費用を含む海外渡航費(以下、このうち丙の渡航に係る費用を「本件各渡航費」という。)を支出し、これを、X社の本件各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入した。
本件各渡航費の額は、それぞれ、平成10年9月期において28万7250円、平成11年9月期において20万8400円、平成12年9月期においては、スイス連邦共和国への出張分19万5768円及びアメリカ合衆国への出張分15万8220円の合計35万3988円である。
③ これに対し、所轄税務署長Yは、平成13年6月27日付けで、X社に対し、本件各渡航費を損金の額に算入することはできないとして、X社の本件各事業年度の法人税について、それぞれ更正処分等(以下「本件各更正処分等」という。)をした。
④ X社は、本件各渡航費は会社の業務遂行上必要な費用であるから損金であるとして、本訴を提起した。
(2)本件の主な争点
本件各渡航費が、X社の業務遂行上必要なものとして、X社の法人税に係る所得金額の計算上損金の額に算入されるべきかどうかである。
(3)判決要旨(棄却)(確定)
① 本件各渡航費に係る海外渡航は、甲らのC社の会議への出席が目的であり、これらの会議は、いずれもC社製品の販売に関する協議を中心的な内容とするものであったところ、丙は、当該海外渡航当時、7歳ないし9歳の小学生であって、X社の業務に従事していたわけでもないのであるから、これらの会議において、同人がX社の業務上必要な行為をする立場にあったということはできない。
② X社は、C社は経営者の後継者を含めた人的信頼関係の構築を重視しており、丙の同伴もC社の強い要請によるものであったと主張する。
しかし、C社において代理店の経営者の後継者を含めた人的信頼関係の構築を重視しているものとしても、丙はX社の業務に従事していない未だ小学生にすぎない者であることからすれば、同人が甲らの海外渡航に同伴することは、X社及びC社の経営者家族相互の信頼関係の醸成に資するということができるとしても、それ以上に、X社の現在の業務の円滑な遂行上の必要性があるものとまでは認め難い。
甲らないしC社の経営者において、丙が甲らの海外渡航に同伴することについて、将来の後継者の交流という目的を有しているとしても、そのような目的は、同人がX社の業務に何ら従事していない未だ年少の者にすぎないことからすれば、親子関係に基づく将来に対する抽象的な期待にとどまるものといわざるを得ず、そのための費用の支出をもって、X社の所得を算出する上で損金の額に算入すべき程度にX社の業務の遂行上必要があるものということは、困難であるというほかはない。
③ X社は、法人税基本通達9-7-8において、海外渡航費の損金算入が認められる例として、国際会議への出席等のために配偶者を同伴する場合が挙げられていることを指摘するが、このような海外渡航費が損金の額に算入されるかどうかは、国際会議への出席等という名目だけではなく、当該国際会議の性質や配偶者の同伴が必要な事情を個別的、実質的に検討して、あくまでも当該法人の業務の遂行上必要な費用であるかどうかによって判断されるべきものであって、同通達の規定もそのような趣旨のものと解される。
④ 本件各渡航費は、海外渡航費としてX社の損金の額に算入されるべき性質のものではなく、上記のところからすれば、丙の扶養者である甲が個人的に負担すべき費用というべきであり、これをX社が支出したことは、X社の甲に対する臨時的な給与、すなわち賞与として支給したものと認められるから、法人税法35条1項の規定により、X社の損金の額には算入されないものである。
したがって、本件各渡航費は、X社の本件各事業年度の損金の額には算入されず、また、X社は、甲に対する本件各渡航費の支給について、所得税を徴収し、国に納付すべき義務があるというべきである(所得税法183条1項)。