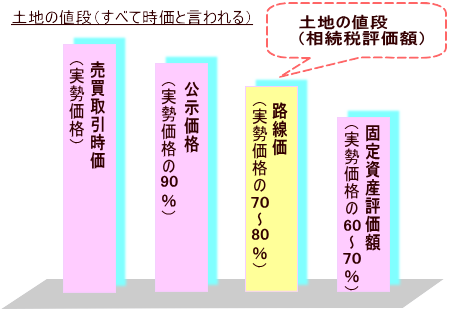概要
相続税法上、債務控除の対象となる被相続人の公租公課は、その死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなった被相続人の所得に対する所得税額等となります(相法14②、相令3)。
ただし、相続人の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなった延滞税、加算税などの附帯税は除かれます(相令3ただし書)。
債務控除の対象となる公租公課は、具体的には以下となります。
所得税
所得税は、暦年終了の時に納税義務が成立します(通法15②一)。また、年の中途において死亡した者に係るその年分の所得税(予定納税などー定の所得税及び源泉徴収による所得税を除く。)については、その死亡の時に納税義務が成立します(通令5①三)。
例えば、被相続人甲が、X2年6月15日に亡くなり相続が開始したとします。この場合、X1年分の所得税はX1年12月31日に納税義務が成立しています。
そのため、仮に期限内(X2年3月15日まで)に申告をしていなかった場合(期限後申告)でも、相続人甲の相続税の計算に当たり、X1年分の所得税は債務控除の対象とすることができます。
次に、X2年分の所得税は被相続人甲の死亡の時(X2年6月15日)に納税義務が成立しているため、被相続人甲の相続税の計算に当たり、X2年分の所得税は債務控除の対象とすることができます。X2年分の準確定申告が期限後申告となった場合でも同様です。
加算税
過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税は、法定申告期限の経過の時に納税義務が成立します(通法15②十四)。
例えば、被相続人甲が、X2年6月15日に亡くなり相続が開始したが、X1年分の所得税の申告が期限後申告となったとします。
この場合、X1年分の確定申告に係る無申告加算税は、法定申告期限であるX2年3月15日の経過の時に納税義務が成立していることとなるため、被相続人甲の相続税の計算に当たり、債務控除の対象とすることができます。
次に、居住者が年の中途において死亡した場合には、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に被相続人の所得税等の準確定申告書を提出しなければなりません(所法125①)。
また、相続人は、その被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継することとなります(通法5①)。
そのため、X2年分の準確定申告が期限後申告となった場合における無申告加算税は、当初申告に係る法定申告期限を徒過して提出されたことにより課されたものであり、その加算税を納付することとなったのは、法定申告期限までに準確定申告を行わなかった相続人の責めに帰すべき事由によるものとなります。
したがって、X2年分の準確定申告に係る無申告加算税は、相続人の責めに帰すべき事由により納付された加算税であるから、被相続人甲の相続税の計算に当たり、債務控除の対象とすることはできません。
延滞税
延滞税は、法定納期限の翌日から国税を完納する日までの期間の日数に応じて発生します(通法15①、③七、60②)。
例えば、被相続人甲が、X2年6月15日に亡くなり相続が開始したが、X1年分の所得税の申告が期限後申告となったとします。
この場合、X1年分の確定申告に係る延滞税のうち被相続人甲の相続開始までの期間に対応する延滞税は債務控除の対象とすることができます。
一方、相続開始後から国税を完納するまでの期間に対応する延滞税は、国税の納税義務を承継した相続人が納付を遅滞したことに伴うものであり、当該延滞税を納付することとなったのは、相続人の責めに帰すべき事由によります。
そのため、被相続人甲の相続が開始してから所得税を完納するまでの期間に対応する金額は、相続人の責めに帰すべき事由により納付された延滞税であるから、被相続人甲の相続税の計算に当たり、債務控除の対象とすることはできません。
次に、X2年分の準確定申告に係る延滞税は、当初申告に係る法定申告期限を徒過して提出されたことにより課されたものであり、当該延滞税を納付することとなったのは、法定申告期限までに準確定申告を行わなかった相続人の責めに帰すべき事由によるものです。
したがって、X2年分の準確定申告に係る延滞税は、相続人の責めに帰すべき事由により納付された延滞税であるから、被相続人甲の相続税の計算に当たり、債務控除の対象とすることはできません。
個人住民税および固定資産税
個人住民税および固定資産税のように地方税法に賦課期日の定めのある地方税については、その賦課期日において納税義務が確定しますので、その確定した金額が債務控除の対象になります。
個人住民税(地法39、318)および固定資産税(地法359)については、それぞれの賦課期日はその年度の初日の属する年の1月1日とされています。
その他
被相続人が取得した不動産に対する不動産取得税、被相続人の行っていた事業に対する事業税等は、相続開始前の事実に基づいて被相続人に課される地方税は被相続人の債務で相続開始の際、現に存する債務にあたりますので債務控除の対象となる公租公課になります。