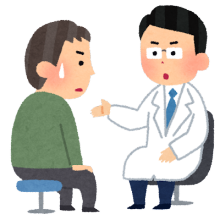概要
作家や漫画家の中には、印税収入(著作権使用料収入)を個人ではなく法人の収入としたいと思う方はいるでしょう。
また、印税収入を個人の収入としたとしても、自分が設立した法人(同族会社)に業務委託料を支払えないかと思う方はいるでしょう。
法人に著作権が帰属する場合
印税は、一般的に、著作物の販売部数に応じてその売上代金の一定割合を支払うという内容のものであり、その支払先は著作権者となります。
著作物は個人によって執筆されるので、著作権は本来個人に帰属します。しかし、特例で法人に著作権が帰属できる場合があります。
具体的には、以下の4つの要件を全て満たす場合に限って、特例により、法人に著作権(職務著作)が帰属するものとされています(著作権法15)。
(1)法人の発意に基づいて作成された著作物であること。
(2)法人の業務に従事する者が職務上作成された著作物であること。
(3)法人が自己の名義の下に公表する著作物であること。
(4)著作物作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定め(一定の場合には、従業員の著作物とする等)がないこと。
一般的に著作物の表紙や奥付などに著者名は表示されていますが、著者名が個人名義であるならば、「(3)法人が自己の名義の下に公表する著作物であること。」の要件を満たさないことになるので、法人の収入とすることはできません。
同族会社に支払った業務委託料
印税収入を個人の収入としたとしても、自分が設立した法人(同族会社)に業務委託料を支払えないかと思う方はいるでしょう。
この場合は、業務委託料の金額が業務量・内容に対して適正であるならば認められますが、税務署が適正でないと判断した場合は、否認をしてきます。
漫画家が、創作活動以外の業務を年額4,800万円の委託料で同族会社に委託し、その委託料を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入して確定申告しましたが、税務署が否認した事例(平成28年2月15日裁決・仙裁(所)平27第13号)があります。
ただし、この事例における国税不服審判所の判断では、納税者が勝っています。
著作権法
14条(著作者の推定)
著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
15条(職務上作成する著作物の著作者)
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
平成28年2月15日裁決(仙裁(所)平27第13号)(全部取消し)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 審査請求人Xは、「A」の名称で、平成20年に株式会社C社コミックス(以下「C社」という。)より、著作物名「D」の単行本を出版することで漫画家としデビューを果たし、その後も著作物名「E」及び「F」などの作品を漫画雑誌に連載し、単行本を出版するなどして、漫画の創作活動を業としている者である。
また、Xは、漫画作品の原稿料及び印税収入のほか、自身が創作した著作物に関する映像作品及び文房具などの商品化による著作権の二次的利用に関する契約を出版社と締結し、使用料収入を得ている。
② 合同会社B社は、平成21年7月14日に、漫画家、イラストデザイナーなどのマネジメント業務などを行うことを目的として設立された法人である。
B社は、X、Xの父である乙、Xの母である丙及びXの妹である丁(以下、Xを除き、乙及び丙と併せて「家族社員ら」という。)が業務執行社員の地位にある法人税法2条10号に規定する同族会社であり、代表社員として乙が選定されている。
③ Xは、B社との間で、平成22年9月28日及び平成23年9月30日において、それぞれ契約期間を平成22年10月1日から平成23年9月30日まで及び平成23年10月1日から平成24年9月30日までとする要旨次の内容の契約書を作成し、業務委託契約を締結した(以下、当該契約書面を「本件委託契約書」といい、XとB社との間で締結された業務委託契約を「本件委託契約」という。)。
なお、平成24年10月1日から平成25年12月31日までについては、新たな契約書を作成していない。
(イ) B社は、Xの制作業務を全面的に支援するために、下記事項の業務を誠意をもって行うものとする(第1項)。
A 制作及びその他の事務・経理管理業務一切の代行(第1号)
B 法令で要求される帳簿・書類の整備の一切(第2号)
C Xの契約事務の立会・書類の整備(第3号)
D Xの知的財産権の保護に関する研究と提案(第4号)
(ロ) Xは、B社に対して、業務委託料として月額400万円を支払うものとする。当該金額には、Xの活動の諸経費負担を含むものとする(第3項)。
(ハ) 業務委託料の改訂は、毎年の業績及び業務形態の変化に応じて、決算時に確認相談するものとする。また、第3項の諸経費負担額が、大きく増減したときは、その都度協議するものとする(第8項)。
④ Xは、本件各年分において、本件委託契約に基づく業務委託料として、月額400万円をB社に対して支払った上、年額4,800万円を本件各年分の事業所得の計算上、必要経費にそれぞれ算入した(以下、当該業務委託料を「本件委託料」という。)。
B社は、Xのみから業務を受託しており、本件各年分におけるB社の営業収入(売上高)は、上記の本件委託料だけである。
B社は、本件各年分において、X及び家族社員らに対し、役員給与を支払った。
⑤ Xが事業所得の金額の計算上、必要経費に算入したB社への業務委託料について、原処分庁が、Xの所得税の負担を不当に減少させるものであるとして所得税法157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》1項の規定を適用して更正処分等を行った。
原処分庁は、本件委託業務の適正委託料を算定するに当たり、Xと同じ漫画家で、同族関係にない法人に本件委託業務に類似する業務を一括で委託している個人事業者又はB社と業務受託の態様が類似する同業者で同族関係にない漫画家から本件委託業務に類似する業務を一括で受託している者を仙台国税局、東京国税局及び関東信越国税局管内から選定し、当該受託同業者が受け取った委託料の額とその原価相当額との割合などで比準させる方式での算定を試みたが、類似する受託同業者を把握することはできなかった。
そのため、次善の方策として、本件委託業務のうち、漫画家アシスタントの派遣、個人事業の経理・記帳事務、マネジメント業務及び製作補助業務に着目し、当該各業務は、Xの執筆業に付随する業務であり、事務処理的な業務であることから、個別受託同業者のうち、派遣先の依頼を受けて派遣元の人材の労働力を提供することを業としている人材派遣業が類似すると判断した。
具体的には、B社の役務の提供が、Xの自宅兼作業場が所在するK市を中心に行われていることから、K市に本店所在地がある人材派遣会社を電話帳からしっ皆的に抽出し、一般業務を取り扱う会社3社を比準会社として選定した(以下、当該人材派遣会社3社を併せて「本件各比準会社」という。)。
⑥ これに対し、Xが、類似性のない同業者を基に算定した業務委託料に基づいて当該規定を適用することは違法であるなどとして、同処分等の全部の取消しを求めた。
(2)本件の主な争点
本件委託料の支払を容認した場合には、Xの所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるか否かである。
(3)判断要旨(全部取消し)
① B社の委託業務の内容は、漫画家アシスタントの確保やXの個人事業の経理事務に加え、出版社との各種交渉業務、秘書業務及び制作補助業務など多岐にわたっている一方、Xにおいては、作品の創作業務に集中し、出版社との打合せについても編集に関する事項に限り対応しており、それ以外のほとんどの業務については、B社に委託していた。そうすると、本件委託契約は、ストーリーの考案やキャラクターの作画等といったXが漫画家本人として行う必要のある創作業務以外の一切の業務を包括的に委託したものであったことが認められる。
② 人材派遣業においては、派遣先で使用する器具類などの経費は負担しないのが一般的であるが、B社は、パソコン、複合機及び車両などに係る経費も負担していた。そうすると、B社は、人材派遣業とは明らに経費として負担するものが異なっていることからすれば、本件委託契約は人材派遣業の範ちゅうに留まらず、請負契約に類似する内容を含んだ契約であったことが認められる。
③ 以上によれば、本件各比準会社とB社の業務内容には個別条件の相違を超えた違いがあり、相当な類似性があるとは認められず、比準同業者としての基礎的要件に欠けるから、原処分庁が採用した各比準会社における人材派遣倍率などに基づく適正委託料の算定方法には、合理性が認められない。また、B社の役員乙のマネジメント業務の適正委託料に関しても、同人の役員給与額を算定の基礎とした点について、その根拠が不明確であるといわざるを得ず、合理性があるとはいえない。
④ 所得税法157条の適用に当たっては、株主等の所得税の負担を不当に減少させる結果となることが要件とされているところ、本件の場合、不当に減少させる結果となるかどうかは、合理的な方法で算定された適正委託料と本件委託料の金額を比較することにより判断することとなる。
⑤ 本件において原処分庁が主張する方法で抽出された各比準会社は、その業務の内容がB社の業務の内容と相当な類似性を備えているとは認められず、また、役員給与の額を基礎とした算定方法にも合理性が認められないから、本件委託料の支払がXの所得税の負担を不当に減少させる結果となるとする原処分庁の主張を採用することはできない。したがって、所得税法157条を適用した本件各更正処分は、法令の適用を誤ったものと認められるため、いずれもその全部を取り消すべきである。