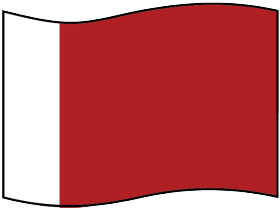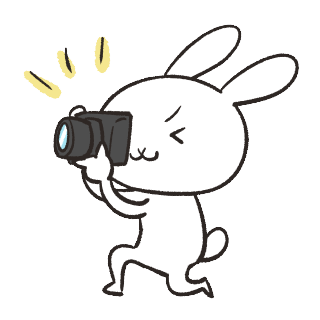概要
同一の種類に属する減価償却資産で「構造」が同じであっても、その「用途、細目」によって異なる耐用年数が定められている場合があります。
例えば、同じ鉄筋コンクリート造の建物であっても、耐用年数が事務所用は50年、住宅用は47年、店舗用は39年となっています(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表)。
なお、貸与している減価償却資産の耐用年数は、別表において貸付業用として特掲されているものを除き、原則として、貸与を受けている者の資産の用途等に応じて判定することとされています(耐通1-1-5)。
建物全体が事務所使用だけであるというように1つの用途に使用されている場合は、耐用年数に悩むことはないでしょう。問題は、複数の用途に使用されている場合です。
例えば、1つの建物で事務所用、住宅用、店舗用のように複数の用途に使用されている場合に、適用すべき耐用年数は何年になるのかということです。
この点につき、国税庁hpで公開されている耐用年数通達によれば、建物のように同一の減価償却資産について、その用途により異なる耐用年数が定められている場合において、複数の用途に共通して使用されているときは、その減価償却資産の用途については、その使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定するものとされています(耐通1-1-1)。
使用の状況等の総合勘案により合理的に判定するということですが、具体的にどう判定すればよいのかほとんどの方は悩むでしょう。
このように具体的にどう判定すればよいのかわからない場合は、裁判例を読みます。また、参考になる裁判例がない場合は、国税の内部通達(文章)を読みます。そうすれば、ある程度のことはわかります。
原則として、同一の減価償却資産について、その用途により異なる耐用年数が定められている場合において、減価償却資産が複数の用途に共通して使用されているときは、それぞれの用途ごとに個別に減価償却を行うのではなく、その建物の主たる使用状況等(専ら使用されている用途)が何であるかを把握し、1つの用途、つまり1つの耐用年数を適用することになります。
例えば、建物内の部屋が2つあり、部屋1が事務所用で400平方メートル、部屋2が店舗用で100平方メートルだったとします。
この場合、面積按分のようなことはせずに、建物については主たる使用用途である事務所用の耐用年数を適用することになります。
なお、ここにいう用途別とは、事務所用、店舗用、住宅用、工場用をそれぞれ独立の用途として、そのうち最も多い割合をみるのではなく、耐用年数省令の細目欄において同一区分に属するものとして表示されたグループ(償却限度額の計算上通算する同一耐用年数の資産グループ)ごとに一括して、いずれが大なる割合であるかをみるのが妥当とされています。
一括されたグループで大なる割合である1つの用途、つまり1つの耐用年数を適用することになります。
ただし、この例外(特例)として、複数の用途に使用するため、建物の一部について特別な内部造作その他の施設をしている場合、例えば、鉄筋コンクリート造の6階建のビルディングのうち1階から5階までを事務所に使用し、6階を劇場に使用するため6階について特別な内部造作をしている場合には、当該建物について減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「建物」の「細目」に掲げる2以上の用途ごとに区分して、その用途について定められている耐用年数をそれぞれ適用することができます(耐通1-2-4)。
耐用年数通達1-1-1では、複数の用途に共用されている場合は事業者が合理的に判定するとされていますが、事業者において採用している耐用年数がその使用状況等からみて、特に不合理であると認められない限り、その事業者の判定は尊重されるとされています。そのため、事業者がよっぽど不合理な判定をしない限り、裁判まで発展するような争いにはならないでしょう。
なお、適用する耐用年数の判定は各年ごとに行うのではなく、その判定した用途に係る耐用年数は、その判定の基礎となった事実が著しく異ならない限り、継続して適用する必要はあります。
耐用年数通達
1-1-1(2以上の用途に共用されている資産の耐用年数)
同一の減価償却資産について、その用途により異なる耐用年数が定められている場合において、減価償却資産が2以上の用途に共通して使用されているときは、その減価償却資産の用途については、その使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定するものとする。この場合、その判定した用途に係る耐用年数は、その判定の基礎となった事実が著しく異ならない限り、継続して適用する。
1-1-5(貸与資産の耐用年数)
貸与している減価償却資産の耐用年数は、別表において貸付業用として特掲されているものを除き、原則として、貸与を受けている者の資産の用途等に応じて判定する。
1-2-4(2以上の用途に使用される建物に適用する耐用年数の特例)
一の建物を2以上の用途に使用するため、当該建物の一部について特別な内部造作その他の施設をしている場合、例えば、鉄筋コンクリート造の6階建のビルディングのうち1階から5階までを事務所に使用し、6階を劇場に使用するため、6階について特別な内部造作をしている場合には、1-1-1にかかわらず、当該建物について別表第一の「建物」の「細目」に掲げる2以上の用途ごとに区分して、その用途について定められている耐用年数をそれぞれ適用することができる。ただし、鉄筋コンクリート造の事務所用ビルディングの地階等に附属して設けられている電気室、機械室、車庫又は駐車場等のようにその建物の機能を果たすに必要な補助的部分(専ら区分した用途に供されている部分を除く。)については、これを用途ごとに区分しないで、当該建物の主たる用途について定められている耐用年数を適用する。
内部文章
法事例1451 建物の耐用年数の適用区分
〔問〕 当社は、この度、3階建てのビルを建築した。1階が店舗、2階が倉庫、3階が事務所として使用し、各階の使用面積は同一である。このような場合、この建物を店舗、倉庫、事務所に3区分し、それぞれの耐用年数を適用することになるのか。
〔答〕 一の建物が耐用年数省令別表第一の「建物」に掲げる2以上の用途に共用されている耐用年数については、次のように取り扱われる。
同一の減価償却資産については、その用途により異なる耐用年数が定められている場合において、減価償却資産が2以上の用途に共通して使用されているときは、その減価償却資産の用途については、その使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定するものとする。この場合、その判定した用途に係る耐用年数は、その判定の基礎となつた事実が著しく異ならない限り、継続して適用する。〔耐通1-1-1〕
しかし、本問の場合のように、同一の建物の用途を耐用年数省令別表第一の「建物」の「細目」欄に掲げる用途の異なるごとに区分した場合において、各々の用途に使用される部分の使用割合が全く等しいという場合には、専ら使用されている用途の判断ができないので、各々の用途別の耐用年数のうち、平均的とみられる耐用年数をその建物の耐用年数とするのが妥当と思われる。
すなわち、3階建ての建物を各階ごとに店舗、倉庫、事務所としての用途につき定められている耐用年数のうち、平均的とみられる「店舗用」の耐用年数が合理的であると認められる。
〔法法31〕
法事例1459 2以上の用途に共用されている建物の耐用年数
〔問〕 当社所有の建物(鉄筋コンクリート造、地下2階地上6階建)は、地下2階がビル用電気、機械室、地下1階が駐車場、地上1階から5階までは貸事務所、6階が劇場となっている。この建物について適用する耐用年数はどのようにして算定するのか。
〔答〕 2以上の用途に共用されている資産の耐用年数については、その主たる用途を合理的に判定し、その判定した用途について定められている耐用年数を適用する。
1つの建物であっても、その用途は必ずしも一様ではなく、多用途に使用されている場合も多いことから、税務上では、一の減価償却資産が2以上の用途に共用して使用されている場合には、次のように取り扱われる。
その減価償却資産の使用目的、使用の状況等より勘案して、いずれの用途が主たる用途であるかを合理的に判定し、その判定した用途について定められている耐用年数により、償却限度額を計算すべきものとする。この場合、その判定した用途に係る耐用年数は、その判定の基礎となった事実が著しく異ならない限り、継続して適用する。〔耐通1-1-1〕
すなわち、2以上の用途に供されている資産については、その主たる用途について定められている耐用年数によることとし、その資産の帳簿価額を用途別にあん分して、それぞれの用途について定められている耐用年数を、それぞれ適用することは認められない。
しかし、一の建物を2以上の用途に使用するため、その建物について特別な内部造作その他の施設をしている場合、例えば、鉄筋コンクリート造の6階建てのビルデイングのうち1階から5階までを事務所に使用し、6階を劇場に使用するため、6階について特別な内部造作をしている場合には、耐用年数取扱通達1-1-1にかかわらず、当該建物について耐用年数省令別表第一の「建物」の「細目」に掲げる2以上の用途に区分して、その用途について定められている耐用年数をそれぞれ適用することができる。ただし、鉄筋コンクリート造の事務所用ビルディングの地階等に附属して設けられている電気室、機械室、車庫又は駐車場等のように、その建物の機能を果たすに必要な補助的部分(専ら区分した用途に供されている部分を除く。)については、これを用途ごとに区分しないで、当該建物の主たる用途について定められている耐用年数を適用する。〔耐通1-2-4〕
すなわち、本問の場合において、その建物のうち6階の部分について特別な内部造作等しているときには「劇場用」の耐用年数を適用することができる。
法事例1474 結婚式場用の建物等の耐用年数
〔問〕 結婚式場用の建物を新築したが、次のものの耐用年数は何年になるか。
1 鉄筋コンクリート造の建物
(1) 1階は駐車場
(2) 2~3階は披露宴会場
(3) 4階は式場、控室等
2 式場にある祭壇(木造)等の造作物
〔答〕 まず、建物については、同一の減価償却資産について、その用途により異なる耐用年数が定められている場合において、減価償却資産が2以上の用途に共通して使用されているときは、その減価償却資産の用途については、その使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定するものとする。この場合、その判定した用途に係る耐用年数は、その判定の基礎となった事実が著しく異ならない限り、継続して適用することと規定されている。〔耐通1-1-1〕
したがって、本問の建物は、使用目的、使用状況からみると、式場、披露宴会場等に主として使用されるもののようであるから、耐用年数省令別表第一の「建物」の「鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」の「飲食店用・貸席用」の「その他のもの」の耐用年数41年を適用することになる。この場合にその建物の木造内装部分が3割を超えるものであるときは、その耐用年数は34年を適用することになる。
次に、式場にある祭壇等の造作物については、建物に固着して建物の一部を構成しているものについては建物の取得価額に算入することになるが、それ以外のものについては「器具及び備品」として「11 前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」の耐用年数5年を適用する。
〔法法31〕
法事例1485 バナナ熟成室の耐用年数
〔問〕 当社の建物(鉄筋コンクリート造)は、地下室をバナナ熟成室、1階は店舖及び事務所、2階は住宅として使用している。この建物の耐用年数はどれを適用するのか。
概要
〔答〕 1棟の建物について、その用途により異なる耐用年数が定められている場合において、建物が2以上の用途に共用して使用されているときは、その建物の用途についてはその使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定する。〔耐通1-1-1〕
したがって、原則として、用途別に使用する面積の割合とか使用程度の割合等を総合勘案して、使用割合の最も多いとみられる用途について定められている耐用年数を適用することになる。
ここにいう用途別とは、事務所用、店舗用、住宅用、工場用をそれぞれ独立の用途として、そのうち最も多い割合をみるのではなく、耐用年数省令の細目欄において同一区分に属するものとして表示されたグループ(償却限度額の計算上通算する同一耐用年数の資産グループ)ごとに一括して、いずれが大なる割合であるかをみるのが妥当と認められる。
すなわち、本問の場合、住宅の用に供される部分が使用割合が最も大とみられ、原則としてこの建物は、耐用年数47年を適用することになる。
しかし、バナナの熟成室のように、蒸気の影響が一の建物のうち特定の階等について直接全面的である場合には、本来の耐用年数によることは適当でない。したがって、地下室部分の取得価額を区分して耐用年数を適用することになる。〔耐通2-1-19〕
その鉄筋コンクリート造のバナナの熟成用むろについては、耐用年数省令別表第一の「建物」の「鉄筋コンクリート造」に掲げる「著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの」に該当するものとして取り扱われている。〔耐通2-1-21〕
したがって、これについて定められている耐用年数31年を適用する。
なお、この建物の取得価額の区分は、単に面積あん分によるものではなく、それぞれの使用目的によって構造、内部造作も異なることから、これらの点を考慮して、工事見積書等の基礎資料から適正な価額相当額を算出することが合理的である。
〔法法31〕
法事例1550 2以上の用途に使用される船舶の耐用年数
〔問〕 当社は、総トン数5万トンの船舶を建造した。これは、鉱石又は油のどちらでも運搬できるような構造のもので、完成後は、荷主の要求に応じて随時鉱石又は油を運搬する予定である。耐用年数の適用はどのようにしたらよいか。
〔答〕 その船舶の主たる用途が鉱石運搬船であるか、油槽船であるかを目的、運航計画その他の具体的な資料によって判定のうえ、いずれか一の耐用年数を適用する。
鉱石運搬船については、耐用年数省令別表第一の「船舶」の「船舶法第4条から第19条までの適用を受ける鋼船」の「その他のもの」の15年の耐用年数になり、油槽船については、「船舶」の「船舶法第4条から第19条までの適用を受ける鋼船」の「油槽船」の13年の耐用年数となる。
耐用年数通達1-1-1には、次のとおり規定されている。
同一の減価償却資産について、その用途により異なる耐用年数が定められている場合において、減価償却資産が2以上の用途に共通して使用されているときは、その減価償却資産の用途については、その使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定するものとする。この場合、その判定した用途に係る耐用年数は、その判定の基礎となった事実が著しく異ならない限り、継続して適用する。
したがって、合理的に判断することになるが、各企業において採用している耐用年数がその利用状況等からみて、特に不合理であると認められない限り、その企業の判定を尊重していくという趣旨に解することが相当である。
〔法法31〕
法事例1653 2以上の用途に共用されているボイラー設備の耐用年数
〔問〕 当社の工場において、製造設備を異にする設備に共通して蒸気等を供給するボイラー設備を有しているが、このボイラー設備の耐用年数の適用は、どのように判定したらよいか。
〔答〕 2以上の用途に共用されている資産の耐用年数の取扱いは、次のように規定されている。
同一の減価償却資産について、その用途により異なる耐用年数が定められている場合において、減価償却資産が2以上の用途に共通して使用されているときは、その減価償却資産の用途については、その使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定するものとする。この場合、その判定した用途に係る耐用年数は、その判定の基礎となった事実が著しく異ならない限り、継続して適用する。〔耐通1-1-1〕
したがって、ボイラー設備については、各製造設備の蒸気の使用量等から、いずれの製造設備に専ら使用されているかを合理的に判定し、その判定された製造設備に含めたところにより、その製造設備の耐用年数を適用する。