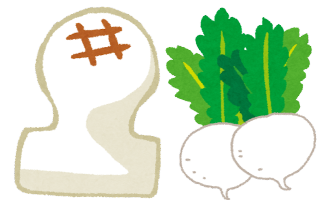概要
今年の上場株式譲渡損は適切な申告をすることによって、翌年以降3年間に渡り、上場株式等の譲渡益から控除することができます。
例えば、以下の上場株式譲渡損益だったとします。
X1年分 -300万円
X2年分 200万円
この場合、適切な申告をすれば、X1年分の-300万円を繰越し、X2年分の200万円と相殺(通算)できます。また、相殺した後のX1年分の-100万円はさらに繰り越され、X3年分の譲渡益と相殺することができます。
一方、今年の上場株式譲渡損と昨年の上場株式譲渡益を相殺することはできません。
例えば、以下の上場株式譲渡損益だったとします。
X0年分 100万円
X1年分 -300万円
この場合、X1年分の-300万円を繰り戻し、X0年分の100万円と相殺し、X0年分に納めた所得税等の還付請求をするということはできません。あくまでも、この場合も、適切な申告をすることによって、X1年分の-300万円を繰越すということになります。
これは、上場株式譲渡損益だけのことではなく、FX取引等の先物取引の損益でも同じ取り扱いとなります。
先物取引により生じた本年中の損失を前年中に生じた利益と通算することはできないとされた事例-令和6年5月8日裁決(関裁(所)令5第41号)(棄却)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 審査請求人Xは、令和2年3月から、金融商品取引業者Aを受託者として、株式会社東京金融取引所が「くりっく株365」の名称で提供する取引所株価指数証拠金取引(以下「本件先物取引」という。)を開始した。
本件先物取引は、租税特別措置法41条の14第1項2号に規定する金融商品先物取引等に該当する。
② Xは、本件先物取引について、令和2年3月2日から同年12月31日までの間に624回の差金等決済を行い、利益(先物取引に係る雑所得)が生じていた。
③ Xは、令和2年分の所得税等について、法定申告期限までに申告したが、上記②の先物取引に係る雑所得については申告しなかった。
④ 原処分庁は、上記③の申告に対し、先物取引に係る雑所得の金額が申告されていないなどとして、令和4年12月26日付で、更正処分等(以下「本件更正処分等」という。)をした。
⑤ Xは、これらの処分を不服として、全部の取り消しを求めた。
なお、Xの令和3年中に行った差金等決済の取引では、損失が生じている。
(2)本件の主な争点
令和2年中に行われた差金等決済により生じた利益と令和3年中に行われた差金等決済により生じた損失を通算できるか否かである。
(3)裁決要旨(棄却)
① 所得税の納税義務は、暦年の終了の時に成立し、その年分の雑所得の金額は各規定に基づいて計算することになるから、その年中の先物取引に係る雑所得の金額とは、当該年中(一暦年)に行われた差金等決済により生じた雑所得の金額を指すというべきである。そうすると、Xの令和2年分の先物取引に係る雑所得の金額は、令和2年1月1日から同年12月31日までに行われた差金等決済により生じた雑所得の金額である。
② この点につき、Xは、本件先物取引は令和3年まで継続して行われていたから、本件先物取引に係る雑所得の金額は、令和2年中に行われた差金等決済により生じた利益と令和3年中に行われた差金等決済により生じた損失を通算して計算すべきである旨主張する。
しかしながら、先物取引により生じた雑所得の申告に当たり、申告の対象期間である年中に生じた利益とその翌年に生じた損失を通算できる旨の法令の規定はないことから、仮に令和3年中に行われた差金等決済により損失が生じていたとしても、当該損失を令和2年中に行われた差金等決済により生じた利益と通算することはできない。
したがって、Xの主張には理由がない。
③ また、Xは、令和3年まで継続する本件先物取引を一体のものとしてみると、損失が生じており、これに係る雑所得の金額は〇円であるから、そのような取引に課税する原処分及びその基となる法令の規定は、Xの財産権を侵害し、違憲である旨主張する。
しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分及びその処分の基となった法令自体の合憲又は違憲を判断することは、その権限に属さないことであるので、この点に関するXの主張については当審判所の審理の限りではない。
④ 本件更正処分等は適法である。