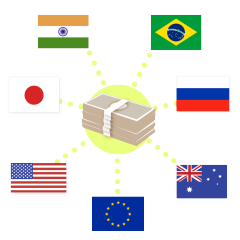概要
購入してすぐ売却等したような場合は、個別対応により算出しますので、売却価額から売却した当該株式の取得価額を控除した金額が売却損益となります。
ただし、同じ銘柄の株式等を買増しした(同じ銘柄の株式等を2回以上にわたって取得した)後、その一部を売却したような場合の取得価額の計算は、「総平均法に準ずる方法」又は「総平均法」により計算します。
その売却損益が「譲渡所得」、「雑所得」、「事業所得」のいずれに該当するかによって異なりますが、一般的な上場株式等の売却は「譲渡所得」に該当します。
株式等に係る「譲渡所得」又は株式等に係る「雑所得」に該当する場合の取得費は「総平均法に準ずる方法」により計算し、株式等に係る「事業所得」に該当する場合は「総平均法」により計算します(所法48①③、所令105①、108①、118①、措令25の8⑧、25の9⑪)。
なお、計算された1単位当たりの金額に1円未満の端数(公社債は額面100円当たりの価額とした場合の小数点以下2位未満の端数)があるときは、その端数を切り上げます(措通37の10・37の11共-14)。
「総平均法に準ずる方法」と「総平均法」
「総平均法に準ずる方法」とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分し、その種類等の同じものについて、その株式等を最初に取得した時(取得後において既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の時)から、その「譲渡」の時までの期間を基礎として、総平均により1単位当たりの金額を計算する方法をいいます(所令118①)。
「移動平均法」 と似ている方法ですが、「総平均法に準ずる方法」が、「譲渡」のつど取得価額を算出するのに対し、「移動平均法」は「取得」のつど保有分の株式の取得価額を算出する方法となっています。「総平均法に準ずる方法」の1単位当たりの金額の算出方法は以下となっています。
1単位当たりの金額=(株式等を最初に取得した時の株式等の取得価額の総額+株式等を最初に取得した後から株式等の譲渡の時までに取得した株式等の取得価額の総額)/(株式等を最初に取得した時の株式等の総数+株式等を最初に取得した後から株式等の譲渡の時までに取得した株式等の総数)
既に株式等を譲渡している場合の「総平均法に準ずる方法」の1単位当たりの金額の算出方法は以下となっています。
1単位当たりの金額=(直前の譲渡の時の株式等の取得価額の総額+直前の譲渡の後から株式等の譲渡の時までに取得した株式等の取得価額の総額)/(直前の譲渡の時の株式等の総数+直前の譲渡の後から株式等の譲渡の時までに取得した株式等の総数)
一方、「総平均法」とは、株式等をその種類および銘柄の異なるごとに区分し、その種類等の同じものについて、その年の1月1日に所有していたものとその年中に取得したものとの取得価額の総額をこれら株式等の総数で除して求める方法をいいます(所令105①一)。
(計算例)
A社株式の取得と譲渡があった場合の、③「年中譲渡30株」の譲渡原価の計算は以下の通りです。
① 前年からの繰越 100株( 前年から繰り越された取得価額総額 10,000円 )
② 年中取得 60株( 取得価額 5,200円)
③ 年中譲渡 30株
④ 年中取得 40株( 取得価額 3,200円)
( 総平均法に準ずる方法 )
10,000円 ①+ 5,200円 ② / 100株 ①+ 60株 ② =95円 譲渡原価 95円×30株③=2,850円
( 総平均法 )
10,000円 ①+ 5,200円 ②+ 3,200円 ④ / 100株 ①+ 60株 ② + 40株 ④ =92円 譲渡原価 92円×30株③=2,760円
「総平均法に準ずる方法」が採用された理由
東京地裁令和4年2月24日判決(令和2年(行ウ)377号)では、以下のように判示しています。
「所得税法48条3項の委任を受けた所得税法施行令118条1項は、(省略)、譲渡所得の計算上取得費に算入する金額に関し、2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券の取得費については、総平均法に準ずる方法を用いて算出した1単位当たりの金額により計算をすることとしている。これは、総平均法が棚卸資産の評価方法として企業会計処理上の合理性が認められることを踏まえ、同一銘柄の有価証券が代替性を有し、各有価証券の取得価額が異なるとしても、一株ごとの株主の当該株式会社に対する社員としての地位は同一であることから、その価値を等価とみて単価を平均化することが合理的であること、また、これによって取得価額の変動を利用した利益操作の可能性を排除することができることから、取得費の算出方法として総平均法に準ずる方法を採用したものであると解される。」
同一銘柄の株式を一般口座と特定口座で保有していた場合、それぞれの口座ごとに取得価額を計算する
特定口座内保管上場株式等は、特定口座ごとに他の口座の所得と区分して、その特定口座に係る株式等に係る譲渡所得等の金額を計算します(措法37の11の3①、措令25の10の2①)。
つまり、個々の特定口座ごとに取得価額の計算を行います。また、特定口座外(一般口座等)で同一銘柄の上場株式等を所有していても、別の銘柄として取得価額を計算します(措令25の10の2①二、令和2年4月17日裁決・名裁(所)令元第25号、東京地裁令和4年2月24日判決・税資272号(順号13674)、東京高裁令和4年9月1日判決・税資272号(順号13750))。
例えば、ある人がA証券会社特定口座に甲銘柄100株、B証券会社特定口座に甲銘柄100株、C証券会社一般口座に甲銘柄100株を保有していたとします。
この場合、甲銘柄は合計300株保有していますが、それぞれの口座ごとに取得価額を計算します。
また、ある人がA証券会社特定口座に甲銘柄100株、B証券会社一般口座に甲銘柄100株、C証券会社一般口座に甲銘柄100株を保有していたとします。
この場合、A証券会社特定口座に甲銘柄100株については、その口座内で取得価額を計算します。B証券会社一般口座とC証券会社一般口座の甲銘柄については、合わせた200株の平均値で取得価額を計算します。
特定口座内保管上場株式を一般口座に払い出した場合の取得価額
特定口座内保管上場株式等については、金融商品取引業者等が、居住者等に代わって一元的に取得費等を計算することが予定され、既に開設された特定口座に新たに受け入れることのできる上場株式等は、原則としてその特定口座において行われた取引により取得した上場株式等に限られるものとされていますが、特定口座制度導入当初は、居住者等が特定口座外で保管している株式を特定口座へ受け入れることができるとする経過措置が定められていました。
しかし、同経過措置は、平成21年5月31日をもって廃止されました(平成17年政令103号附則11条1項、2項参照)。
他方、特定口座内保管上場株式等を特定口座外へ払い出すことは現在も可能であるところ、上記払出しがされた場合、その払出し後の一般口座内の上場株式等に係る譲渡所得の計算上、その払出しをした上場株式等は、その払出しの時に特定口座内保管上場株式等の譲渡があったものとした場合に、総平均法に準ずる方法により取得費の額として計算される金額に相当する金額により取得されたものと扱われます(措令25の10の2㉖一、⑫二イ、所令118、105①一)。
すなわち、特定口座内保管上場株式等を一般口座に払い出した場合には、その払出しの際に特定口座から譲渡されたと仮定した場合に算出される取得費の額が、その払出しがされた上場株式等の取得費として、一般口座に引き継がれることとなります。
そして、金融商品取引業者等は、特定口座から一般口座への払出しがされた場合、その特定口座を開設している居住者等に対し、その払出しがされた上場株式等について、上記の計算により算出された取得費の額等を通知するものとされています(措法37の11の3③二、措令25の10の2⑩一)。
同一銘柄の株式を同一日に複数回売買した場合の取得価額の計算方法
同一銘柄の株式を同一日内に複数回売買し、同じ日に売却した場合の取得価額の計算方法は、特定口座か、それ以外(一般口座等)で違ってきます。
特定口座の場合、同一銘柄の株式を同一日内に複数回売買し、同じ日に売却した場合は、まず同日中の全ての取得があったものとして、その後に売却があったものとして計算します(措令25の10の2①三)。
一方、特定口座以外(一般口座等)の場合、時間の経過順に計算します。
ですから、同一銘柄の株式を同一日内に買い、売り、買い、というようなことをすると、特定口座か、それ以外(一般口座等)で売却分の取得価額の金額が変わってきてしまうということです。
(計算例)
A社株式の取得と譲渡が同一日内にあった場合の、計算は以下の通りです。
① 前日からの繰越 10,000株(取得単価 600円 )
② 当日譲渡(③より先) 10,000株(売却単価 1,000円)
③ 当日取得 10,000株(取得単価 1,000円)
( 特定口座 )
譲渡原価
10,000株×600円 ①+ 10,000株×1,000円 ③ / 10,000株 ①+ 10,000株 ③ =800円
800円×10,000株②=8,000,000円
譲渡益
10,000株×1,000円② - 譲渡原価8,000,000円=2,000,000円
残高
10,000株(取得単価 800円)=8,000,000円
( 特定口座以外 )
譲渡益
10,000株×1,000円② - 10,000株×600円 ① = 4,000,000円
残高
10,000株(取得単価 1,000円)③=10,000,000円
同一銘柄の株式を一般口座と特定口座で保有していた場合、それぞれの口座ごとに取得価額を計算すべきとされた東京地裁令和4年2月24日判決(税資272号(順号13674))
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 原告Xは、保有するA株式85万株のうち、平成25年6月11日に72万5000株を総額21億3585万円で、同月12日に1万2000株を総額3403万円余で、それぞれ譲渡した。
Xは、上記平成25年6月11日の譲渡の直前において、A株式の全て(85万株)をB証券会社の一般口座において保有していたところ、同株式について、総平均法に準ずる方法により算出した1株当たりの取得価額は59円であった。
② Xは、平成25年6月12日、B証券会社の特定口座において、A株式72万5000株を総額21億3827万7946円で取得した。
③ Xは、平成25年6月13日から同月24日までの間に、一般口座において保有していたA株式の残り11万3000株を、総額3億2052万円余で順次譲渡した(以下、これらA株式11万3000株を併せて「本件譲渡株式」という。)。
④ Xは、平成26年3月、平成25年分の所得税等の確定申告書を法定申告期限内に提出した。同申告書において、Xは、平成25年分の所得税等に係る株式等の譲渡所得の金額の計算上、取得費に算入する金額を、平成25年6月11日及び同月12日に譲渡したA株式〔前記①〕については概算取得費とし、本件譲渡株式〔前記③〕については、特定口座で取得したA株式の取得費〔前記②〕を含めて総平均法に準ずる方法により算出した。
申告書におけるXが算出した本件譲渡株式の取得費の計算方法は以下のとおりであった。
| (ア) 1単位当たりの金額の計算 (59円/株×11万3000株+21億3827万7946円)÷(11万3000株+72万5000株) =2560円/株(1円未満の端数は切り上げ) (イ) 本件譲渡株式の取得費の計算 2560円/株×11万3000株=2億8928万円 |
つまり、Xは、A株式を特定口座と特定口座以外の口座(一般口座)の双方において保有していたところ、平成25年6月13日から24日までの間に、そのうち一般口座において保有する株式のみを譲渡したが、その譲渡における取得費とした金額は、一般口座において保有するA株式の取得価額だけでなく、特定口座において保有するA株式の取得価額も含めて総平均法に準ずる方法により算出した額で申告した。
⑤ 処分行政庁が、平成31年3月、Xに対し、本件譲渡株式の譲渡所得の金額の計算においては、租税特別措置法(以下「措置法」という。)37条の11の3第1項及び措置法施行令25条の10の2第1項2号の規定により、特定口座内で保管する株式と当該特定口座以外で保管する株式が同一銘柄の株式であったとしても、それぞれの銘柄が異なるものとして区分して計算することとなるから、一般口座において譲渡した本件株式に係る1単位当たりの取得単価を算定するに当たって特定口座内のA株式の取得費を含めるのは相当ではないとして、平成25年分の所得税等に係る更正処分等をしたため、Xは、その取消しを求めた。 処分行政庁における本件譲渡株式の取得費の具体的な計算方法は以下のとおりであった。
| (ア) 1単位当たりの金額 59円/株 (イ) 本件譲渡株式の取得費の計算 59円/株×11万3000株=666万7000円 |
(2)本件の主な争点
本件の争点は、本件譲渡株式の取得費の計算方法及びその金額であり、具体的には、措置法37条の11の3の規定は、特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合だけでなく、一般口座に保有する同一銘柄の上場株式等を譲渡した場合にも適用があり、それぞれの銘柄が異なるものとして取得費の計算を行うべきである(被告国主張)か、特定口座内保管上場株式等が譲渡された場合にのみ適用され、一般口座内に保管されている上場株式等が譲渡された場合には適用がない(X主張)かである。
(3)判決要旨(棄却)
① 措置法及び措置法施行令は、個人投資家である居住者等の申告事務の負担を軽減することを目的として、特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る区分計算を定めた(措法37の11の3①、措令25の10の2①)。そして、既に開設された特定口座に新たに受け入れることのできる上場株式等は、原則としてその特定口座において行われた取引により取得した上場株式等に限られるものとされ、居住者等が特定口座外で保管している株式を特定口座へ受け入れることができるとする経過措置は廃止された。また、特定口座内保管上場株式等が一般口座に払い出された場合において一般口座に引き継がれる取得費の計算方法を定め、上記計算方法に従って算出された当該払出しに係る上場株式等の取得費の額を、居住者等に通知するものとしている。
② 以上に判示した各規定の内容や経過措置の廃止等に照らせば、措置法及び措置法施行令は、特定口座内保管上場株式等と一般口座において保管されている上場株式等とを、譲渡、払出しの各処理において区分して取り扱うことを前提としているものと解される。そうすると、特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合だけでなく、一般口座内に保管されている同一銘柄の上場株式等を譲渡した場合についても、それぞれの銘柄が異なるものとして取得費の計算をする国主張に係る計算方法が、上記の各口座に保管された株式を区分して取り扱うという前提に沿うものといえる。
③ 他方、X主張に係る計算方法は、特定口座内保管上場株式等と一般口座において保管されている上場株式等とを譲渡、払出しの各処理において区分して取り扱うという趣旨、内容と整合的であるということはできない。
④ 以上に判示したとおり、特定口座制度が創設された趣旨等、特定口座の受入れと払出しの規制等、取得費の算出方法として総平均法に準ずる方法が採用された趣旨等を総合考慮すると、一般口座内に保管されている上場株式等を譲渡した場合に所得税法48条3項及び所得税法施行令118条1項を適用するに当たり、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等については、その銘柄が異なるものとして、その取得価額は、一般口座内に保管されている上場株式等の取得費の計算において考慮されないものと解するのが相当である。
したがって、本件譲渡株式の取得費は、特定口座において取得したA株式の取得費を含めずに総平均法に準ずる方法により算出した金額である666万7000円(=59円/株×11万3000株)となる。
その後
東京高裁令和4年9月1日判決・税資272号(順号13750)は原判決を引用し、Xの請求は理由がないと棄却した。
Xは上告受理申立てをしたが、最高裁(第三小法廷)令和5年2月8日決定において不受理された。