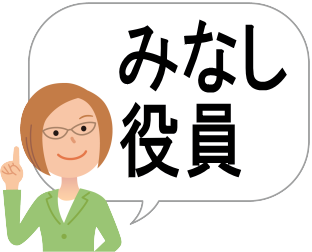概要
銀行からの借入をするため等により、中小企業の中には事実を仮装して経理した、いわゆる粉飾決算に基づき所得金額を過大に申告する法人もあるでしょう。
中小企業が粉飾決算によって所得金額を過大に申告した場合は、本来の所得金額よりも多く法人税を納めていることになります。
このような過大申告が行われた場合には、法人がその後の事業年度の確定した決算で、粉飾事項について「修正の経理」をし、その決算に基づく確定申告書を提出するまでの間は、たとえ税務調査によって過大申告であることが判明しても、所轄税務署長は減額の更正をしないことができます(法法129 ①)。
「修正経理」とは、確定決算で仮装に係る部分を修正した事実を明示することとなりますが、具体的には、中小企業の場合は「前期損益修正損」の計上を行うことになるでしょう。
なお、「前期損益修正損」を計上して修正の事実を明示していない場合、例えば、帳簿上、粉飾決算時の仕訳の反対仕訳をしているような場合は「修正の経理」に当たりません(大阪地裁平成元年6月29日判決・行裁例集40巻6号778頁)。
また、このような過大申告について減額更正となり還付金が生じる場合でも、その還付金のうち粉飾決算に関連する税額の部分は直ちに還付されません。
原則として、その減額更正の日の属する事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の法人税相当額だけ還付され、残額は、更正の日の属する事業年度以降5年間に納付する法人税額から順次控除されることとされています(法法70、135①)。なお、5年間で控除されなかった場合は、還付されます(法法135③)。
この規定の趣旨について、大阪地裁平成元年6月29日判決(行裁例集40巻6号778頁)では、以下のように判示しています。
「自ら、粉飾決算をして意識的に多く納めた税金を、還付加算金を付して一時に還付するということは、数年間の税金を一時に還付するという点において財政を不安定にするおそれがあるのみならず、申告納税制度の本旨からみても好ましくないこと、また、粉飾決算をなくして真実の経理公開を確保しようという要請とも相容れないものであることから、粉飾決算をした法人が自ら仮装経理状態を是正するまでは減額更正を留保し、また、還付についても通常の場合より不利に扱うことにするとともに、その是正方法も一定の厳格な方法によつて既往事業年度の経理を修正した事実を明確に表示することを義務づけ、その負担により、財政の安定をはかると同時に粉飾決算を未然に防止することをも目的とするものと解される。」
なお、更正は原則として法定申告期限から5年以内(通法70①一)に限りできるものであるため、その期限を過ぎると所轄税務署長は減額更正することができません(ただし、純損失等の金額についての更正は10年、通法70②)。
そのため、法人が修正の経理をし申告をしたからといっても、実際に、所轄税務署長が減額更正をするまでにはある程度の時間がかかりますので期限切れで減額更正されなかったとという事例もあります。
このような粉飾決算に対する減額更正について厳しい規制が設けられたのは、昭和40年の山陽特殊製鋼倒産事件(上場していた山陽特殊製鋼が倒産した際に、同社経営陣が粉飾決算していたことが明らかになった経済事犯)に代表される粉飾決算が社会問題化したことに対応したからです。
仕訳
(Q)当社は中小企業ですが、前期に粉飾決算をして、以下の仕訳をしました。当期において、「修正の経理」をする場合、どのような仕訳をする必要がありますか?
売掛金 1100万円 売上 1100万円
(A)以下となります。
前期損益修正損 1100万円 売掛金 1100万円
なお、以下のような粉飾決算時の仕訳の反対仕訳では「修正の経理」となりません。
売上 1100万円 売掛金 1100万円
減額更正ができる期間が過ぎていたため、一部納税額が減額更正されなかった事例-新潟地裁昭和62年6月25日判決(税資158号706頁)、東京高裁昭和63年9月28日判決(税資165号903頁)、最高裁平成元年4月13日第一小法廷判決(税資170号14頁)(棄却)(確定)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① X(原告、控訴人、上告人)は、木材等の卸販売を業とする会社であるが、昭和54年7月期の事業年度(以下「本件事業年度」という。)の法人税について、所得金額7347万円余との確定申告をしたが、整理特別損失9億4298万円余を計上していた。
整理特別損失9億4298万円余のうち9億3777万円余は、過去の事業年度において事実を仮装して経理したところに基づく受取手形、売掛金、たな卸資産等の過大計上及び支払手形、買掛金、預り金等を過少計上していた金額を当期において修正の経理をしたというものであつた。
② これに対し、所轄税務署長Yは、仮装経理による所得金額の過大申告分9億3777万円余というものは、あくまでも当該事業年度分限りのものであつて、本件事業年度分の損金としては認められないとした上で、次の過年度の減額更正に伴う繰越欠損金8億69万円余からXが本件事業年度に損金算入した繰越欠損金5718万円余を超える7億4350万円余を損金算入し、本件事業年度の所得金額を2億5819万円余とする各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)をした。
(イ) 昭和51年7月期欠損 1億2305万円余
(2) 昭和52年7月期欠損 3億7340万円余
(3) 昭和53年7月期欠損 2億8423万円余
(4) 合 計欠損 8億69万円余
ところで、国税通則法70条2項(当時)の規定によれば、その更正に係る国税の法定申告期限から5年を経過したときには減額更正はできないのであり、Xの場合には昭和49年7月期については昭和54年9月30日、また昭和50年7月期については昭和55年9月30日を経過して減額更正はできないところ、Yが昭和54年7月期の整理特別損失の内容を具体的に調査確認し本件各更正処分を行つたのは、昭和56年7月7日であつてすでに減額更正処分が可能な期間を経過しており、Yは、昭和49年7月期及び昭和50年7月期については減額更正処分を行つていない。
③ Xは、本件各更正処分に対し、昭和49年7月期の欠損8980万円余及び昭和50年7月期の欠損5299万円余の合計1億4280万円余の欠損についても減額更正を行うべきであるとして、本訴を提起した。
(2)本件の主な争点
昭和49年7月期及び昭和50年7月期の欠損について、減額更正処分を行うべきか否かである。
(3)一審判決要旨(棄却)(控訴)
① Xは、青色申告の繰越欠損金控除の規定の意義を考慮すれば、当該控除年度の更正自体が国税通則法70条2項(当時)に抵触しない限り前5年度分は更正できることが当然の前提になつていると主張する。
しかし、本件の場合のように過去の事業年度について減額更正処分を行うことによつて当該控除年度の繰越欠損金が増額されるという場合には、過去の事業年度の減額更正が国税通則法70条2項の規定に抵触しない場合に初めて当該控除年度の繰越欠損金の額を更正できるのであり、Xの主張は独自の見解であり、採りえない。
② 次に、Xは、国税通則法70条2項が規定する5年の期間内に、納税者が減額更正のための調査に着手した場合若しくは納税者が税務署長に対し減額更正を求める意思を明らかにして具体的に減額更正のための調査活動を開始した場合または税務署長の了解ないし要請に基づいて納税者が減額更正のための具体的な調査活動を開始した場合には、同項の期間制限に触れないと解すべきであると主張する。
そこで、国税通則法70条2項2号の立法趣旨を検討するに、同号は租税法律関係の早期安定をはかるために減額更正を5年間の除斥期間に服するものとしたものであると解される。このように同号は除斥期間を定めたものであるから、消滅時効の場合とは異なり中断事由を認める余地はなく、Xが主張するような事由がある場合には一般的に同号の期間制限には触れないと解することはできない。
③ 次に、本件において右除斥期間の規定の適用が許されないと解すべき特別の事情が存するか否かを検討するに、次の事実を認めることができる。
(イ) Xは、本件事業年度の確定申告に際して、申告書の付属書類として資産整理の内訳及び明細説明と題する書面を提出して過年度において発生した欠損金についての説明を行つているが、そこには「過年度(昭和50年~53年の4期)に及ぶ膨大な書類のため簡単に結論に達することは不可能で、当期末までに作業は終了できなかつた。しかしながら、各期毎に明確に経過を判明できなかつたとしても、総体として資産が失われ損失が発生したことは明らかであるので、欠損処分にするとともに、この件に関連する損益を集合して決算表示することになつた。なお目下更に調査は継続されているので、遠からず各期毎にその内容が明らかにされるはずである。」と記載されているにすぎず、過年度において発生した欠損金についての右書面における説明は極めて概略的なものである。
(ロ) 昭和54年11月頃、X代表者のK、顧問税理士ZがYを訪れ、過年度においてXが粉飾していた概略の数字及び調査に日時がかかることを報告した。
(ハ) 昭和55年5月26日、KとZはYへ行き、過去5年分についての解明は大体できているが、最後の2年間については不明な点もあるので解明はできていないとの報告を行つた。
(ニ) 昭和55年9月20日、KとZはYへ行き、過年度に生じた欠損金について各年度ごとに具体的な数字を示して細い説明を行い、更正の要請をした。
④ 右認定事実によれば、XがYに対して昭和49年7月期までの所得について具体的な根拠を示して更正の要請を行つたのは、昭和55年9月20日であるが、Yの指示に従つたために更正の要請が遅れたと認めることはできない。またXが更正の要請を行つた昭和55年9月20日にはすでに昭和49年7月期については5年の除斥期間が経過しており、昭和50年7月期についても同月30日を経過しては更正ができなかつた(昭和50年7月期については5年の除斥期間が経過するのは、昭和55年9月30日である。)のであるから、昭和49年7月期及び昭和50年7月期について除斥期間が経過したことについて、Yに特段の責められるべき点があるとはいえない。
したがつて、本件において右の5年の除斥期間の規定の適用が許されないと解すべき特別な事情が存するとはいえない。
⑤ 以上によれば、昭和49年7月期及び昭和50年7月期について減額更正処分が可能な期間を経過しているとして減額更正処分を行わず、本件事業年度の繰越欠損金の計算上昭和49年7月期及び昭和50年7月期に生じた欠損金額はないものとして行われた本件更正処分は正当である。
(4)控訴審判決要旨(棄却)(上告)
同旨
(5)上告審判決要旨(棄却)(確定)
同旨
大阪地裁平成元年6月29日判決(行裁例集40巻6号778頁)(棄却)(確定)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 原告X株式会社は、婦人・子供用下着、寝室着等の製造販売を営む内国法人である。
② Xは、昭和52年5月1日から昭和53年4月30日までの事業年度(以下「昭和53年4月期」という。以後の事業年度についてもこれにならつた呼称を用いる。)から、粉飾決算をするようになつた。昭和53年4月期及び昭和54年4月期(以下「本件係争各期」という。)について、争われた。
Xは、主として、在庫、売掛金を実際より増やす等の方法で粉飾を行い、その翌事業年度の期首に、前事業年度に仮装した経理金額(以下事実を仮装して経理することを「仮装経理」といい、仮装経理をしたことにより生じる金額を「仮装経理金額」という。)を帳簿上反対仕訳した。
右反対仕訳を含む経理は、いずれも取締役会の議決を経て、株主総会の承認を得、Xは、これに基づき、確定申告を行つた。
③ Xは、所轄税務署長Yに対し、前記のとおりの修正の経理を含んだ法人税確定申告書を提出しているにもかかわらず、課税当局は、Xの本件係争各期の各法人税についてなんら適切な指示あるいは処分をせず、更正処分を行うことについての期間の制限(国税通則法70条2項、1項)を失念して、漫然とこれを徒過したため、本件係争各期の各法人税についての更正処分を行うことが不可能となつたのであり、Yの右義務の懈怠は違法であるととし、国家賠償請求をした。
④ これに対し、被告国は、Xは、仮装経理金額につき、その翌事業年度の期首に、帳簿上反対仕訳をしているものの、その事業年度の決算財務諸表において、特別損益の項目で前期損益修正損等を計上するなどして修正の事実を明示していないから、右処理は、法人税法(以下「法」という。)129条2項(更正に関する特例)にいう「修正の経理」に当たらないため、税務署長に更正義務は存在しないと主張した。
(2)本件の主な争点
「修正の経理」の意義についてである。
(3)判決要旨(棄却)(確定)
① 法129条2項に規定する「確定した決算」とは、株主総会において承認を得た決算のことであるから、修正の経理は、企業が決算に際して作成すべき財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)上なされるべきこととなる。
ところで、同条項の修正の経理については、法は、その定義につき別段の定めを設けていないが、これを考えるに当つては、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準にしたがつてなされるべきである(法22条4項参照)。また、一般には、法人税について過大申告がなされた場合、税務署長は、正しい税額を納付させるため、更正処分を行い、過大に納付されている税額は還付加算金を付して還付することとされているところ、法129条2項は、仮装経理に基づく過大申告の場合には、税務署長は、確定した決算において修正の経理がなされ、これに基づく確定申告書が提出されるまで更正をしないことができることとし、また、減額更正処分がなされた後の還付方法についても、法70条1項、134条の2において、全額を一時に還付することなく、更正の日の属する事業年度前1年間の各事業年度の法人税相当額だけを還付し、残額は爾後5年間に納付することとなる各事業年度の法人税額から税額控除することとされている。
② 右各規定の趣旨は、自ら、粉飾決算をして意識的に多く納めた税金を、還付加算金を付して一時に還付するということは、数年間の税金を一時に還付するという点において財政を不安定にするおそれがあるのみならず、申告納税制度の本旨からみても好ましくないこと、また、粉飾決算をなくして真実の経理公開を確保しようという要請とも相容れないものであることから、粉飾決算をした法人が自ら仮装経理状態を是正するまでは減額更正を留保し、また、還付についても通常の場合より不利に扱うことにするとともに、その是正方法も一定の厳格な方法によつて既往事業年度の経理を修正した事実を明確に表示することを義務づけ、その負担により、財政の安定をはかると同時に粉飾決算を未然に防止することをも目的とするものと解される。したがつて、法129条2項の修正の経理の意味内容を解釈するに際しても、右のような法の趣旨を踏まえてなされる必要がある。
③ 法129条2項の修正の経理の意義を考えると、過年度の仮装経理は、当期の営業活動や財務活動ではないから、右仮装経理による損益の修正は、企業会計原則(損益計算書原則6特別損益・注解注12特別損益項目について)に則れば、特別損益項目中で前期損益修正損等と計上してなされるべきことになる。また、右のような解釈は、企業会計は、企業の財務状態及び経営成績に関して真実の報告を提供しなければならず、財務諸表によつて、利害関係者に必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならないとの企業会計原則の一般原則(真実性の原則及び明瞭性の原則)に合致し、さらには、法がいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準にも合致するというべきであり、また、粉飾決算を防止し併せて真実の経理の公開を確保しようとする前記法の趣旨・目的とも合致するというべきである。したがつて、修正の経理とは、財務諸表(損益計算書)の特別損益の項目において、前期損益修正損等と計上して仮装経理の結果を修正して、その修正した事実を明示することであると解すべきである。
④ これを本件についてみると、Xは、本件係争各期(及びその後の事業年度)の仮装経理金額につき、その翌事業年度の期首に、帳簿上反対仕訳をする処理をしたが、その後の事業年度の決算の際の財務諸表において、特別損益の項目で前期損益修正損等と計上するなどして修正の事実を明示したことはないことが認められる。そうすると、修正の経理に関する前記解釈を前提とすれば、本件係争各期の仮装経理金額につき、修正の経理がなされたことはないというほかはない。
⑤ Xは、本件係争各期の仮装経理金額については、それぞれの翌事業年度の期首に反対仕訳がなされており、これによつて修正の経理がなされたものである旨主張する。しかしながら、Xは、期首に反対仕訳を行つた事業年度の期末になつても粉飾をする必要があるときは、改めて仮装経理金額を計上する方法によつて仮装経理を継続してきたものであり、Xがその期首に前事業年度の仮装経理金額につき反対仕訳を行つた昭和54年4月期及び昭和55年4月期の期末には、改めて前事業年度期末の仮装経理金額累計額を上回る金額の仮装経理がなされていることが認められるから、Xは、期首に反対仕訳をした右各事業年度においても、粉飾の項目及び金額について変更を加えたのみで、前事業年度から継続して、しかも仮装経理金額累計額を前事業年度よりも拡大して前事業年度からの粉飾を継続していたというべきであり、決算においては、前事業年度の仮装経理の修正を全くなしえていないというほかはない。
⑥ Xは、粉飾決算を行つた法人に特別損失または前期損益修正という形での修正を要求し、粉飾決算の事実が明らかになるような形式で決算書類の承認を求めることは、税務の現状からは無理である旨主張する。しかし、粉飾決算を行つた役員自らこれを明らかにすることは自らを窮地に陥らせる結果につながるため事実上困難な面があることは否定できないとしても、それは粉飾決算を行つた役員自身の責に帰すべきものであつて、正確な財務諸表を作成して利害関係者に企業の財政状態や営業成績について正確な情報を提供することによる利益を制約してまで、粉飾決算を行つた役員の利益を保護する理由はないのであり、かえつて、粉飾決算をすることによつて過大に納付した税金の還付を受けるためには厳格な要件を充たすことを必要とすることによつて粉飾決算の防止をはかろうとする法129条2項の趣旨目的をも考慮すれば、これを無理な要件ということはできない。また、たとえ、単に反対仕訳を行い、その結果が含まれた財務諸表を作成することが、粉飾決算の事後処理として会計実務の慣行となつているとしても、それが公正妥当な会計処理の基準に従つた経理の方法といえない。不公正な会計慣行を基準として法の解釈を行うことは本末転倒であることからすれば、Xの右主張は失当というべきである。
⑦ さらに、Xは、簿記会計学上、修正の経理といえば反対仕訳しか考えられない旨、また、特別損失または前期損益修正という勘定科目で処理する方法とXが行つた仮装経理金額を単に当該勘定科目で処理する方法とは、結果が同一であり、実質を重んじる税務において区別すべきでない旨主張するが、修正の経理の方法としては特別損益の項目において前期損益修正損等と計上して修正の事実を明示すべきこと及びXの行つた方法が弊害を持つ不公正な方法であることは前記のとおりであり、さらに、課税の面から粉飾決算を防止し真実の経理の公開を実現することを目的とした法129条2項の解釈において、結果の同一のみを重視することもできないのであつて、Xの主張は採用できない。
⑧ 以上で検討したところによれば、Xは、法129条2項の要求する確定した決算における修正の経理を経ていなかつたため、Yには減額更正義務が存在しなかつたというべきであるから、右義務の存在を前提とするXの被告国に対する国家賠償請求は理由がない。