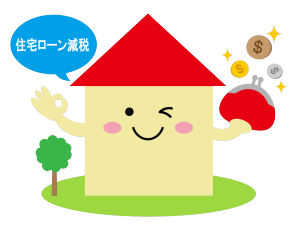個人の場合
原則として、不動産の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期(譲渡日)は、譲渡所得の基因となる不動産の引渡しがあった日によります(所基通36-12)。
ただし、納税者の選択により、その不動産の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、それが認めれます(所基通36-12ただし書き)。取得日も、同様な考え方となります(所基通33-9)。
つまり、原則、譲渡日は引渡日となりますが、納税者が契約効力発生日を選択してもよいということになります。ただし、原則として譲渡代金の決済を了した日より後にはなりません(所基通36-12(注)1)。
また、所有権移転登記日は関係ありません。例えば、年内に譲渡代金の総額(又は一部)を受領し、引渡しが終了しているにもかかわらず、買主の都合で登記(又は資金繰り)が翌年以降となったからといっても、登記の日(又は残金を受領した日)が譲渡日とはなりません。
土地等又は建物等を譲渡した場合における分離長期譲渡所得及び分離短期譲渡所得の区分は、その譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えるか否かにより判定します(措法31①、32①)。
分離短期譲渡所得に対する税率は、一律39.63%(所得税30.63%、住民税9%)です。一方、分離長期譲渡所得に対する税率は、一律20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です(10年超所有軽減税率の特例を受けない場合)。
短期なのか長期なのかで倍くらいの税金が違ってきますが、これは、短期で売買を繰り返すことを防止する政策的見地からそうなっています。
よって、所有期間の考え方が大切となりますが、取得日を売買契約の効力発生日(契約ベース)とし、譲渡日を引渡日(引渡ベース)とすることは可能です。
つまり、納税者有利で取得日、譲渡日を選択することができるので、取得日、譲渡日とも引渡ベース譲渡所得を申告しなくてはいけないというわけではありません。
分譲マンションの場合
マンションの建築完了前に、そのマンションの分譲業者と売買契約を締結し、その契約に基づき建築が完了したマンションの引渡しを受けた場合のマンションの取得日は、マンションの建築が完了した日(契約ベース)又はマンションの引渡しを受けた日(引渡ベース)のいずれかの選択となります。
売買契約の締結時において、取得する予定の建物の建築が完了していない場合、売買契約の効力が発生する建築完了日以後が取得日となるからです(措法36の2、措通36の2-16(注))。
法人の場合
原則として、土地、建物の譲渡に係る収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入します(法基通2-1-14)。
ただし、法人がその不動産の譲渡に関する契約の効力発生の日において収益計上を行っているときは、その効力発生の日は、その引渡しの日に近接する日に該当するものとし、その契約の効力発生の日の属する事業年度の益金に算入することも認められています(法基通2-1-14ただし書き、法法22の2②)。
なお、土地又は土地の上に存する権利で、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができます(法基通2-1-14(注)、2-1-2後段)。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
なお、法人税基本通達逐条解説十訂版144頁(税務研究会出版局)による2-1-2の解説において、次のように書かれています。以下、引用。
「この後段部分の取扱いは、通常の不動産の販売についてまで一般的に適用することは考えられていないことに留意すべきである。あくまでも山林、原野のように一般の例によっては引渡しの日の判定が困難な場合で、しかも実体的にはすでに引渡しが行われ、収益も実現しているにもかかわらず、長期にわたって既収代金が仮受金等として経理され、課税上も弊害が生じるというようなケースについて、特殊な引渡しの判断基準として適用することが考えられているということである。」
東京地裁平成24年1月25日判決(税資262号-12(順号11862))(棄却)(控訴)(所得税)
(1)事案の概要
① 本件は、原告Xら(納税者)が、平成19年に、訴外会社A社との間でB区所在の甲土地建物及び乙土地建物(本件各物件)を譲渡する旨の売買契約(本件各契約)を締結し、売買代金の9割に相当する契約時金を受領するとともに、A社に所有権移転登記申請手続に必要な書類を交付し、同日に所有権の移転登記を完了した後、平成20年になってA社に本件各物件を明け渡したという事実関係の下において、本件各物件の譲渡に係る譲渡所得(本件各譲渡所得)の総収入金額の収入すべき時期が争われている事件である。
② Xらは、本件各譲渡所得について、平成19年分に帰属するとして所得税の申告をした後に、本来は平成20年分に帰属すべきものであったとして更正の請求をしたところ、Y(課税庁)から、本件各譲渡所得は平成19年分に帰属するものであり更正をすべき理由がない旨の通知を受けたことから、上記各通知処分の取消しを求めて本訴を提起した。
③ Xらは、本件各契約において、(イ)Xらの本件各物件の立ち退き及び動産撤去の完了、(ロ)売買代金全額(残代金)の受領と同時のA社に対する鍵の引渡し、(ハ)管理責任の移転、(ニ)危険負担の移転及び(ホ)解除権の消滅が、いずれも平成20年7月28日であり、また、(ヘ)明渡日である同日までは、「使用・収益する権利」はXらに帰属しており、XらからA社に対する本件各物件の現実の支配の移転あるいは実質的な支配管理の変動が生じた日(引渡しがあった日)は平成20年7月28日であって、同日の現実の引渡しにより初めてA社に対する譲渡代金請求が確定的となったとして、本件各譲渡所得は平成20年分に帰属すると主張した。
(2)主な争点
所得税の額の計算上、本件各譲渡所得の帰属する年分が、平成19年分であるか(Yの主張)、平成20年分であるか(Xらの主張)であり、つまり、「明渡し」と所得税基本通達36-12の「引渡し」は同じであるか否かである。
(3)判決要旨(棄却)(控訴)
① 特定の資産の譲渡に係る譲渡所得がいずれの年分の所得に帰属するかは、当該譲渡所得に係る収入金額が所得税法36条1項の「収入すべき金額」に当たると評価されるに至った時期のいかんによって判断されるものと解されるところ、これについては、一般に、譲渡をした者による資産の引渡しがあれば、通常、その時点で、相手方に対してその対価を請求することができることが確定的となり、所得税法が採用する権利確定主義の趣旨に照らし、仮にその時点では現実の収入がなくても、その金額をもって、同項にいう「収入すべき金額」として評価し得る状態となったものとみることができるといえ、所得税基本通達36-12が、譲渡所得に係る総収入金額の収入すべき時期は、原則として、その所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする旨定めているのは、この趣旨をいうものとして相当であると解される。
② 所得税法の採用する権利確定主義の趣旨によれば、特定の資産の譲渡により支払われる対価が所得税法36条の「収入すべき時期」に当たると評価される時期は、その現実の支払がされた日よりも遅れることはないと考えられるのであって、所得税基本通達36-12の注書1は、この当然の事理を確認的に述べたものにすぎないと解される。
③ 本件において、(イ)売買契約書には、各物件の所有権は、売買代金の9割に相当する契約時金の支払と同時に、XらからA社に移転し、Xらは、各物件を引き渡すものと定められていたところ、実際に、契約日である平成19年11月29日に、約旨に従い契約時金が支払われ、所有権も移転したこと、(ロ)実際に各物件につき所有権移転登記がされていること、(ハ)所有権移転後は、公租公課をA社が負担することになったことに加え、一般に不動産の引渡しは占有改定(民法183条)の方法によってもすることができることを考慮すると、各物件については、契約書の定めるところに従い、契約時金の支払がされた日に、A社に占有改定の方法により引渡しがされたものと認められ、このことを踏まえると、各物件の譲渡に係る収入金額は、上記の日の属する年における収入すべき金額に当たるものとみるのが相当である。
東京地裁平成26年1月27日判決(税資264号-16(順号12397))(棄却)(確定)(法人税)
(1)事案の概要
① 本件は、X(原告会社)が、借地人の存在する本件土地を売却して受領した代金等について、買主T(東京都)において本件土地の使用収益ができることとなった日(本件土地上の建物等が取り壊された平成21年7月)を引渡しの日とすべきであるから、売買代金等に係る収益の額は平成21年12月期の益金の額に算入されるとして確定申告をしたところ、Y(課税庁)が、本件土地の現実の支配が移転した時期(平成20年11月)にその引渡しがあったというべきであるから、売買代金等に係る収益の額は平成20年12月期の益金の額に算入すべきであるとして更正処分等をしたため、Xがその取消しを求めた事件であり、具体的な事実関係は以下のとおりである。
② Xは、不動産の賃貸及び金銭の貸付業を目的とする合資会社であるところ、本件土地を売却した当時、複数の土地を所有しており、そのうち大半の土地には借地人が存在していた。
③ Xは、平成20年11月13日、Tとの間で、X所有の本件土地をTの事業用地として譲渡する旨の契約(本件売買契約)及び本件土地の譲渡に伴い残地となる土地について、TからXに対して残地補償金(本件残地補償金)を支払う旨の補償契約(本件残地補償契約)を締結した。本件土地の所有権移転登記は平成20年12月26日に完了し、平成21年1月16日にTからXに売買代金が支払われた。
④ Tは、平成20年11月13日、本件土地の借地人との間で、借地上の建物等を同借地人が移転期限(平成21年3月31日)までに撤去する旨の物件移転補償契約を締結した。その後、移転期限は平成22年3月31日に延長され、平成21年7月7日に撤去が完了した。
⑤ Xは、平成20年12月期の法人税の確定申告において、本件土地に係る譲渡益及び本件残地補償金を収益の額に計上しなかった。
⑥ Xは、平成21年12月期の法人税の確定申告において、本件土地に係る譲渡益及び本件残地補償金を収益の額に計上するとともに、租税特別措置法64条の2(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に基づき、これらを圧縮特別勘定に繰り入れて損金の額に算入した。
⑦ Yは、本件土地に係る譲渡益及び本件残地補償金は、平成20年12月期の収益の額であるとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った(なお、平成21年12月期については、Xが収益の額に計上していた本件土地に係る譲渡益及び本件残地補償金を所得の金額から減算するとともに、損金の額に算入していた特別勘定繰入損を否認して所得の金額に加算する等の減額更正処分を行った。)。
⑧ Xは、上記⑦の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を不服として、審査請求を経て本訴を提起した。
(2)主な争点
本件売買代金及び本件残地補償金に係る収益の額を原告の法人税の確定申告において益金の額に算入して計上すべき時期がいつかである。
(3)判決要旨(棄却)(確定)
① 法人税法上、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、同法22条(各事業年度の所得の金額の計算)5項に定める資本等取引以外の取引に係る当該事業年度の収益の額とするものとされ(同条2項)、当該事業年度の収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(公正処理基準)に従って計算すべきものとされている(同条4項)。したがって、ある収益の額をどの事業年度の益金の額に算入して計上すべきかは、公正処理基準に従って判断すべきであり、これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入の原因となる権利(収入すべき権利)が確定した時の属する事業年度の益金の額にその額を算入して計上すべきであると解される(最高裁平成5年11月25日第一小法廷判決参照)。また、法人税基本通達2-1-14及びこれにおいてその例によるものとされている同2-1-2(棚卸資産の引渡しの日の判定)は、上記の公正処理基準に従い、固定資産の譲渡に係る収益の額の計上時期について上記に述べた権利確定主義を採用し、その収益の額をいつ益金の額に算入して計上すべきかを具体的に示したものであって、法人税法22条4項の趣旨にも適合するものと解するのが相当である。
② 不動産の譲渡の取引においては、代金の支払と同時に当該不動産の引渡しや所有権の移転の登記がされることにより取引が一時に完了し、法人税基本通達2-1-14にいう「引渡しがあった日」が客観的に明白な場合がある一方、諸般の事情から各契約当事者の給付等が段階的に複数回に分けてされ、外見上は上記の「引渡しがあった日」や収益が実現したといえる日が必ずしも明らかでない場合も生ずるが、後者のような場合には、契約上買主に所有権がいつ移転するものとされているかということだけではなく、代金の支払に関する約定の内容及び実際の支払の状況、登記関係書類や建物の鍵等の引渡しの状況、危険負担の移転時期、当該不動産から生ずる果実の収受権や当該不動産に係る経費の負担の売主から買主への移転時期、所有権の移転の登記の時期等の取引に関する諸事情を考慮し、当該不動産の現実の支配がいつ移転したかを判断し、上記の現実の支配が移転した時期をもって、当該不動産に係る上記の「引渡しがあった日」であると判断するのが相当である。
③ 本件各売買契約においては、代金の支払、所有権の移転、所有権の移転の登記及び土地の引渡しをするものとされる日がそれぞれ異なっているから、基本通達2-1-14にいう「引渡しがあった日」が客観的に明白であるとは認められない。
④ (イ)本件各売買契約の締結日である平成20年11月13日に土地1ないし3の所有権がXからTに移転するものと定められていること、(ロ)各売買契約の締結日である同日にXからTに対して所有権の移転の登記を嘱託するために必要な書類が提出され、土地3については同年12月17日に、土地1及び2については同月26日に、それぞれ同年11月13日売買を原因とする所有権の移転の登記がされていること、(ハ)Xは、Tに対し、本件各売買契約の締結日に売買代金に係る請求書を提出していたこと、(ニ)所有権の移転の登記が完了したことに伴い、それ以後は、土地1ないし3に係る固定資産税等の公租公課をTが負担することになったこと、⑤Tは、同年11月13日以降、本件各借地人及び借家人との間で、土地1及び3上にある物件の移転及び立ち退きについてそれぞれ個別の契約を締結したほか、各物件の移転期限及び立ち退き期限の延長も合意している反面、Xはこれらの点に全く関与していないことの各事情を総合して考慮すると、土地1ないし3の現実の支配は平成20年11月13日にXからTに移転したものと認められ、同日が基本通達2-1-14にいう「引渡しがあった日」であると認めるのが相当である。
⑤ 本件土地4は、土地3と一団の土地を成していたところ、土地3をTがXから買い取った結果、残地となったこと、本件残地補償金は、土地3をTがXから買い取った結果生ずる損失を補償する性質のものであること等の各事情を踏まえると、残地補償金は、平成20年11月13日の属する事業年度の収益の額に当たる。