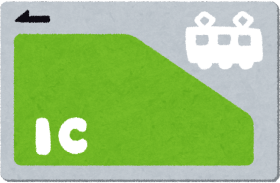概要
副業といっても、アルバイト代は給与所得ですし、家賃収入は不動産所得です。これらは事業所得や雑所得ではありません。
従来、個人が副業といった場合、アルバイト(給与所得)や不動産所得が多かったのですが、最近は多様化してきており、特に増えているのは、将来の独立を見据えての自営業主形態です。
こういった自営業主形態、つまり、給与所得や不動産所得に該当しないような自分で行うビジネスの場合、事業所得なのか雑所得なのかという問題が生じます。
専業(本業)であれば、商いが小さくても、通常、事業所得ではないと税務署に否認されません。ただし、副業で行われるビジネスの場合、問題になるということです。
例えば、サラリーマンの場合、副業が事業所得であり赤字であれば、損益通算にて給与所得から赤字分を差し引くことができるので、結果的に、本業の給与所得で源泉徴収されていた所得税等が減少、還付されるということになります。
例えば、年間の給与収入600万円がある方で、給与所得控除や所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除や生命保険料控除)を差し引いて算出された所得税額(源泉徴収税額)が仮に20万円だったとします。
確定申告をすれば、事業所得の赤字があれば給与所得と損益通算(相殺)できるので、払いすぎた所得税額(源泉徴収税額)の一部が還付されます。事業所得の赤字が大きければ、所得税額(源泉徴収税額)が丸々還付される場合もあるでしょう(例でいえば、20万円)。
一方、雑所得の場合は他の所得と損益通算ができません。なお、副業が絶対に事業所得と認められないというわけではありませんが、過去の税務裁判例からすると、事業性を認定するうえで重要な要素となっています。
ただし、副業を推進する政府の方針との関係もあり、今後の課税庁の対応や税務裁判を注目したいと思います。
令和4年分以後の取扱い(通達改正)
令和4年8月の国税庁の対応
令和4年8月1日、国税庁は、副業に対して、事業所得か雑所得かの争いが多いため(今後の増大を未然に封じるため)、以下のように、所得税基本通達35-2(令和4年分以後の所得税について適用)が改正される予定であるとし、それに対して、意見募集がされました(募集期間は同年8月31日まで)。
| (注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。 |
つまり、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、副業であり、かつ、その収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、雑所得として取り扱うということでした。収入金額とは所得金額のことではなく、簡単に言うと、売上金額のことです。
「特に反証がない限り」とありますが、これは、例えば、長年継続して事業所得で申告し、それによって生活していたものの、新型コロナの影響などといった特殊な事情により、事業収入金額が300万円以下になり、生活のために他にアルバイトをして給与所得があるような場合等でしょう。
長年サラリーマンをしているが、会社が副業解禁となったので副業始めて収入300万円以下です、なんていうのは、当然、雑所得になるという予定でした。
〇「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0
令和4年10月の国税庁の対応
上記の通達改正案に対して、令和4年8月31日までに7,059件もの意見が寄せられましたが、上述の改正案に反対する意見が多く、それを受けて国税庁は、同年10月7日、以下のように所得税基本通達35-2改正案を大幅に修正しました。
| (注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。 |
また、意見に対する国税庁の考え方として、以下のようなことが記載されています。
- 事業所得又は業務に係る雑所得に対する従来からの考え方に変更を加えるものではありませんので、税負担額が変更されるものではないと考えています。
- 事業所得と業務に係る雑所得の所得区分の判定については、パブリックコメントにおける御意見を踏まえ、主たる所得かどうかで判定するという取扱いではなく、所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務づけられている点に鑑み、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定することとし、通達を別添のとおり修正いたしました。
- 収入金額が 300 万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります。
- 所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務づけられているところ、一般に帳簿書類の保存がある場合には、営利性や有償性、継続性や反復性、自己の危険と計算における企画遂行性があると考えられることから、反証に代えて、帳簿書類の保存がある場合には、原則として、事業所得に区分することとし、別添のとおり通達を修正いたしました。
これにより、副業による収入金額が 300 万円以下であっても、記帳をし、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります。8月の段階とは大幅に考え方が変わっており、帳簿の有無が重視されています。
〇事業所得と業務に係る雑所得等の区分(国税庁HP「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」のイメージ図を改変)
| 収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存なし |
| 300 万円超 | 概ね事業所得(注) | 概ね業務にかかる雑所得 |
| 300 万円以下 | 業務に係る雑所得 |
記帳・帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得、つまり、概ね事業所得となりますが、個別判断が必要なものがあるとして、国税庁は、「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」で、以下のように示しています。
| 事業所得と業務に係る雑所得の区分については、上記の判例に基づき、社会通念で判定することが原則ですが、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。 (注)その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。 ① その所得の収入金額が僅少と認められる場合 例えば、その所得の収入金額が、例年、300 万円以下で主たる収入に対する割合が 10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。 ※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。 ② その所得を得る活動に営利性が認められない場合 その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます ※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。 |
よって、サラリーマンが副業をする場合、以下の点は最低限注意をする必要があるといえます。
(1)帳簿書類を作成、保存をすること
国税庁の考え方として、「帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分」としている以上、帳簿書類を作成、保存すべきだということになります。
(2)収入金額を300万円超とするか本業の収入の1割以上とすること
所得(利益)金額ではなく、収入(売上)金額なので、これをクリアするのは、さほど、難しくないかと思われます。
(3)連年(目安は3年)継続して赤字にならないこと
下記で詳しく説明していますが、副業が事業所得か雑所得で争われた税務裁判例・裁決例の多くが、その取引等で連年継続して損失が生じており、給与所得などと損益通算しているケースです。ですから、これに引っかからないように注意が必要です。3年連続して副業が赤字を続け、その赤字を本業の給与所得と損益していれば、税務調査が入り、雑所得と言われるでしょう。3年連続して赤字を続けていれば、赤字解消のための取り組みを進めていると主張しても、通らない可能性が高いです。
〇「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410040064&Mode=1
〇国税庁HP「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
新たな情報が入りましたら、すぐにアップデート
この改正について、新たな情報が入りましたら、すぐにアップデートします。
事業所得、雑所得(公的年金等に係るものを除く。)の所得金額の計算方法の違い
事業所得、雑所得(公的年金等に係るものを除く。)の所得金額の計算方法は、ともに「総収入金額-必要経費」であり、大きな違いはありません(所法27②、35②二)。
ただし、所得(総収入金額-必要経費)の金額の計算上、損失となった場合に違いが生じます。事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、給与所得など他の所得と損益通算(所法69①)できますが、雑所得ではできません。あくまでも、雑所得内での通算しかできません。
「雑所得」の分類は、シャウプ勧告に基づく昭和25年の改正で設けられたのですが、当時は、雑所得の計算上生じた損失については、特に制限がなく他の所得との通算が認められていました。
しかし、昭和43年に、雑所得の計算上生じた損失については他の所得との損益通算を認められないとされたのですが、これは、「雑所得の必要経費の支出内容には家事関連費的な支出が多いこと、必要経費が収入を上回る場合があまり考えられず、損益通算を存置する実益が少ないこと」(武田昌輔「DHCコンメンタール所得税法」2674頁)などの理由からとされています。
「必要経費が収入を上回る場合があまり考えられず、損益通算を存置する実益が少ないこと」を理由として損益通算を認められないとされたといいますが、事業所得なのか雑所得なのかで争われた裁判例・裁決例の多くが、納税者が行っている本業以外の取引等で連年継続して損失が生じており、給与所得などと損益通算しているケースです。
そして、争いのほとんどが事業所得とは認められず雑所得に該当すると判断がされています。
なお、そのほか、事業所得と雑所得の間には、資産損失の必要経費算入額(所法51)にも違いがあり、さらに、事業所得について青色申告制度を適用すれば、青色申告特別控除(措法25の2)、青色事業専従者給与(所法57)、純損失の繰越しと繰戻し(所法70、140)、中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措法28の2)等の点で税制優遇が受けられます。
ただし、サラリーマンの副業が事業所得なのか雑所得なのかで争われる最大の理由は、損益通算ができるか否かです。例えば、事業所得で年間20~30万円の所得があるが、青色申告特別控除額の範囲内なので、結果的に副業による納税0円といったケースも、本来、過去の裁判例・裁決例の判断基準に当てはめれば、雑所得になるというのがほとんだと思います。
ただし、そのようなケースで争われた裁判例・裁決例は、私が調べた範囲ではありませんでした。つまり、副業が赤字で給与所得や主たる事業所得と相殺しているようなケースが狙い撃ちされて税務調査に入られ、結果的に、裁判例・裁決例になるようなものが出てくるということです。
納税者が行っている本業以外の取引(経済活動)等が事業所得か雑所得で争われた裁判例・裁決例の多くが、その取引等で連年継続して損失が生じており、給与所得などと損益通算しているケースです。そして、ほとんどが事業所得とは認められず雑所得に該当すると判断がされています。
裁判例からわかる事業所得、雑所得か否かの判断基準
1つ目の裁判例は、事業所得に該当するか否かを判断するうえで極めて有名な弁護士顧問料事件(最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決・民集35巻3号672頁)です。弁護士が複数の会社から受け取った顧問料収入を給与所得であると確定申告をしたところ、課税庁は事業所得であるとし更正処分等をしたことにより争われたのですが、本判決では、事業所得について、以下のように判示しています。
「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。」
2つ目の裁判例は、会社役員をしている納税者が6年間にわたって年間数百回行っていた商品先物取引が、営利性及び継続性は認められるとしても、所得税法施行令63条12号にいう「事業」には当たらないとして、事業所得の金額を計算するのに右取引による損失額を算入することはできないとした名古屋地裁昭和60年4月26日判決(行集36巻4号589頁)です。本判決では、「対価を得て継続的に行なう事業」に該当するか否かについて、具体的に、以下のように判示しています。
「一定の経済的行為が右(編注:所得税法施行令63条12号)に該当するか否かは、当該経済的行為の営利性、有償性の有無、継続性、反覆性の有無のほか、自己の危険と計算による企画遂行性の有無、当該経済的行為に費やした精神的、肉体的労力の程度、人的、物的設備の有無、当該経済的行為をなす資金の調達方法、その者の職業、経歴及び社会的地位、生活状況及び当該経済的行為をなすことにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が存するか否か等の諸要素を総合的に検討して社会通念に照らしてこれを判断すべきものと解される。」
つまり、事業所得を発生させる事業とは社会通念上事業といえるものかどうかだということであり、下記のような諸要素を総合考慮して判断する必要があるということになります。
(1)営利性、有償性及び反復継続性の有無
(2)自己の危険と計画による企画遂行性の有無
(3)その者が費やした精神的及び肉体的労力の程度
(4)人的設備及び物的設備の有無
(5)資金の調達方法(△)
(6)その者の職業・経験、社会的地位、生活状況
(7)相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性(◎)
上記で、「(5)資金の調達方法(△)」としている理由は、最近の事例では、あまり、重要視されていないからです。一方、「(7)相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性(◎)」としている理由は、どの事例においても、最重要とされているからです。
なお、学説は以下のように、種々のファクターを参考とし、社会通念によって決定するとしています。下記、金子宏・租税法第24版243頁より引用。
「事業と非事業との区分の基準は必ずしも明確ではなく、ある活動が事業に該当するかどうかは、活動の規模と態様、相手方の範囲等、種々のファクターを参考として判断すべきであり、最終的には社会通念によって決定するほかはない」
個人事業の開業届出書
稀に、「個人事業の開業届出書を税務署に提出しているから、自分の場合、事業所得になる」という方がいますが、完全に間違いです。
個人事業の開業届出書を提出していても、雑所得に該当する場合は、雑所得でしかありません。
過去の裁判例では、副業であることは事業所得か否かの判断で不利な要素となっている
事業所得であるか否かを判断する要素の1つである「副業」について、小豆先物取引が所得税法上の事業であるとする納税者の主張が排斥された京都地裁昭和59年9月6日判決(税資139号511頁)では、以下のように判示しています。
「『対価を得て継続的に行なう事業』に該当するといえるかどうかは、法27条1項、法施行令63条に規定する具体的業種を参照したうえ、諸般の事情を考慮したうえ、社会通念上、営利を目的として継続的に行なわれる事業と認められるかどうかによってきめられるべきであると解するのが相当である。そして、右の意味での事業性を認定するについて、事業所の設置、人的物的要素が結合した経済的組織体の存在することは、必ずしも必要ではないし、また、その者の本来の業務、職業としてなされている場合であると、副業としてなされている場合であるとを問わない。」
「しかしながら、営利を目的として継続的に行われる事業であると認められるためには、通例、事業所が設置され、人的物的要素が結合した経済的組織体を有し、また、主として本業として営まれるものであるから、他に特別の事情がない限り、事業所や経済的組織体の有無、本業であるかどうかは、事業性を認定するうえで重要な要素となることはいうまでもないし、継続的な営利事業というためには、継続的に相当程度安定した収益が得られる可能性があることが必要であることも、当然のことに属する。」
前段では、事業所得となるには本業、副業を問わないといいながら、後段では、本業であるかどうかは重要な要素といっています。つまり、副業であることは、事業所得か否かの判断をするに当たって、不利な要素となっているということです。
ただし、この判決は昭和の時代のものであり、副業を推進する現代の政府の方針とはあっていないといえます。よって、この考え方を令和の時代でもとるのかどうかは、現時点ではわかりません。今後の税務裁判を注目したいと思います。
関連記事
平成26年9月1日裁決(裁事96集)判断要旨
所得税法第27条第1項は、事業所得について、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得である旨規定し、その委任を受けた所得税法施行令第63条において、事業所得の事業に当たるものとして、11項目にわたり業種を例示するとともに、その他対価を得て継続的に行う事業がこれに当たる旨規定している。
このように、所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。
横浜地裁令和3年3月24日判決(税資271号-43(順号13545))(棄却)(控訴)
事件の概要
1 X(納税者)は、医療法人社団の理事長であり、同社団が経営するクリニックの医師として勤務して多額の給与所得を得ていたほか、本件制作販売等による収入も得ていた。
2 Xは、本件制作販売等に関し、一日平均4、5時間を洋画等の制作に費やしているとし、年に数回個展を開催して作品を販売するほか、画集の出版、制作・保管用アトリエの賃借、美術雑誌等への自費掲載、HPの開設を行う等していたことから、本件制作販売等から生じた所得(損失)は事業所得に該当するとして、当該損失を損益通算して各年分の所得税等の確定申告をした。
3 本件制作販売等に係る収支状況は、各年分とも、収入金額が数千円ないし数十万円であるのに対し、必要経費の額は1,000万円を超えており、いずれの年分も多額の損失が生じていた。なお、当該必要経費や自己の生活費等は、医療法人社団からの給与等で賄われていた。
4 Y(課税庁)は、本件制作販売等から生じた所得(損失)は事業所得には該当しないため損益通算できないとして各年分の更正処分等を行ったところ、Xが当該各更正処分等の取消しを求めて本訴を提起した。
本件の争点
本件制作販売等から生ずる所得(損失)は、事業所得に該当するか否か。
裁判所の判断
1 事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいうが(最判昭和56年4月24日)、具体的に特定の経済的活動により生じた所得がこれに該当するといえるかは、当該経済的活動の営利性、有償性の有無、継続性、反復性の有無のほか、自己の危険と計画による企画遂行性の有無、当該経済的行為に費やした精神的・肉体的労力の程度、人的、物的設備の有無、当該経済的行為をなす資金の調達方法、その者の職業、経歴、社会的地位及び生活状況並びに当該経済的活動をすることにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が存するかどうか等の諸般の事情を総合的に検討して、社会通念に照らして判断すべきである。
2 本件制作販売等は、有償性、継続性、反復性、Xの計算と危険における企画遂行性を有し、物的設備を備え、さらに、Xが相当の精神的・肉体的労力を費やして行っていた活動であるといえるものの、これらの活動に要する資金は、専らXが医師として診療行為を行うことにより得た給与所得及び資産から調達されており、しかも、各年分における客観的収支状況や販売実績に照らせば、多額の資金を投じる一方で、収益は全く上がっておらず、およそ相当程度の期間継続して安定した収益が得られる見込みがあったとはいえず、客観的にみて営利を目的として行われたものともいえないことからすれば、社会通念上、本件制作販売等が、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務であるとはいえず、事業に該当しない。
3 以上より、本件制作販売等から生ずる所得は、事業所得に該当せず、雑所得に該当する。