
概要
不動産管理会社の方式は、大きく分けて3つ(4つ)の方式があります。①管理委託方式、②一括転貸(サブリース)方式、③所有型法人方式です。そして、③所有型法人方式には、「建物のみ所有」と「建物・土地の両方を所有」している2つの方式があります。
すでに個人が収益物件を持っている場合であれば、管理委託方式や一括転貸方式がやりやすいのですが、過去の不動産管理会社の税務裁判例、裁決例(否認事例)の多くが、この2つの方式に集中しています。
また、所得を移転できる金額の上限でいえば、所有型法人方式(建物・土地両方所有)が一番ですが、移転コスト等により、実際利用されているのは所有型法人方式(建物のみ所有)の方が多いです。
それぞれの方式とも一長一短あるので、理解して、どの方式を利用するかじっくり検討しましょう。
① 管理委託方式
不動産管理会社にオーナー所有の賃貸不動産に係る管理等を委託し、オーナーが不動産管理会社に管理料を支払う方式です。
管理料の相場は、賃借人支払家賃総額×3~8%程度となっています。
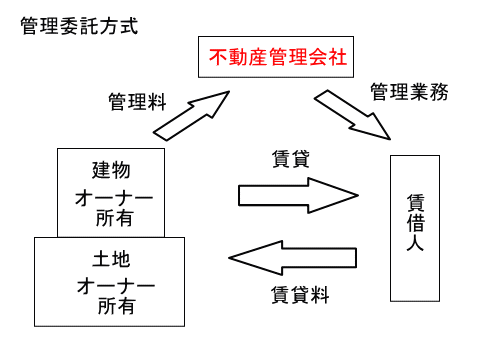
② 一括転貸(サブリース)方式
不動産管理会社にオーナー所有の賃貸不動産を一括転貸し、不動産管理会社が転貸する方式です。
不動産管理会社がオーナーに支払う一括転貸料の相場は、賃借人支払家賃総額(満室の場合)×85~90%程度となっています。
つまり、不動産管理会社の取り分は10~15%程度ということになります。上記の①管理委託方式により表面上の取り分は多くなりますが、空室リスクを不動産管理会社が負うこととなります。
なお、新築物件を一括借り上げする場合には、入居者ゼロから始めるので、それに合わせた契約(1か月目50%、2か月目75%、3か月目以降85%といったような契約)が一般的です。
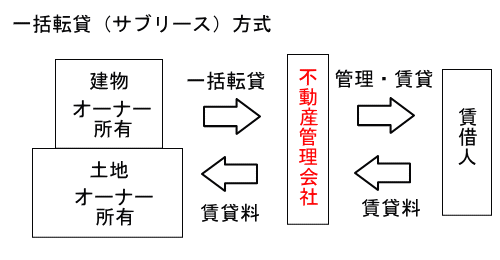
③-1 所有型法人方式(建物のみ)
不動産管理会社が建物のみを所有する方式です。借地権の認定課税を避けるため、土地の貸借について「無償返還方式」をとることが一般的です。
また、その場合も相続税対策のため、使用貸借契約をとらずに、土地の固定資産税と都市計画税の合計相当額の2~5倍程度(年額)の地代設定が多いです。
なお、個人所有の建物を不動産管理会社に売却(移転)する場合には注意が必要です。
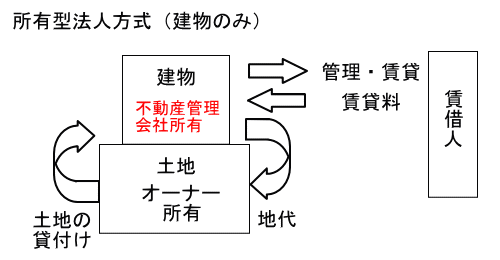
③-2 所有型法人方式(建物・土地両方)
不動産管理会社が建物・土地の両方を所有する方式です。税務リスクが最も低い方式です。
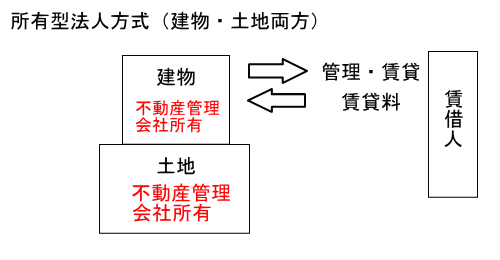
内部文章(法事例0105 法人成りに当たり個人不動産を会社に賃貸する場合)
〔問〕 法人成りに当たり、個人不動産を会社へ賃貸することにしたい。どのようなことに注意したらよいか。
〔答〕 会社が個人に支払う賃借料、権利金等については、適正な時価に相当する金額を支払わなければならない。
法人成りに当たり、個人資産を会社へ引き継ぐ場合、時価によらなければならない。仮に時価より低い価額で引継いだとすれば、受入れた法人側では時価によって取得したものとされる。一方、出資者側では、時価の2分の1未満の低額譲渡の場合であれば時価によつて譲渡があったものとみなされ〔所令169,所法59〕、時価と取得価額(減価償却資産にあっては未償却残高)との差額が譲渡所得とされる。
特に、建物については、会社が受け入れ、当該建物の敷地については、個人所有のままとする方法を採用すると、借地権の問題が起こってくるので注意しなければならない。この場合、借地人である会社は、土地所有者である個人に対して通常の権利金を支払うか若しくは、相当の地代を支払わなければ、原則として借地権の受贈益が認定される。〔法令137,法法65〕
また、借地権の受贈益の認定を受けることにより、会社の株式又は出資の価額が増加するため、その増加した部分に相当する金額を他の株主又は出資者が、その財産の提供者から贈与によって取得したものとみなされる。〔相基通9-2〕
以上のようなことから、不動産は個人所有のままにしておき、会社に賃貸するのケースが多いが、会社へ賃貸する場合においては、会社が個人に支払う賃借料、権利金等については適正な時価によらなければならない。時価を超えて支払った場合には、当該部分は、個人に対する贈与、当該個人が役員であれば役員給与とされる。
また、敷金についても相当額を超える金額を会社から受け取れば、当該部分は個人に対する貸付金とされ、その金銭が会社において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》に規定する特例基準割合による利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により、利息を徴収しなければならない。〔所基通36-49〕
